第12回
はじめてのアナキズム|松村圭一郎
2020.03.01更新
現在、世界中で脅威の広がる新型コロナウィルス感染。日本では、「先手で対応する」とのA首相の言葉が喜劇であってほしいと思わざるをえないほど、「後手」および「誤手」の連続。一例に事欠かないが、2月19日クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客を「ソフト隔離」することなく下船させ、専用バスなどの手配もなく、そのまま帰宅させてしまう。二週間ほど前の検査で「陰性」だったことだけを根拠に。当然のように、その後、下船客から陽性患者が出ている。
こうした愚策が、なぜおこなわれるのか? どうして、これほど頻発するのか?
『ちゃぶ台』Vol.5の「編集後記」で記した通りの事態ーー「何かが起こったら、機能停止。予想できない事態に直面したら、思考停止。それは、機能不全の上層部の判断を仰ぎながら仕事をすることを常とした結果」。ーーが日々、進行しているとしか思えません。本号では、「実態として無政府状態になっている」と捉えて、「ちゃぶ台5」の特集を「みんなのアナキズム」としました。
ここに寄稿してくれた松村圭一郎さんの「はじめてのアナキズム」は、刊行直後から大反響いただいておりました。これ以上、 自分たちの生活や社会が悪くなる前に。一刻も早く現政権が退陣するために。今こそ読んでもらいたい一編です。それで、このたび、著者の松村さんにお願いし、特別にミシマガへの部分転載をすることにしました。一人でも多くの方々に読んでいただきたいです。(三島邦弘)

「あたりまえ」を問う
誰もがどこかの国に生まれる。最初から国家はそこにある。国や政府は、ずっと昔からあって、空気のように自然な存在に感じられる。でも人類の長い歴史からみれば、いまのような国が誕生したのは最近のことにすぎない。いつの間に、こんなに自然であたりまえのものになったのか? はじめてのアナキズムは、そんな問いからはじまる。
「アナキズム」は「無政府主義」と訳される。なんだかきな臭い、あやしい響きがある。でも、ここまで国の存在があたりまえになった時代のアナキズムは、国家に囲まれた自分たちの生について立ち止まって考えてみる、ひとつの態度のようなものだ。
大学の授業で、ときどき学生たちに問いかける。「明日の朝、目が覚めて、日本という国がなくなっていたら、どうする?」と。きまって、みんな「はっ? なに言ってんの?」という顔になる。「もしそうなったら、大学に来る? バイトには行く? 電車は動いているかな?」とたたみかける。
誰にとってもあたりまえの存在がもしなくなったら・・・。そんな想像をめぐらすと、ぼくらが日々、当然のように繰り返していることの意味を根底から問われる。「そもそも大学って何のために行くんだっけ?」とか、「どうして働くの?」とか。
国がなければ国立大学はなくなるかもしれない。でも場所があって、学びたいという人がいれば、たぶん私はいつも通り教壇に立つ。国や政府のために授業をやっているわけでも、働いているわけでもないからだ。給料が出なくなるとしたら、食べていく方法を考えないといけないけど、それは自分で塾を開いている人と同じだ。
民営化された交通機関だって、利用する人がいれば、きっと動かすだろう。企業や市場の経済活動は、かならずしも国の存在を必要としない。
役所は機能しなくなるかもしれない。婚姻届が出せなかったら、結婚もできなくなるだろうか? そもそも、なんで自分たちが結婚するのを国に届けて承認してもらう必要があるんだっけ? そうやって考えていくと、案外、国がなくても回っていくかもしれない。
でも、やっぱり警察や軍隊がなくなったら、大混乱に陥るのでは、と不安になる。もし警察が機能しなくなったら、あなたは店に強盗に入るだろうか? 捕まらないからといって、人を殺すだろうか? そもそも警察官たちは、政府がなくなって給料が出なくなった途端、目の前で起きる盗みや暴力をただ見過ごすのだろうか? 非常時のために訓練してきた兵士は、何か起きても、その能力を活かそうとしないだろうか? もしそうだとしたら、市民の安全や平和を守るためにその職業に就いているのではなく、給料を得るためだけに働いていることになる。想像すればするほど、私たちの「あたりまえ」が問われはじめる。
国という枠組み、その枠組みを機能させる政府や行政の組織、そこで営まれる政治の役割。その意味を問うアナキズムは、世の中を考える絶好の出発点になる。さて、いまこの時代を生きるぼくらにとって、アナキズムにどんな可能性があるのか? 考えていこう。
国家なき社会はどうなるのか?
じっさいに無政府状態を経験した人類学者がいる。『アナーキスト人類学のための断章』(以文社)という本を書いたデヴィッド・グレーバーだ。彼は、現地調査のためにアフリカ南部のマダガスカルに1989年から2年間、滞在していた。グレーバーがいた小さな町の周辺では、地方政府が実質的に機能停止していた。でも彼がそれに気づいたのは、町で生活をはじめて半年後のことだった。
人びとは役場へ行き、公的な書類に署名し、木を伐る許可をとったり、葬式後の埋葬の許可書を受けとったりしていた。グレーバーが異変に気づいたのは、公務員が書類の紙を自分で買っているのを見たときだ。じっさいには誰も税金を払っていなかった。それでも、おそらく「公務員」たちは書類発行の手数料を受けとりながら役場の仕事をつづけ、人びともあたかも政府があるかのように振る舞っていた。
国家がなくなれば、人びとは殺し合ったり、強盗が家や店を荒らしたり、混沌の世界になる。そんなイメージがある。でも、グレーバーは言う。長年にわたって国家なき社会を研究してきた人類学は、そうならないことを示してきた、と。いまのような政府などの国家組織がなくても、人類はずっと秩序を維持する仕組みをもってきたし、そうした秩序を生み出せる能力があった。
グレーバーはこう書いている。
人類学がアナーキズムを伝播するもっとも明白な理由は、それが人間性に関してわれわれが手放さない多くの通念が真実でないことを、否応なく証明するからである。(『アナーキスト人類学のための断章』7頁)
ぼくらが常識だと思っていることの多くは、ほんとうにそうなのか、と問いなおすことができる。現代のアナキズムは、その問いかけを可能にする視点なのだ。(中略)
ぼくらは問題が起きたら、すぐに行政や警察などに頼ってしまう。知らないうちに問題の解決を他人任せにばかりしている。不審者を見たら警察に電話するし、駅で倒れている人がいれば、自分では声をかけずに駅員を呼ぶ。そうやって他人任せにばかりしていると、自分たちで秩序をつくったり、維持したりできっこない、と思ってしまう。でも、人間はずっとそうやって自分たちで問題に対処してきた。
いまアナキズムを考えることは、どうやったら身の回りの問題を自分たちで解決できるのか、そのためになにが必要なのかを考えることでもある。国家の制度や大きな仕組みに頼ってばかりいると、その責任や能力が自分たちにあることすら忘れてしまう。
国家が機能しなくなるとき
アフリカみたいに遅れた場所だから、自分たちで問題解決せざるをえないんでしょう? 日本で暮らしていれば、国も政府もふつうにあるんだから、それがない状態を考える必要なんてない。そう思われるかもしれない。
でも、国や政府があたりまえにあるからこそ、その問いと向き合う重要性は増している。それ以外の問題解決の手段や知恵が失われつつあるからだ。
現実には、国や行政が機能しなくなる事態がたびたび起きている。たとえば自然災害が起きると、行政のシステムは一時的にせよ機能麻痺に陥る。
2016年4月に熊本地震が起きたとき、私の母は、ひとりで家にいた。深夜の二度目の大きな揺れで、家のなかは家具が倒れ、物が散乱し、めちゃくちゃな状態になった。母は、近所の人に声をかけてもらい、一緒に近くの中学校に避難した。
避難所となった体育館は、人でごった返し、床は砂だらけだった。母や近所の人は外に出て、星空のもとで一夜を過ごした。水道は止まり、トイレはすぐに排泄物で詰まって使えなくなった。深夜、一瞬にしてライフラインが失われ、市内各地に避難者があふれた。公務員だって被災した。避難所の運営や物資の補給など、役所が適切に対応できる状態ではなかった。(中略)
行政機能が麻痺し、消防も警察も、コンビニも頼れないとき、どうしたらいいのか。頼りになるのは、隣にいるふつうの人だった。不測の事態を打開する鍵は、大きな組織ではなく、小さなつながりにある。
1995年の阪神淡路大震災のとき、倒壊した建物などから救出された人の八割近くが家族や近隣住民の手で救助された。警察や消防、自衛隊が救助したのは二割ほどだった(河田恵昭「大規模地震災害による人的被害の予測」1997)。生きるために自分たちでなんとかしていくほかない。そんな状況が、すぐ身近な場所で繰り返されている。
ときに行政やインフラなどの仕組みは頼れなくなる。それは、2018年の西日本豪雨のときもそうだったし、東日本大震災のときも、本号に出てくる周防大島で大型貨物船が橋に衝突して断水したときも同じだ。広域の大災害でもないのに、住民の命に関わる水道が40日近く復旧しない事態が、いまの日本で現実に起きている。
国や行政がつねに全国どこでも完全にカバーしているなんて幻想にすぎない。今年9月の台風15号では、一週間たっても約7万戸で停電がつづいた。2018年の大阪北部地震と台風21号で被災した家の屋根は一年以上たったいまもブルーシートで覆われたままだ。そもそも国という制度は国民全員の生活を支え、保障してくれる万能の仕組みではない。
それに災害が起きなくても、国の存在感が薄い場所はいくらでもある。瀬戸内のある島では、数年前に陸からの橋が架かるまで、お年寄りはみんな無免許で原付バイクを乗り回していた。坂の多い島でバイクは貴重な島民の足だった。橋が開通する直前、一台のパトカーがやってきて取り締まりをはじめた。慌てて70代のおばあさんが中学生と並んで原付免許をとる試験勉強をしたそうだ。
いまの日本でも、国家は隅々まで均質に社会を覆っているわけではない。まだらに、でこぼこに存在している。ときどき動かなくもなる。きっとぼくらのすぐそばにも、そんな国家とは無縁の小さなスキマがたくさん残っている。アナキズムの問いかけは、そんな誰にとっても身近なスキマのもつ意味を可視化してくれる。
国家とはどんな存在なのか?
さてここで少し歴史を遡って、そもそも「国家」がどんなものだったのかを振り返ってみよう。いま国はなくてはならない存在になっている。安全な生活を守ってくれて、何か問題が起きれば解決してくれる。みんなそう信じている。
でも歴史的にみれば、国家は、そんなやさしい存在ではなかった。アメリカの政治学者ジェームズ・C・スコットが書いた『ゾミア―脱国家の世界史』(みすず書房)には、おもに中国南部や東南アジアでいかに国家が人びとを飲み込んできたか、そこから人びとが逃れて生きてきたかが描かれている。(中略)
歴史的にみれば、国家は人民を守る仕組みではなく、人民から労働力と余剰生産物を搾りとる制度だった。当然、反乱を起こして抵抗したり、そこから逃げ出したりする者が出てくる。東南アジアの国家の盛衰史は、国家が絶えず失われる人口を捕虜獲得のための戦争で補う歴史だった。隣国との戦争に敗れて人口を補充できなければ、国家は滅亡を余儀なくされた。
国家から逃れた人びとはどこへ行ったのか? 多くは国家の支配が及びにくい険しい山奥へと逃れた。スコットが「ゾミア」と呼んだのが、そんな広大な非国家空間が広がる中国南部から東南アジア大陸部の山岳地帯のことだ。
いまも中国南部からベトナム、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマーの国境にまたがる山岳地帯には、たくさんの少数民族がいる。スコットは、それらの民族がいずれも繰り返し国家の領域から逃れ出てきた多様な人びとの層で構成されていると指摘する。
最初からそこに少数民族がいたわけではない。中国南部では、もとは同じ民族的ルーツをもつ人のなかで国家の内に臣民としてとどまった人が漢民族と呼ばれ、山地に逃れた人がミャオやヤオなどと呼ばれた。それはタイやミャンマーなどの支配的民族と少数民族の関係でも同様だ。こうして山地に、平地国家に吸収された者たちとは異なる独特の空間が生まれたのだ。
どこから来て、どこに向かうのか?
(中略)いま国家とどう向き合うべきか。そこには複数の選択肢がありうる。国家ができあがったあとに生まれたぼくらも、もう後戻りできない場所にいるわけではない。
スコットは、ゾミア的な場所が、東南アジアに限らず、世界中にあったと述べている。険しい山や森林地帯だけでなく、湖沼や湿原地帯、離島、荒れ地や乾燥地のような土地に国を逃れた人びとが生きる場を見いだしてきた。
日本にもこの非国家空間はあった。柳田国男が『遠野物語』の冒頭に書いた一文は、明治末になっても山人の世界が平地民にとって異質な存在でありつづけていたことを印象づける。
国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。
柳田は、日本人が「数多の種族の混成」であることを前提に、山に暮らす山人が日本列島の先住民だった可能性について探究した。鬼、天狗、山男、山姥・・・。日本の民話には「山」という場所への恐れと憧れが織り込まれている。山は、つねに国家に抗う「まつろわぬ民」の住処だったのだ。
宮崎県の椎葉村を訪れたとき、柳田は人びとが富を平等に均分していることに感動している(「九州南部地方の民風」)。柳田にとって、そこは社会主義の理想を実現した奇跡的なユートピアだった。戦後まで長く狩猟や焼畑で生計を立てていた椎葉村では、山の土地はすべて村の共有地だった。そして畑地などが多い家には少なく、少ししかない家には多くの山の土地を割り当てることで、貧富の差が広がらないようにしていた。
それはスコットが描いた東南アジアの山地民の姿ともぴったりと一致する。国家から距離をおいた人びとは、自分たちの社会が国家のように階層的で抑圧的な場所にならないように、慎重に平等的な社会構造を維持しようとした。山の民は、国家空間に取り込まれないために、あるいは自分たちの内側から国家が生まれないように、あえて平地とは真逆の「国家に抗する社会」をつくりだしてきたのだ。
柳田の山人研究の系譜は、宮崎駿監督のアニメ映画『もののけ姫』など、現代の寓話のなかにも息づいている。「ゾミア」の歴史は、ぼくらの物語の一部でもある。ぼくらはどこから来て、どこに向かうのか。国家なきアナキズムを生きた人びとの営みは、いまもその想像力のひとつの源泉でありつづけている。
いまここに生まれるアナキズム
『ゾミア』で描かれた「まつろわぬ民」は、たんに国家から逃れ出た者たちではない。彼らはときに国家の圧政に反乱を起こし、抵抗してきた。国家なき場所は、国家から逃れた先にあるだけでなく、国家のなかにあらたにつくりだされる。そんなある種のアナキズムが歴史を動かしてきた。
スコットは『実践 日々のアナキズム』(岩波書店)で、過去300年における重要な解放運動のすべてが警察権力をはじめ国家の法的秩序と真っ向から対決してはじまったと指摘している。
自由民主主義を実現した社会においても、不遇な状況におかれた少数者は選挙で代表を選んで社会を改善する術を奪われている。民主主義はつねに多数派のための制度だからだ。多数派の利益を守る国家の法そのものが抑圧的なとき、法の枠内でそれを改善することは困難だ。黒人への人種差別撤廃に向けたアメリカの公民権運動も、当時の法的秩序からの逸脱なしには実現しえなかった。
スコットはこう書いている。
少数の勇敢な者たちが、座り込み抗議、デモ、可決された法案に対する大規模な違反などによって法律や慣習を率先して破らなければ、解放運動の拡大はありえなかっただろう。憤慨、憤懣、憤怒によって活気づけられた破壊的な行動は、彼らの要求が既存の制度的・法的な枠組みのなかでは満たされないということを見事に露呈させた。このように進んで法を破る彼らの気持ちに内在したのは、無秩序と混乱の種を撒き散らしたいという欲求ではなく、むしろより公正な法的秩序を創出しようとする強い衝動だった。現在の法治主義が、かつてよりも寛容で、解放的であるというのであれば、私たちはその恩恵を過去の法律違反者たちに負っている。(『実践 日々のアナキズム』26頁)
よりよき生を実現するには、ときに国家のなかにあってなお国家の外側に出ることが必要になる。そこでのアナキズムは、かならずしも国家体制だけに抗うものではない。
スコットは、アメリカの自動車工場で導入された最新の効率的な組み立てラインが、労働者の目立たないサボり行為でたびたび止められ、いらつきや怒りから多くの部品が損傷して欠陥部品が増え、設計が変更された例をあげている。最初に設計された「効率的」なラインでは、労働者がそれまで以上の速いペースで作業しつづける必要があった。机上で計算された「効率性」は、労働者の我慢と忍従に依存していたのだ。
アナキズムの視点は、目の前の苦しい現実をいかに改善していくか、その改善を促す力は、政治家や裁判官、専門家や企業幹部など選ばれた人たちだけでなく、日常を生きる自分たちのなかにあることを気づかせてくれる。
よりよいルールに変えるには、ときにその既存のルール自体からはみ出ないといけない。サボったり、怒りをぶつけたり、逸脱することも重要な手段になる。それなら、ぼくらにもできそうな気がする。自分の思いに素直になればいいのだから。
いやいや、ちゃんとルールを守らないとダメだ。そういう人もいるかもしれない。アナキズムは、そんな間違った真面目さとぶつかる。
なんのために、ぼくらは生きているのか、働いているのか。どんな社会で子どもを育て、仲間とともに暮らしていきたいのか。アナキズムのそもそもへの問いかけは、かならずしも自分の内なる思いや身近な他者の生きる日常が既存のルールと一致しない現実をあぶりだす。そのとき、ぼくらは何に真面目であるべきなのか?
誰かが決めたルールに無批判に従うことと、大きな仕組みや制度に自分たちの生活を委ねて他人任せにしてしまうことはつながっている。
アナキズムは、そこで立ち止まって考えることを求める。自分たちの生を見つめなおし、内なる声に耳を傾けろと迫る。「そんなことやるために生きているの?」と。
ぼくらはときに真面目であるべき対象を取り違えてしまう。ほんとうに大切なことを守るために、いやなことにはちゃんと不真面目になる。それがいますぐできる「はじめてのアナキズム」への一歩だ。
松村圭一郎(まつむら・けいいちろう)
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『文化人類学 ブックガイドシリーズ基本の30冊』(人文書院)、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『これからの大学』(春秋社)、編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)がある。
いまの時代にミシマ社のイチオシ!本

●ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』とは?
お金や政治にふりまわされず、「自分たちの生活 自分たちの時代を 自分たちの手でつくる」。創刊以来、その手がかかりを、「移住」「会社」「地元」「発酵」などさまざまな切り口から探ってきました。本号では、「宗教」と「政治」を特集の二本柱に据えました。これからの宗教とは? 政治にどう向き合えばいいか?
災害、毎年のように起こる人災。くわえて、外国人労働者受け入れ策など議論なきまま進む政策。すさまじい勢いで進む人口減少。 大きな問題に直面する現代、私たちはどうすれば、これまでとまったく違う価値観を大切にする社会を構築できるのか。「ちゃぶ台」が、未来にたいして、明るい可能性を見出す一助になればと願ってやみません。(本誌編集長 三島邦弘)
●『ちゃぶ台Vol.5』巻頭の言葉より
自然災害、人災、議論されないまま通過する法案......今、私たちをとりまく環境は、実態としてすでに「無政府状態」に近い。まともな感覚で生きようとすればするほど実感する。
そういう時代において宗教はどういう役割を果たせるのか? 自分たちの時代の政治 はどうなるのか。一人の生活者としてどう動いていけばいいのか? その手がかりを求めて、本誌の特集を企画した。(本誌編集長 三島邦弘)

●「はじめに」より
世の中どこかおかしい。なんだか窮屈だ。そう感じる人は多いと思う。でも、どうしたらなにかが変わるのか、どこから手をつけたらいいのか、さっぱりわからない。国家とか、市場とか、巨大なシステムを前に、ただ立ちつくすしかないのか。(略)この本では、ぼくらの生きる世界がどうやって成り立っているのか、その見取り図を描きながら、その「もやもや」に向き合ってみようと思う。
●10刷記念!松村圭一郎さんからの動画を公開します。
編集部からのお知らせ
8/26(水)19時〜
「ちゃぶ台編集室」開催のお知らせ
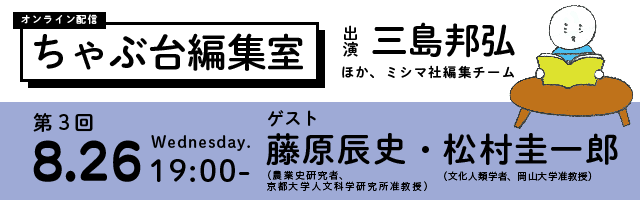
今年の秋に刊行予定のミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.6』。2015年に創刊した『ちゃぶ台』は、今年で6冊目になります。直接取材に赴くことが難しい状況で、雑誌の作り方から新たな気持ちで取り組もう。そんな思いを胸に、オンラインで雑誌について考える場所「ちゃぶ台編集室」を開室しました。
■第3回ゲスト(第1回、第2回は終了しました)
*藤原辰史
(農業史研究者、京都大学人文科学研究所准教授)
*松村圭一郎
(文化人類学者、岡山大学准教授)
■開催日時
2020年8月26日(水)
19:00〜21:00(休憩10分含む)
※本講座は全4回です。各回単発でのご参加、4回通しでのご参加、いずれも可能です。
※通しチケット(4回分)にて参加ご希望の方で、ご都合でリアルタイムでの参加が難しい回がおありの際は、後日録画動画にて受講いただくこともできます。ご希望の方は備考欄にてお知らせください。
■チケットのご購入
事前に下記オンラインチケットをご購入ください。
ご購入いただくと視聴方法のご案内を記載したチケットがダウンロード可能となります。
● 「ちゃぶ台編集室」通しオンラインチケット(全4回分 3,500円+税)
※ すでに終了しているイベントについては、動画版をお送りいたします。
● 「ちゃぶ台編集室 第3回」オンラインチケット(1,000円+税)
※ オンライン配信をご覧いただくには、インターネット環境が必要です。
※ やむを得ない事情によりライブ配信ができなかった場合、ご返金いたします。


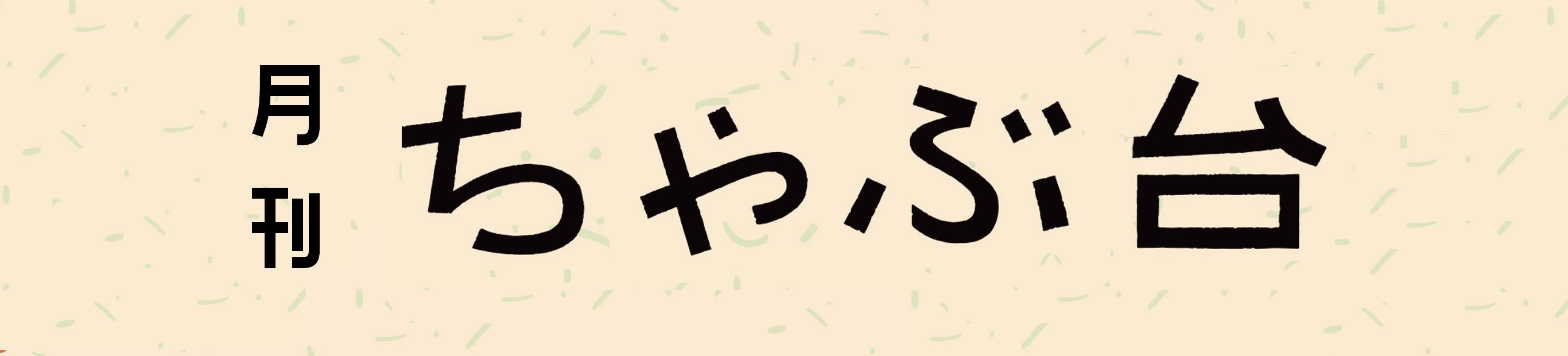


-thumb-800xauto-15803.jpg)


