第36回
これまでの『ちゃぶ台』で「書店、再び共有地」特集に登場したお店を紹介します!(前編)
2023.05.28更新
こんにちは、営業チームのスガです。
『ちゃぶ台11 特集:自分の中にぼけを持て』の発売が、来月の9日(金)に迫っています。
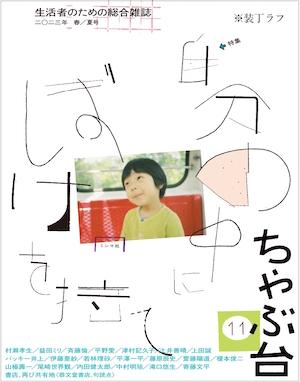 『ちゃぶ台11 特集:自分の中にぼけを持て』ミシマ社編(ミシマ社)
『ちゃぶ台11 特集:自分の中にぼけを持て』ミシマ社編(ミシマ社)
そのちゃぶ台で、恒例になっているのが「書店、再び共有地」。「居場所」となったり、町を動かす拠点になったり、地域の方の生活に欠かせない存在となっていたり。そんな書店を営業メンバーが取材するコーナーです。
始めたきっかけは、『ちゃぶ台9 特集:書店、再び共有地』の刊行です。
この特集について、代表ミシマが言葉を寄せています。
編集長より 特集「書店、再び共有地」に寄せて
社会を安定的に持続させてゆくためには、社会の片隅にでもいいから、社会的共有資本としての共有地、誰のものでもないが、誰もが立ち入り耕すことのできる共有地があると、わたしたちの生活はずいぶん風通しの良いものになるのではないか
――平川克美『共有地をつくる』
この一文のあと平川さんは、「国家のものでもないし、『私』のものでもない」、「自分一人で生きてゆくのではなく、かといって誰かにもたれかかって生きているわけでもない場所」と共有地を定義づけます。たとえば、喫茶店、銭湯、居酒屋、縁側など。
これを読んだときすぐに、間違いなく書店もそうだ、と直感しました。なぜなら、私たち(ミシマ社)は書店さんと日々、直取引をおこなうなかで、書店という場が読者、のみならず地域の人たちにとってどんどん「共有地化」しているのを感じていたからです。
いえ、なにも急に起こった現象ではありません。むしろ逆で、かつてはほとんどすべての書店がそうだった。そして、一部はそうでなくなっていた。が、いま再び共有地となっている本屋さんが次々と現れている。同時にその姿はかつてと同じではない。つまり、強すぎる地縁や共同体意識などから解放されてある。
かつてあった、ということは今もできるという裏返し。
かつて、と違うかたちなのは、現代社会が希求するかたちへ変形したということ。
現代の共有地はこうしたふたつの希望を抱えて現出してきつつあるのではないでしょうか。
本特集では、現代に生きる共有地たりうる本屋さんを、普段よりお付き合いさせていただいているミシマ社の営業メンバーたちが取材しました。
本誌編集長 三島邦弘
昨年5月の『ちゃぶ台9』の発刊から、ちょうど1年が経とうとしています。本企画のスタートから1年を記念して、『ちゃぶ台9』と『ちゃぶ台10 特集:母語ボゴボゴ、土っ!』で取材した書店を、ミシマ社メンバーが紹介します。本日は前編です!
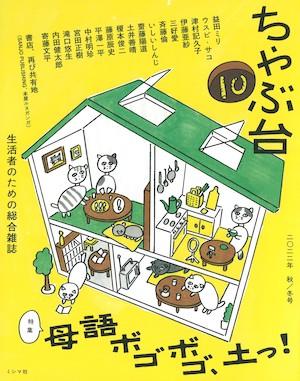 『ちゃぶ台10 特集:母語ボゴボゴ、土っ!』ミシマ社編(ミシマ社)
『ちゃぶ台10 特集:母語ボゴボゴ、土っ!』ミシマ社編(ミシマ社)
ミシマ社メンバーが「書店、再び共有地」の全登場書店を紹介します!(前編)
●うなぎBOOKS 旧塚本邸(福岡・八女/『ちゃぶ台9』)

 白壁の町並み、八女のエントランス、ハブとして、まず訪れたい場所です。併設の宿もとても素敵で、地元の「ネイティブ」なものことにギュッと出合える場所。でも、地元に閉じていない。またいつか、ゆっくり滞在したいです。(営業・イケハタ)
白壁の町並み、八女のエントランス、ハブとして、まず訪れたい場所です。併設の宿もとても素敵で、地元の「ネイティブ」なものことにギュッと出合える場所。でも、地元に閉じていない。またいつか、ゆっくり滞在したいです。(営業・イケハタ)
●本屋ルヌガンガ(香川・高松/『ちゃぶ台9』)
 私はまだお店にお邪魔したことはないのですが、『ちゃぶ台10』に掲載されている店主・中村さんのインタビューを読むと、その魅力がひしひしと伝わってきます。店内には文鳥がいるとのこと! 最近しゃべる鳥が登場する津村記久子さんの小説『水車小屋のネネ』を読んだので、ますますお店にうかがいたい気持ちが高まりました。(営業・ヤマダ)
私はまだお店にお邪魔したことはないのですが、『ちゃぶ台10』に掲載されている店主・中村さんのインタビューを読むと、その魅力がひしひしと伝わってきます。店内には文鳥がいるとのこと! 最近しゃべる鳥が登場する津村記久子さんの小説『水車小屋のネネ』を読んだので、ますますお店にうかがいたい気持ちが高まりました。(営業・ヤマダ)
・ウィー東城店(広島・庄原/『ちゃぶ台9』)

 街の人たちがなんでも相談にくる山間の本屋、ウィー東城店。「本は問題解決のツール」という佐藤店長の言葉を体現するように、本屋という垣根を越え、食品、化粧品、美容室、コインランドリーも揃っている、「よろずや」でもあります。(営業・ニシオ)
街の人たちがなんでも相談にくる山間の本屋、ウィー東城店。「本は問題解決のツール」という佐藤店長の言葉を体現するように、本屋という垣根を越え、食品、化粧品、美容室、コインランドリーも揃っている、「よろずや」でもあります。(営業・ニシオ)
●汽水空港(鳥取・湯梨浜/『ちゃぶ台9』)

 湖のほとりに佇むお店。店主のモリさんご夫妻がとっても気さくで、話しやすいのが大きな魅力です。本をレジに持っていくと、「これは知ってますか?」とさらにおすすめをしてもらえて、世界がどんどん広がります。山陰地方、農業、セルフビルドといった、このお店ならではの本やZINEも大充実で楽しい! そして本を買ったあとは、ぜひコーヒーやクラフトコーラを片手に、湖を見ながらぼーっとしてください。(編集・スミ)
湖のほとりに佇むお店。店主のモリさんご夫妻がとっても気さくで、話しやすいのが大きな魅力です。本をレジに持っていくと、「これは知ってますか?」とさらにおすすめをしてもらえて、世界がどんどん広がります。山陰地方、農業、セルフビルドといった、このお店ならではの本やZINEも大充実で楽しい! そして本を買ったあとは、ぜひコーヒーやクラフトコーラを片手に、湖を見ながらぼーっとしてください。(編集・スミ)
●毎日食堂(兵庫・南あわじ/『ちゃぶ台9』)

 定期的に帰りたくなる実家のような安心感のあるお店です。海と自然に囲まれた南あわじのお店には心地よい空気が流れます。ランチを食べて、店主の石井さんとお話ししながらゆっくり本や生活雑貨を選ぶ。最高な休日の過ごし方です。(営業・ヤマダ)
定期的に帰りたくなる実家のような安心感のあるお店です。海と自然に囲まれた南あわじのお店には心地よい空気が流れます。ランチを食べて、店主の石井さんとお話ししながらゆっくり本や生活雑貨を選ぶ。最高な休日の過ごし方です。(営業・ヤマダ)
・ブックハウスひびうた(三重・久居/現 日々詩書肆室/『ちゃぶ台9』)

 「目の前の一人から、居場所をつくる」そう理念を掲げ運営されている街の本屋さん。あらゆる立場や身分を受け入れる温かい店内と人に触れていると、いつしか自分の身体もリラックスし、優しい気持ちになってしまう不思議な本屋さんです。(営業・ニシオ)
「目の前の一人から、居場所をつくる」そう理念を掲げ運営されている街の本屋さん。あらゆる立場や身分を受け入れる温かい店内と人に触れていると、いつしか自分の身体もリラックスし、優しい気持ちになってしまう不思議な本屋さんです。(営業・ニシオ)
後半は来週日曜日(6/4)に掲載予定です。お楽しみに!
〈『ちゃぶ台9』登場書店〉【6/3(土)18時〜】佐藤友則(ウィー東城店)×三島邦弘(ミシマ社)「これが僕たちの生きる道!〜書店・出版社の枠を超えて、いま」
人口がどんどん減る、コミュニティもなくなりつつある、物価は急激に上がりたいへん・・・都市か過疎地か関係なく、私たちはこうした「下り坂」の時代に生きています。そのなかで、それでも元気に、前を向きつづけて、「次世代」へ自分たちの仕事をパスしようともがき続けている人たちがいます。
それがこの二人。
佐藤さんは、本以外にも日用品や食品、コインランドリーにパン屋と美容室まで揃っているウィー東城店を営まれています。
お客さんと話しているうちに「本は問題解決のツールだ」と気がつき、その上で本だけでは解決できない町の人の困りごとを引き受けるうちに、自然と「よろず屋」になっていったとお話されています。
出版社ミシマ社の三島は、新刊『ここだけのごあいさつ』(ちいさいミシマ社)で、少ない人数で「おもしろい」本づくりを続けていくために、社内のチームづくりに取り組んだり、社外では「一冊!取引所」というサイトをつくり、全国の出版社と書店がやりとりをする場作りを模索する様子が記されています。
二人は同世代でもあり、同じ年数を生きてきながら、全然違う道を歩んできたわけですが、いま、ものすごく見ている景色が似ているのです。
今回の二人による対談では、その景色をたっぷり語り合います。さらには、そこから、二人が現時点では気づいていない景色まで、きっと見えてくると二人とも期待しています。書店、出版社、職種は違えど、同志と慕いあう二人による記念すべき初対談!
概要
日時:6月3日(土)18:00〜19:30
参加方法:会場参加
会場:BOOK MEETS COFFEE(啓文社 BOOKS PLUS緑町 内)
住所:広島県福山市緑町1番30号 みどり町モール内
出演者:佐藤友則、三島邦弘
参加費:1,000円(税込・ワンドリンク付)
お申し込み:啓文社 BOOKS PLUS緑町店頭 or お電話(084-925-1811)


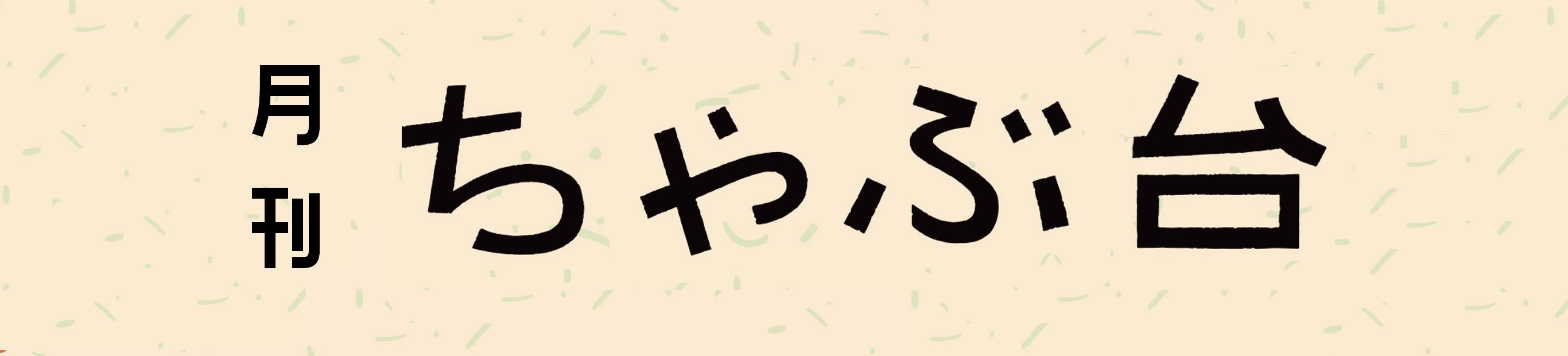
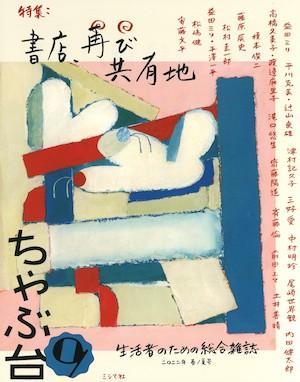




-thumb-800xauto-15803.jpg)
