第129回
顔を覚える
2025.05.14更新
人の顔を覚えることが得意な人とそうでない人がいると思う。私はまあ、ほぼ人並みというか普通だと思うが、そんなに得意な方ではない。一度会ったことの人は忘れない、などという特技はできないし、たくさんの人の名前も一度には覚えられない。大学教員をしているときもゼミ生はだいたいクラスに10名から15名くらいいて、ゼミ生というのは名前を覚えるのが必須なのだが、1週間に一度しか会わないし、すぐには覚えられないので、いつも紙を三角に折ったものに名前を書いてもらって、机の上に出してもらって、ゆっくり覚えていった。そんなに得意ではないし、かといって絶対覚えられないというわけでもない。時間をかければ覚えられる。
しかし、一度だけ、ほぼ30名以上の人たちをとても短い期間で覚えてしまったことがある。2004年に津田塾大学国際関係学科に入職した。同僚は30名以上いた。しかし、この国際関係学科の同僚に関しては、ほぼ一瞬、といっては言い過ぎだが、一回会っただけでほぼ全員を覚えてしまった。こんな経験はそれまでにはなかったし、その後も今のところ、ない。なぜこういうことができたのか、というのを考えるのは、人の名前を覚えるという基本的な仕組みに関わっているような気もする。
国際関係学科、というのは、今は珍しくないが津田塾が作った1970年代には、他には存在しなかった。東大駒場にあった国際関係論関係者が中心となって作った日本で最初の国際関係学科だったと聞いている。国際関係論という専門はあることはあるが、国際関係学科というのは、全員が国際関係論の専門ではなく、さまざまな異なる専門分野の人の集まりである。政治、経済、文化、言語、さらに私のような公衆衛生系、教育、保健体育系の講座も包含していたから、体育や心理学を専門とする教員もいた。そのような専門分野を縦軸とすれば、横軸として専門の地域、すなわち、どの地域を専門とするか、という人たちで構成されていた。例えば東南アジアの経済の研究者、アフリカの文化人類学の研究者、フランス文化の研究者、ドイツの哲学の研究者・・・。私はそこではブラジルをはじめとするラテンアメリカを中心のフィールドとする公衆衛生研究者であった。
つまり国際関係学科の教員は、専門が同じではなく、専門分野も違い、フィールドとする場も異なる。しかし、異なるからこそ、個人個人の顔と名前に、はっきりとした属性が付与されることになった。この人はスペイン語の先生、まさにスペインがフィールド、とかこの人は人口学の先生、でもスペイン語でも試験問題が作れるくらいスペイン語のできるメキシコ専門の先生・・・とか。そういう意味では同じ専門の人が「二人といない」。
人を覚える時、まだゆっくり話をしていない人ならば、その人の顔と名前とその人にまつわるストーリーで覚えていくことになる。どういう人なのか、何が好きなのか、何をやっているのか・・・だいたい多くの人に一度に会う、たとえば、上記に挙げたゼミの学生十五人、とかいうときに、1日で覚えることができないのは、今思えば、彼女たちを「一年生」とか「三年生」とかいうカテゴリー以外にまだ、彼女たちそれぞれのことを個別で知らなくて、「ゼミの学生」とそれぞれの顔、という以外にうまく付与していくような情報を知らないからだ。顔、というのは重要な個体識別の要素の一つだが、それだけでは十分ではない。
いや、しかし、顔というのが最も重要なことであるのは新型コロナパンデミックで全員マスクをするようになった時に、よくわかった。マスクをしている人の顔を覚えることは本当に難しかった。というか顔を覚える、というほど顔の特徴をみられないわけで髪型と目だけしかないのである。オンライン授業をして、画面上でもマスクを取ってもらっている時はまだ良かったが、対面に移行して、まだ全員マスクをしている、という状態の時、たった4名くらいしかいないゼミ(もその時あったのだが)でもすぐには名前を覚えられなくて往生した。
顔、声、性別(これは誠に重要だ)、背丈など外見だけでは覚えていけないので、その人にさまざまな属性を付与していって記憶する。そして付与する属性は、その人の持つものだけではなく、私自身の興味関心のあり方とリンクしていればいるほど覚えやすくなる。津田塾大学国際関係学科の場合、私は大学に入職するくらいだからまずアカデミアのことに興味があった。アカデミアで教えていること自体に興味があると同時に、一般的好奇心も強く、なんでも知りたい。さらに言語や国際関係や文化的なことには私はさらに興味があった。そういう意味では津田塾大学国際関係学科の所属教員のそれぞれの専門分野と専門地域はわくわくするくらい興味のあることだったのだ。さらに、それぞれの教員は、その専門分野と地域の、文字通り専門家なのであり、それぞれのありようが単なる興味関心を超えて、その専門分野を体現しているようなたたずまいなのである。経済学なら経済学のたたずまいで、フランス語ならフランス語のたたずまいなのか、と言われると、確かに、そうだ、としか言いようがない。経済学者のたたずまいは明らかに文学研究者とは異なり、明らかにある程度常識的で、社会的に「きちん」としている人たちであり、フランス語の先生は明らかにドイツ語の先生とは異なり、男性だが長く伸ばした髪を一つにまとめていたり、革ジャン着ていたり、これまた男性でもピンクのセーター着ていたりパープルの上着を着ていたりした。印象と専門分野もかなり深く関連している。名簿を見て、そして、専門分野と専門地域を見て、そして学科会議で一度会ったら、驚くほどに全員の名前がわかるのだ。
このように考えると、人の名前を覚える、というプロセスには、自分自身の興味と、その人の生育上で身につけてきたさまざまな属性が、他のこと、他の人より際立っていればいるほど、記憶されやすく、忘れられにくく、印象に残り続ける、ということになる。もちろんこれは学校の同窓生などのように、ひとまずは同じカテゴリー(同じ学校であるということ、年齢、性別、住んでいる地域など)にかなり入る人が多いこと、まだ、それぞれの属性というものが、大人になってからよりも際立っていないことが多いから覚えにくいということはあるだろうが、そこは、一年とか三年とか長い時間を共に過ごすから忘れることがないわけだ。
それにしても人間がはっきりと覚えていられるのは150名程度だと言われている。長い人生の間に会ってくる人のことを考えると150名は大きな数ではない。現在私は竹富島という離島に住んでいるが、島の人はいつも島にいる人は全員わかっている、という言い方をよくしていた。島は現在320名程度であるが、元々は二千人くらいいたのである。それでも島の人であるかどうかは必ずわかったということだし、話を聞いていても、竹富島の人が誰か、ということはそれぞれの家族やきょうだいも含めて全て記憶されているようだ。それだけを考えても150名ならはっきりと覚えていられる、というのは、あるカテゴリー、つまりは、「職場の同僚」とか「同窓の友人」とか「趣味の知り合い」とかそういう一つのカテゴリー内でのことなのだろうか、と思う。私自身は教員をやっていて、ゼミの担当学生が150名を越えたあたりから退職を意識するようになった。これ以上増えても覚えられない気がして、もう、この深い学生との関わりはこの辺りにしておこうか、と思ったからだ。200名を越えたあたりで退職したのはむしろキャパシティーオーバーだった。これ以上続けないことが正解だっただろう、と退職後一年の今、思っている。



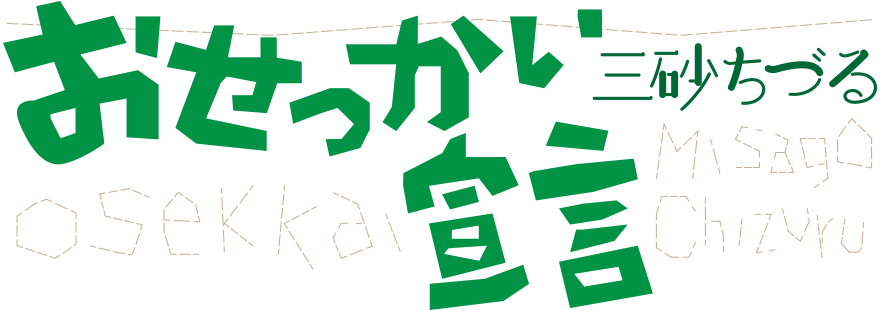

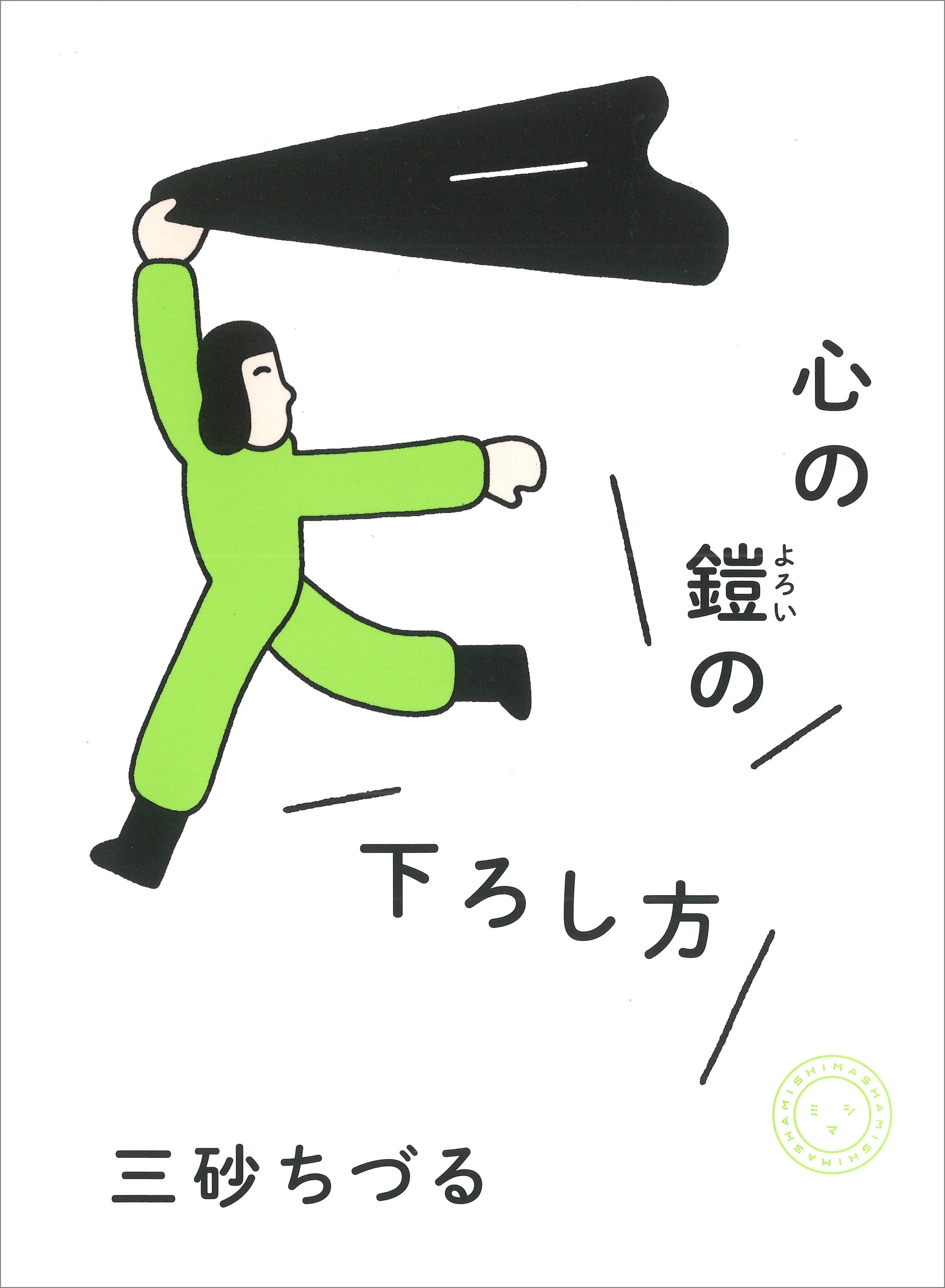
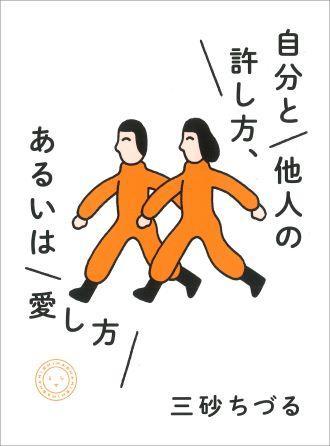




-thumb-800xauto-15803.jpg)
