第131回
ビジョン
2025.07.07更新
なるべく明確にビジョンを描くこと。それが人間の意志の力というものであり、はっきり描いたものは実現していく・・・こう書くといかにも、スピリチュアル系の本の内容のようだが、これは全てのものが実現していく過程のことを述べているに過ぎない。思えば人間がやっていることは全て、こういうものだ。ああいう勉強をしたいと思って、そうだ、こういう学校に行けば学べるのだ、ということがわかって、そこに合わせて勉強し、見事にその学校に合格して、望んだ勉強をする、とか、こういう職業に就きたい、と思って、その職業の学校に入学する、とか、そんなに大きなことでなくても、気のあった友達から連絡があって、どこそこで待ち合わせて一緒にどこかに行こう・・・とか。そういった人間関係とか能力の発揮といったようなこともあるし、実際に何かを作り出す、というプロセスのことでもありえるし、要するになんでもそういうものだ。家を建てる、というのも同じことで、実際にどこに作るのか、どのように作るのか、をまずイメージし、そして土地を入手し、家の設計図を作り、自分で作る、あるいは人に頼む(現在は圧倒的にこちらが多いわけだが)か、して、家を形にしていく。ビジョンと意思の力が全てなのだ、そしてそれを、土地の神様が許してくださっていれば物事はスムーズに進む。おそらく。
私は2024年4月に竹富島西集落に土地を借りて新築の家を建てたのだが、このプロセス自体がビジョンと意思の力の顕現であることを実感することになった。まず、どこからやってきたのかわからない「家を建てよう」(ほぼ、お告げ)という発想を琉球大学八重山芸能研究会の先輩である竹富島出身の亀井保信さんにつぶやいた。彼は私のその意思を軽やかに受け止め、うちの土地があるよ、といって、芸能保存会の後輩である太鼓の名手の設計士根原さんに設計図を書いてもらった。なんといっても町並み保存条例があるので、「どんな家を建てる」かはほぼ決まっているから、伝統家屋の平屋の設計図はあっという間にでき、家のない場所に、もう一つ赤瓦の伝統建築の家ができることはあっという間にイメージができた。
そこから始まって、あ、そうだ、今、畑になっている土地を宅地にするより、裏に、すでに屋敷となっていて家は70年前に移転した土地があるのだから、そっちの方がいいね、と亀井さんは「ピン、ときて」(ほぼ、お告げ)、現在実際に家の建っている前新屋(という屋号の土地)に建てることのビジョンがやってきて、地主さんは喜んで土地を貸してくださった。旧知の沖縄本島の業者さんが施工を担当してくださり、お値段も相場よりはずっと抑えて、ツーバイフォーの台風に強い木造建築を作り、壁は全て漆喰にして、床には竹炭を敷き詰め、ありがたい鏑射寺のお札をしつらえて、本当に文字通り「気持ち」の良い家が出来上がった。裏にある亀井さんの家から見て、ここに家ができる、ということを想像していた通りの、いや、それ以上の立派な赤瓦のシーサーの鎮座まします、伝統家屋が出来上がった。
2024年3月、すでに赤瓦の屋根も家のおおよそも出来上がって、家の風貌がはっきりと竹富西集落に形を表していた頃、20年勤めた大学の研究室を整理していた。ほとんどのものは処分することにして右から左にゴミ袋に入れていたのだが、ふと出てきたものは、とても古い竹富島の絵葉書だった。1980年代半ばに初めて那覇に住んだとき(その時のご縁が今につながって移住したわけだが)に求めたものか、あるいは、1978年に初めて父に連れられて、彼の久高島に水道管を敷いた仕事の終了を祝って家族で沖縄に渡ったときに求めたものか、わからない。しかし、地球の裏まで引っ越したり荷物を移動したりする中で、なぜか残ってきた絵葉書である。おそらく1953年にできた、なごみの塔と呼ばれる、集落が見渡せる小高い公園にある塔の上から撮った集落の街並みである。「竹富島の街並み」と言われるときによく使われるアングルの写真だが、私が持っているのはかなり古い写真である。そこには、2024年に完成し、住むことになる前新屋の屋敷が写っている。
その絵葉書が初めて私のもとにやってきたとき、すでに、ここに家を建てるビジョンは始まっていたのかもしれない。関東圏の大学院で学ぼうとしていたのに、なぜか突然、琉球大学大学院に行くことになり、大学院生だから、学生の部活に顔を出すなんて考えられないのに、西表島でフィールドワークをしていた同僚の院生に引っ張られて、八重山芸能研究会に顔を出すことになった。西表島星立(今は干立)で合宿をし、石垣島を訪れ、そしてそのときにちらっと寄ったのが初めての竹富島だったか。あまり覚えていないのだが、実は。
地球の裏のブラジルまで行っても、イギリスに住んでいても、舞扇と八重山芸能の音源と、ムイチャーにミンサー帯、ティーサージなどはなんと全ての場所に持ち歩いていた。竹富島に移住する前に住んでいた東京の家で、「片付け祭り」をやったので、多くのものを処分し、ムイチャーは手放してしまっていたが、他は全て自分の手元にあり、静かにビジョン形成を助けてくれていた、と思う。
そして今、私は竹富島の家に住んでいる。これは一つの明確な意思とビジョンの成したことである。数知れない人に助けていただき、無理をしていただき、力を添えていただき、出来上がったが、それは何よりも、私という一人の人間の中にあった意思とビジョンから始まっているのだ。だから私はすごい、と言いたいのではない。私だけではない、全ての人間の営みが、すごい、ということだ。思い返してもみよ、私たちは誰かの意思とビジョンが作り上げたものに囲まれて、暮らしているのである。ユングは人類の総合無意識ということを言ったが、今現在生きている私たちの多くが望んでいることが次の世代に向けて実現していく、ということを考えても、一人の人間のみでなく多くの人間がビジョンとして描いたことが総合的に大きな力になって何かを実現していく、ということは、明確である。50年前にはびっくりするようなことが現実世界にその時間を経ると当たり前として生起している。
例えば私たち昭和30年代生まれの人間の母たちの多くは、専業主婦だったが、そのことにハッピーと思っている人よりも思っていなかった人のほうが多かったのであろう。彼女たちの多くは娘たちに必ずしも結婚しなくていい人生や、子どもを持たなくていい人生や、職業を持って一生働いていく人生を望んだ。そのように話し、そのように育てたから、次世代の娘たちはそのように生きるようになり、結婚しないこと、子どもを持たないこと、女性が仕事をすること、は社会的に認められるようになってきて、選択は自由になった。少子化になって大変だ、と騒がれているが、これは前の世代の夢の実現、すなわちビジョンの顕現にすぎない。大体、1970年ごろは世界中で人口爆発についての議論が重ねられ、どうすれば人口を抑制できるかについて提案が出され、日本も例外ではなかった。当時のビジョンが今、なのだから、文句は言えない。少子化社会は、私たちの多くが集団で望んだビジョンだったのである。
こうして書いていると母のビジョンというものの影響力の大きさに改めて気づく。母のビジョン、とは、すなわち、母がどのように考え、どのように望んで子どもを育てていくのか、ということに他ならない。先の世代の母たちの多くは、権威的で、コミュニケーション能力が低く、機嫌も悪く、子育てをしたり家事を手伝ったりすることなど一切しない、自らの父親や夫の態度が気に入らなかった。自分が育てる男の子たちは、優しく、人の話が聞けて、にこにことしていて喜んで家の中のことをやってくれて自分が仕事をすることに賛成してくれる人がいい、と思っていた。そしてそのように育てた。そうやって育ってきたのが今の生殖年齢男性である。皆、優しくて、こぎれいで、コミュニケーション能力が(比較的)高くて、料理も掃除も洗濯もできる。というか、できない人はモテない。母のビジョンの実現である。
だから、スピリチュアル系の人たちの話によく出てくる「自分の描いたビジョン通りになる」というのは、別にとんでもないような話なのではなく、現実というものはそのようにして作られる、という仕組みの話なのである。だから、美しいビジョンが必要である。明確にこのようであってほしい、という方向性が必要である。そしてそれを手放さないこと。
家を建てさせてもらって住まう竹富島の明確なビジョンづくりに加担すること。それ以外に私自身のやることはない。神様の島、伝統芸能の島、竹富島。伝統を大切に、街並みを守りながら、自治を何より尊いものとし、日々を生きている、今となっては奇跡のように存在する小さな島。50万人観光客が押し寄せるこの島の次なるビジョンとは、現在すでに宝物のように大切にされてきたものを次世代に引き継ぎながら、新たなビジョンをひっそりと立ち上げていくことにほかなるまい。この島がほとんどなくしてきて、なくならないほうがよかったことの筆頭が、手仕事である。バーナード・リーチら民藝の一行が1950年代に訪れて感嘆した美しい手仕事、とりわけ多くの女性たちによる織物、いつも機の音の聞こえる竹富島は、今は、遠くなってしまった。竹富島出身で、現在は西表島で紅露工房を率いる世界的染織家、石垣昭子さんも、そのことを残念に思っておられ、もう一度手仕事の島になってほしい、と願っておられる。
女性たちは、本当は、皆、手仕事が好きである。織物も、好きである。長い長い間、女性たちは世界中で衣を整えることを自らの仕事としてきて、単調な繰り返す作業とその出来上がりの喜びを通じて、日々の辛さを慰められてきた。それは私たちの記憶に刻まれていて、糸を作ったり織ったりすることに素朴な喜びを感じる。生産年齢(島では65歳まで、ということになっている)にある女性たちは、竹富島でも、皆、子育てや日々の仕事で忙しくてそんなひまはない。同時に、もともとは織物に憧れて竹富にきた女性たちも少なくない。だから、いまは、ただ、こういう仕事がある、とイメージしていればいい。時折ワークショップなどで経験してくれたらいい。生産年齢を過ぎ65歳になった頃、思い出して、織るようになれば良い。65歳以上が、糸を紡ぎ、いつも織っている。そんなビジョンはどうだろうか。



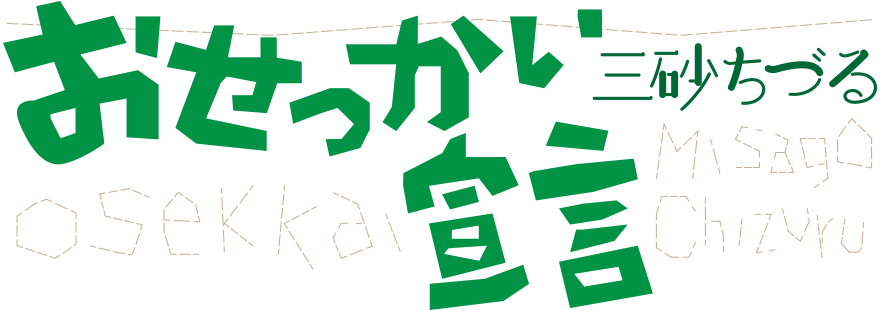

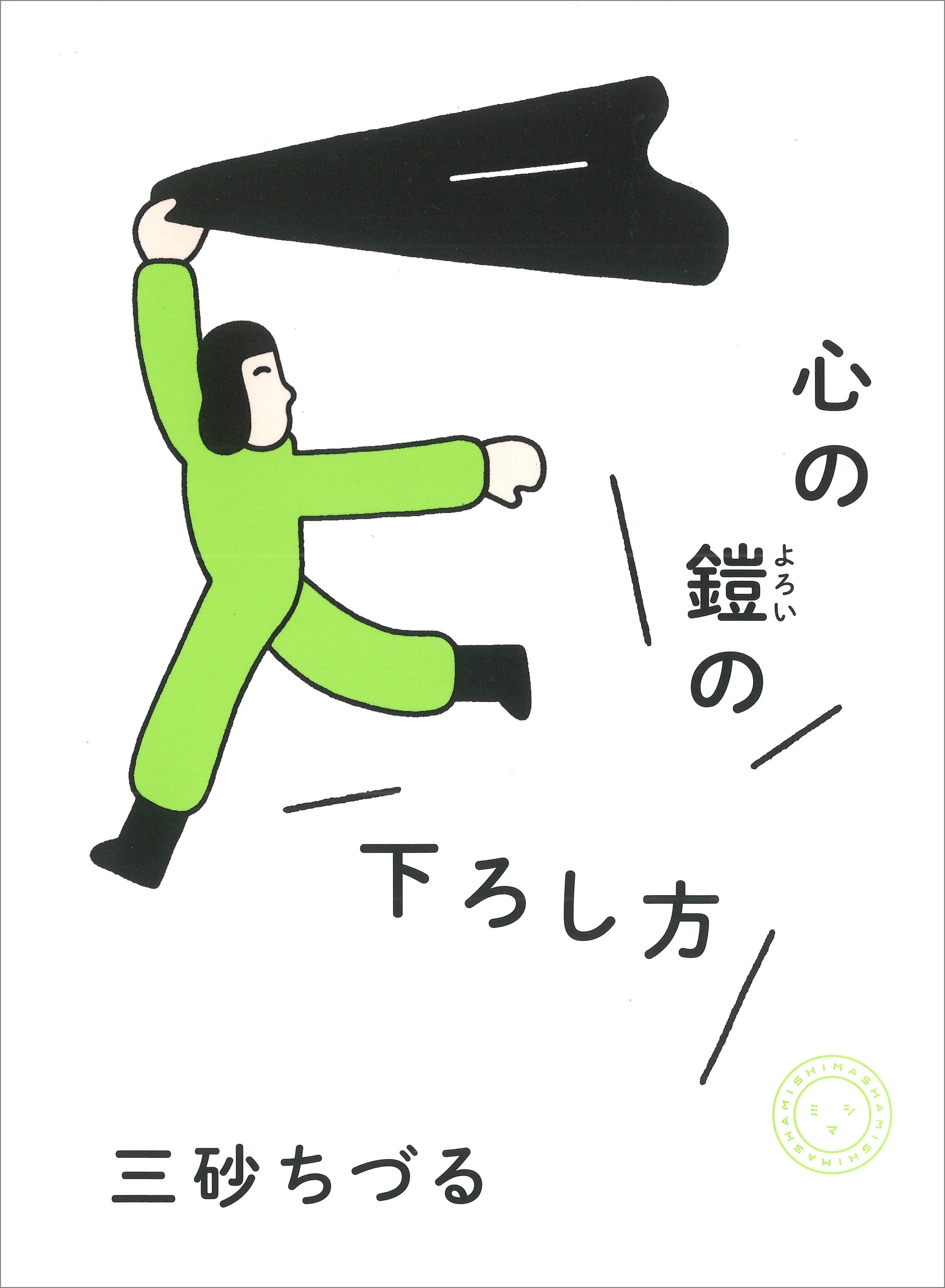
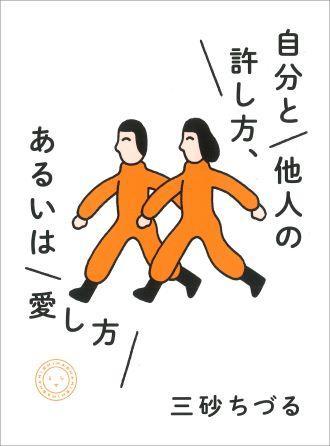




-thumb-800xauto-15803.jpg)
