第135回
ベーシックインカムアゲイン
2025.11.13更新
2017年ごろからか、日本でも話題になったのがベーシック・インカムであった。オランダの若き経済学者、ラトガー・ブレグマンの著書やTEDは話題になっていた。大学で教員をしていたからベーシック・インカムをテストの問題にも出してみたことがある。
「生活保護や、就学援助、などさまざまな福祉プログラムはすべてやめ、就労や資産の有無に関係なく、全ての人に対して最低限の生活を送るのに必要な現金を無条件で定期的に給付する、というアイデアは、ベーシック・インカムと呼ばれています。貧困の問題は、「お金が無いこと」、「現金の欠如」なのだから、お金を配ればよいのではないのか、という考え方です。この考え方についてあなたの意見を述べなさい。」
答えのほとんどは、否定的なものだった。多文化・国際協力学科という学科を2019年から作って、そこに所属していた。多文化共生とか国際協力とかいうキーワードに興味のある若い人たちは、みな、「援助のバラマキは現地の人の自立を損なう」、「自らが働くことを支援するのがいい」、「魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えるのがいい」とかそういうことを高校生の頃からしっかり習ってきているのである。2024年現在、60代半ばである私の世代には、ちょっと隔世の感がある。
昭和33年生まれの私が生まれた頃は、日本はまだ国際援助をもらう側であった。東海道新幹線が世銀の援助で作られたことはよく知られている。戦後の日本はいわゆる今でいう発展途上国の一つであり、60年代、70年代の高度成長期を経て、世界の中で経済力を増し、援助をする側になっていった。とはいえ、そんなことは慣れていない。慣れないのに、帝国主義の世界ではなんとか近代化して海外に出て行って植民地を作らなければ自らも植民地にされてしまう、という危惧を内面化してばりばりと近代化を進めて行った明治政府のリーダーシップと、それに、十二分に個人や地域のレベルで適応して、ちょんまげ切ったり、着物を捨てたり、学校行かせたりしながら、思えば、日本に住まう市井の人々は結構、すぐに、近代日本国家を支えられる「日本国民」になっていったのである。そもそも、おらが村のことしか考えておらず、日本国家など何のことかわからないほとんどの人々を引き連れて、みんな「日本国民」にしたのは大したもので、日露戦争の頃日本に留学していた中国人留学生をして、なぜこの国の人はこんなに国のことを考えているのか、と感心させている。
欧米列強に植民地にされないために尽力した明治政府であるが、その急速な近代化がどのような弊害を我々にもたらしたのかは短期間に隣国に侵攻し信頼を失い敗戦につながっていったことが末代まで語り伝えられることになっていることで、何よりも明らかになっている。経済復興でいくらがんばっても、つい先の世代が起こした戦争と敗戦の顛末によりなんとも言えない罪悪感と後ろめたさを何世代にもわたって引き継ぐことになっていて、そのことの自己肯定感への影響は計り知れない。
キューバやベトナムといった国を訪問した時の、一人一人の明るさ、そしてその明るさが、自らの国への誇りにこそ根ざしていることを知った時のことを忘れることはできない。日本にいるとアメリカ経由の情報しか入ってこないので北朝鮮と並ぶ独裁国家のように言われているのだが、キューバは今もラテンアメリカ全ての国々の誇りである。大国アメリカの目と鼻の先にあって、アメリカに対峙し、一部の人間に集中していた富のシステムをくつがえし、誰もが医療が受けられるように多くの家庭医を養成し、教育を行き渡らせ、文化を大切にしながら全員が食べていけるようにした。現在、非常に困難な状況に陥っているとはいえ、人間にとっての理想を掲げ、それを実践したフィデル・カストロとその仲間たちへの敬意は未だキューバの人々の胸に強く残り、それが誇りとなっている。親しくしているキューバ人医師は、「私たちは他の国に行くから、他の国がどんなに贅沢で豊かな生活をしているか知っている。でも、その裏にはいつも惨めな生活をしている貧しい人、恵まれない人がいる。キューバに帰るとね、みんな貧しいわけだけれど、惨めな人はいない。みんな平等で、物乞いをする子どもなんかいないし、高齢者も幸せ。やっぱりキューバに心からの誇りを感じるの」という。
ベトナムの人にも同じ姿勢を感じた。なんといっても世界で唯一、アメリカ合衆国に勝利した国なのである。中越戦争で中国にも勝っているのだ。ホーチミンも理念を持った優れた指導者で知られていた。一人の優れたリーダーがいると、国民は少なくとも3代くらい幸せに暮らすことができる。
こういうことに接すると、日本がいかに経済的に発展したといっても、私たちの国は抑圧に対して闘った、人間の本来の美しさを失わないようにした、理念を貫いた、そういう誇りは持てないままに100年が過ぎたのだ、ということに気づき、なんともいえない気分になる。
ともあれ1960年代はまだ国際援助を受けていた日本は、時代と共に、援助する側の国になっていった。当初1970年代は多くのインフラに投資し、ハコモノ援助が盛んになり、日本は国際協力の名のもとあちこちに病院や橋などを作っていったものである。私自身がこういう当時でいう第三世界の問題、つまりは発展途上国における開発の問題に興味を持ち始めたのは大学に入ってからだから具体的には1977年以降である。その頃から1980年代初めにかけては、このハコモノ援助は厳しく批判されていた。モノだけを送って企業のみの利益になるのではなく、もっと人と人の交流が行われるべきだ、一対一で人と人が出会うべきだ、顔の見える援助を、エコノミックアニマルとだけ言われないような日本の援助のあり方を考えるべきだ、政府間援助のみに頼るのではなく、非政府組織のレベルでもっと関わるべきだ。先進国から途上国へ一方的に技術援助や何かを教える、という形ではなく、全ての開発プロジェクトは参加型のプロセス、すなわち現地の人たちのニーズを汲み取り、現地の人たちと意見を交換しながら行われていくべきだ、ということが盛んに言われた頃でもあった。世界の参加型手法の根本的な哲学を述べ、開発問題に関わる人に決定的な影響を与えたパウロ・フレイレや、そもそも近代社会における学校や医療や交通というものにラディカルな問いかけをもたらしたイヴァン・イリイチなどがよく読まれた頃でもある。
私たちの生きる今、とは、前の世代の考えたことの顕現である。2000年代から2020年代にかけて国際関係、国際協力系の学生たちと出会ってきたが、この時代にこういうことに関心を持って大学にくる学生たちの多くは高校時代に国際協力等についてかなり深い学びを重ねていることが多く、ハコモノ援助や、バラマキ援助などとんでもない、人間同士の交流と出会こそが大切であり、地元の声が大切にされ、そういうものが汲み取りやすい小さな規模のNGOのような活動が、もっとも良い、と自然に考えているような人たちに成長していた。中には「私は国際協力関係のNGO /NPOに就職を考えています」という人が出てくるようになって、誠に驚いた。国際協力系に限らず日本のNGOというのは、志を持つ人たちの集まりであるから、まともに給料が払えるところなんて本当に少なかった。だから、「就職先」として目指すところではなく、どこかに就職した後で、自分の興味関心を伸ばすもの、として捉えられていたからだ。学生たちは安定していなくても給料が悪くても、本当の意味での国際協力はNGOだ、と思っているのである。
そして彼らは、すでに高校時代に、お金のある側がない側にお金を施す、というタイプの開発援助は最悪である、と学んできている。だから冒頭のベーシック・インカムの問題に関しては、ほとんどが、そのようなことをしては本来の意味での現地の人の自立を妨げると書いてきて、このベーシック・インカム論を興味あるもの、未来があるもの、として捉えているのは二十人ほど答えた人のうち一人だけだった。
この学生たちの態度は、開発援助問題を超えて、私たちの「自立」を考えるときの基本的な考え方になっているのではないか。自立とは、経済的自立のことである。自分で自分の食べていき、生活していくお金が稼げるようになった時に、人は自立したという。開発途上国から、一人の人間の生き方まで、そう考えているのではないか。人にお金をあげると自立を妨げている、もちろん子育ての目標は、その人が経済的に自立することが目標、と。
まあ、その通りではあり、自分で食べていかなければどうにもならないが、お金を稼ぐこと、食い扶持を得てくること、は全員が全員、やらなければいけないことなのだろうか。ブラジルにAlguem tem que trabalhar em casa.という言い方がある。10年ブラジル家族とブラジルで暮らしている間に、よく聞いた。これは要するに「家で、誰かは働かなくちゃね」ということである。つまり「家族の誰かは働いていなければね」「誰かは食い扶持を稼がなくちゃね」であり、この含意するところは「家族の誰かが食い扶持を稼いでいくれればいい」、「みんながみんな働かなくてもいい」ということになるのである。つまり、誰かが働いていれば、働いていない人がいてもいい。アマゾン森林に住む先住民、ヤノマミは、狩りに行ったり畑で何か作ったり、そういうのは好きな人がやればいいということになっていて、ずっと一日ハンモックで寝ていたい人は、そうしたのでもいいらしい。この「家で誰かは働かなくちゃね」は、こういうブラジル先住民由来なのである(かもしれない)。ブラジル人の夫と私、そして息子たち二人がブラジルで暮らしていた頃、夫は医師で大学の教授、私もイギリスの大学で給料をもらいながらブラジルで調査をしている上、日本の国際協力の仕事までしていたから、お金に困っていなかった。だから、失業してお金に困っている夫の弟の仕事を作るために店を作る援助をしたり、姪の予備校費用を出したりしていて、それが普通のことだと思っていた。
自分の稼いだお金は、自分のため、自分の一緒に住んでいる一親等の家族のためだけではなく、もちろん、もっと大きな意味での家族のためのものなのである。当時のブラジル人の夫は五人きょうだいで、それぞれ、子どもは三人以上おり、お手伝いさんが亡くなったのでその子どもが養子になっていたりして(もちろんみんなと同じように育てられていた)、甥姪は山ほどいたし、クリスマスにはみんな家族が集まりそれはそれは賑やかだった。この顔の見えている範囲の人たちはみんな家族、と捉えられているから、誰かが困っていたら、助けるのは当たり前、という気分になるのである。よく、フィリピンとか、アフリカとか、ラテンアメリカの人と結婚したら「家族にたかられる」みたいな言い方をする人が時折いるが、先方からすれば、「家族なのに、なんで、たかられるみたいに言われちゃうの? 信じられない〜」ということになると思う。
つまり大家族の中の、お金のある側がない時のない人を助けるのは当たり前の雰囲気が、日本にいると、よくわからなくなるのだと思う。お互い様、でもあるので、私は、いつか私が失職したり、お金と家を無くしたりすることがあっても、ブラジル人家族の誰かが、拾ってくれて助けてくれる、というか、困ったことがあったら、駆け込んでもいいのだ、という気分になれた。幸い今のところ、そういうことにはならなかったが、いざとなれば、地球の裏に私の居場所があるのだ、と思うことは全然悪い気分じゃなかった。ブラジル人の夫とは別れてしまうが、夫の姉妹たちは「あなたがうちの弟と別れても、あなたはずっと私たちのCunhada(義理の妹のこと)であることは変わらないんだからね」と言ってくれるし、親戚づきあいは、普通に続くのである。別れて日本にやってきても、私の二人の息子たちは、未来永劫、このブラジルの家族の子どもでもあるわけだ。ブラジルでも、まあ、顔も見たくないような別れ方をすることもあるかとは思うが、普通、子どものいる親は別れても、双方の親戚とは関係性が続いていることが多い。夫の家族では、離婚した人も再婚した人も、甥の別れた彼女まで、みんな、家族の集まりにやってくるので、離婚して再婚すると際限なく家族は増えることになる。そして家族が増えるのは、めでたいことなのである。
現在これを書いている私は沖縄県八重山郡に住んでいるのだが、ブラジルの人口の1%は日系人であり、その日系人のうち10%は沖縄出身(ウチナーンチュ)である。ボリビアとかペルーとかアルゼンチンとかは日系移民の七割近くがウチナーンチュであるらしい。1990年からほぼ5年に一度行われている世界のウチナーンチュ大会の盛り上がりは十分に予想できる。沖縄出身の方の多くがラテンアメリカをはじめとする多くの国に移住していることについては貧困問題、政策の問題、等々背景には色々あるとは思う。思いはするが、私の経験したいわゆるラテンアメリカ的なこと、例えばこの大家族の助け合い、などはウチナーンチュのありようとはあまりにも相性が良い。
長々と書いているが何が言いたいのか、というと、「経済的な自立」などというのはその人の人生のフェーズの問題であり、人間としての「自立」というのとは別の問題ではないか、ということが言いたかったからだ。20年間女子大で学生の卒論指導をしたが、その中で、「自立とは何か」ということをまともに取り上げて論文を書いた学生がいた。地方から東京に出て学んでいたが、地元に戻って就職することにした。親の家に住みながら一体自立ってできるのか、と自分で考え始めたことがきっかけで、あちこちに話を聞きに行き、フィールドワークや聞き取りを重ね、最終的に「自立」に「経済的自立」というのは必須のことではない、という結論に達していた。経済的自立が自立した一人の人間になることを助けはするが、それがなければ自立した人間になれない、というわけではない。自立した人間とは、「自分のありようを誰のせいにもしない人のこと」と彼女は結論づけていた。自分の人生は自分のものだ、自分の人生は良くても悪くても自分が背負っていくのだ、自分が自分を幸せにするのだ、と思えるようになることが、人間としての自立、だと。
悲惨な環境に生まれ落ちることもある。とんでもない時代に生まれることもある。大きな環境や時代でなくても、自分の親がいない、片親である、いるけれどもとんでもない親である、とかいろいろな親との関係に苦しむこともある。人間が3歳までにどのように育ったかということは生涯に影響を与えることは「三つ子の魂百まで」とも言われるし、科学的根拠でもってもある程度示されてはいるのだが、影響を与えられてもなお、自分の人生は自分のものだ、環境や時代のせいにはできない、人のせいにはできない、と理解して、悩みながら生きていく。そのことが自立、だというのだ。
そう思えば、冒頭のベーシックインカムには、意味がある。食べていくため、世の中を渡っていく上にどうしても必要なお金は、一律であげるから、そのあとは、自分で考えよう、と言うのである。いっとき、維新の会などが話題にしていたこともあったが、国内では今ひとつ評判は良くない。しかし、再考に値することだといつも考えている。



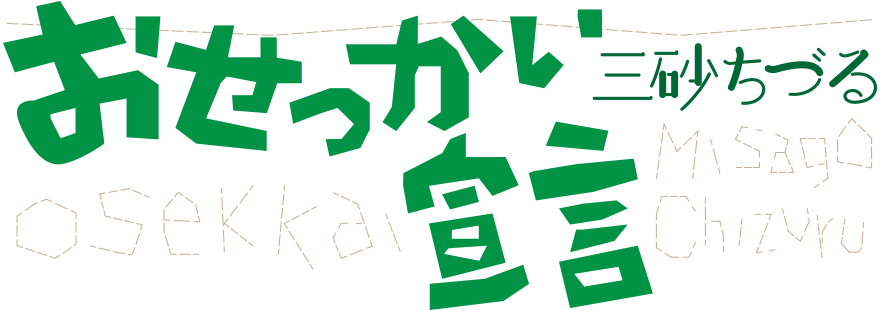

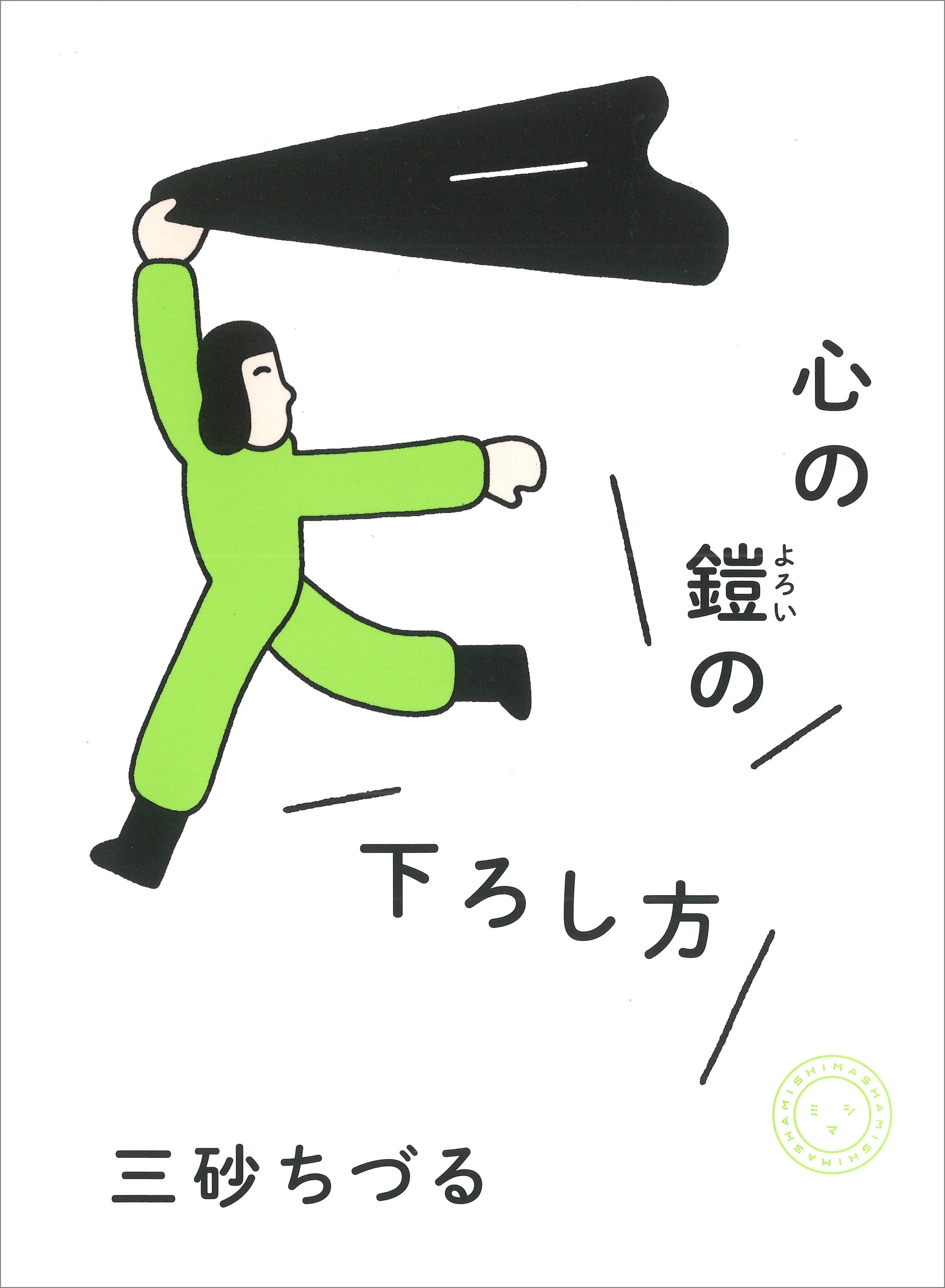
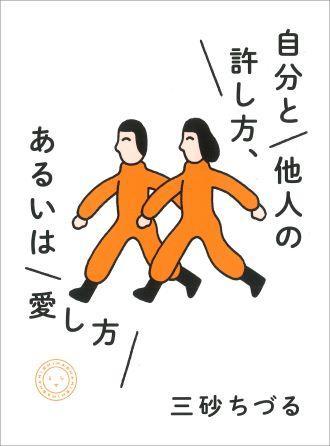


-thumb-800xauto-15803.jpg)


