第133回
ヘマリン
2025.09.15更新
ヘマリン、ってなんだろう、と思っていたらしい。3歳になったばかりの孫、がよく、パパとママにへマリン、という。なんだか嬉しそうに言っているのだけれどなんのことかよくわからない。
3歳児になると言葉は飛躍的に増大して、「話」ができるようになり、本当におもしろい。今までずっとなんでもわかっていて、でも、自分で表現できなかったんだな、と感じる。堰を切ったように言葉があふれてきてあれこれ話すようになるのをみていると人間って本当にすごいな、と思う。
私自身には息子が二人いて、この人たちはいわゆるバイリンガルとして8歳、10歳まで育った。マルチリンガルな子どもが育っていく様子を見るのは初めてだったから、なかなか興味深かった。父親がブラジル人でポルトガル語スピーカーで、子どもたちには生まれた時から、ポルトガル語しか話していなかった。私は生まれた時から日本語しか話していなかった。育った環境はブラジルだったので、家族以外とはずっとポルトガル語を話していた。彼らは自然にポルトガル語と日本語を身につけ、父親やその他の人と話す時はポルトガル語、私の方を向くと日本語で話す、という感じで、私にはポルトガル語で話しかけたりはしない。「この人にこの言葉」と使い分けている感じだった。私は彼らが育ってくる頃にはポルトガル語ができたから、食卓を囲む家族の会話はポルトガル語なのだが、そういう時でも彼らは私に話しかける時は日本語になっていた。次男が生まれたのはロンドンで、長男は八ヶ月から2歳半くらいまでロンドンに住んでいたので、当時、周りの言葉は英語だったから、あと一年くらいロンドンにいたら、おそらく長男は英語も普通に話したことだろう。この時期にはいくらでも言語を覚えるという感じだった。
この人にはこの言語、あるいは、話しかけられた言語で答える、という感じだから、彼らは二つの言語を混ぜることは決してなかった。つまり彼らのポルトガル語会話に日本語が混じることはないし、また、私との日本語で話す時にも、ポルトガル語は決して混じらなかった。運用システムが違う、という印象を受けた。だから、「翻訳」のようなことは幼い子どもにはできなかった。ブラジルの友人たちは、うちの子どもたちが日本語も話すことを知っているからポルトガル語の単語で「これは日本語でなんというの?」と聞いても彼らは答えられなかった。答えられるようになったのは5歳を過ぎるくらいだったのではないかと思う。運用システムが違うから、ポルトガル語で聞かれている限り、ポルトガル語システムしか運用されていないようだった。
長男の息子は、東京都心に住んで、終日英語を使う英語のナースリーに通っている。無認可保育所の一つであり、現在都心にはこういうタイプの保育所が結構あるらしい。彼らの住んでいる区では、かなり柔軟にどのようなタイプの施設にも補助が出るようで、現在、英語だけで乳幼児が過ごすような環境は思ったより増えているらしい。孫の通うナースリーは小規模で人数も少なくとても家庭的なところで、アメリカ人とかフィリピン人とか英語を生活言語とする先生たちが子どもたちに自然に接している。歌も英語、ゲームも英語、だから、まあ昼間は英語漬け、ということになり、孫は英語がわかるようになっている。こういう時代なのだな、と思う。
家で誰も英語を話していなくても、英語のYou tubeは観るし、歌も歌っているし、母親に、英語でなんていうのと言っても、答えられたりしているから、この人は、バイリンガルとして意識せずに二言語体系を身につけたというより、英語を習い覚えているんだな、ということがよくわかる感じで、日本語にも時折英語の単語を混ぜて話したりしている。こういうことはバイリンガルとして息子たちが育っていた時には全くなかったことだから、孫は、確かに、「外で習い覚える言語」としての英語を幼い頃から習っている、ということなのだと思う。耳で聞いて覚えているから、発音などはほぼネイティブであることは、バイリンガルキッズと変わらない。
長男は仕事で毎日英語を使わなければならない環境にあり、長男の妻も子どもが生まれる前はエアラインのCAだったので、日本人の平均からすれば英語は話せる方である。しかし両方、バイリンガルではない。習い覚えた英語である。それは私も同じで、英語でコミュニケーションは取れるし仕事もしてきたし仕事のうち10年くらいはイギリス大学勤めだったから、それなりにはできるけど、いわゆるバイリンガルが話すようには話せない。世界中の人の英語を聞いてきたし、開発途上国と呼ばれる国に出て行って仕事をすることが多かったから、英語は別にイギリス人とかアメリカ人とかが話すように話す必要はなく、要するにコミュニケーション言語として通じればいい、世界の人たちはそうやって第二、第三言語としての英語を使っているのだ、と感じていたから(開き直ってしまって)ジャパニーズ・イングリッシュで何が悪い、通じたらいいだろう、読み書きできればいいだろう、程度で過ごしてきたので、その程度の英語力である。逆に言えばその程度の英語力で、イギリスの大学でも生き延び、国際保健関連の仕事をやって世界中の人、政府レベルの人とある程度渡り合うことも不可能ではなかった、というべきか。
で息子夫婦も私も、時折、この英語ナースリーに行っている孫が混ぜてくる英語の単語がよくわからなかったりするのである。
息子たち夫婦は、時折、息子が「へまりん」「へまりん」というのがよくわからなくて一体何のことだろうと思っていたらしい。先日息子と話していたら、「へまりん」がわかったよ、という。何のことかと思ったら「へまりん」は「へマリン」であり、「へマリン」はファミリー、すなわちfamily、家族、のことなのであった。
どんな時にへまりんを使っていたのかというと、パパとママと一緒に行って「ウィーアーへまりん!」と言ったり、パパとママをぎゅーっとしながら、「へまりん、へまりん」と言っていたらしい。パパとママとしては何だかよくわからずににこにこしていたらしいのだが、ある時突然、へまりんがファミリーであることに気づいて、わー、ごめん、気がついてなくてごめん、と謝ったらしい。
孫としては、パパやママや生まれた妹と一緒にいるのがうれしくてうれしくて、「家族っていいね〜っ!」と言っていたわけである。なんとかわいい。そして、3歳児にそんなことを言わせることができるように育てているパパとママは本当にえらい。パパとママと一緒にいることが何より嬉しくて、みんな一緒にいると、感極まって、へまりん、って言っちゃうくらい嬉しくて・・・なんて、素敵なことなんだろう。少なくとも自分が子どもの時にそんな気持ちになったり、そんなことをした覚えはない。そんなことやっていい、と思うように育たなかったし、わたしもかわいげのない子どもで、そんな素直なことは言わなかったはずである。
気づいてみると、なるほど、である。ネイティブ発音のfamilyは、確かに、へマリン、と聞こえる。というか、おそらく、アメリカとか行ったら、ファミリーって発音するよりへマリン、の方が通じるに違いない。耳で聞いたように話せる、というのはやっぱり幼児ならでは、だな、と思う。
先日のニュースで、こう言った英語ナースリーが増えているので、小学校でも英語で授業を行うようなところも増えつつある、ということであった。日本語教育をしっかりやって、日本語の本をしっかり読ませる上に、そういったことを重ねるのなら、それもありなのだろう、おそらく。



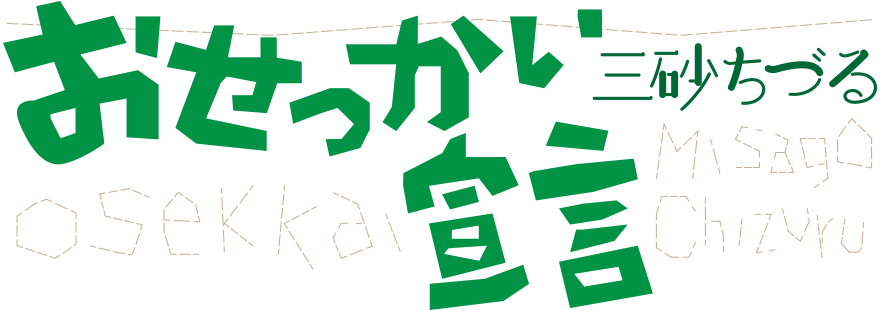

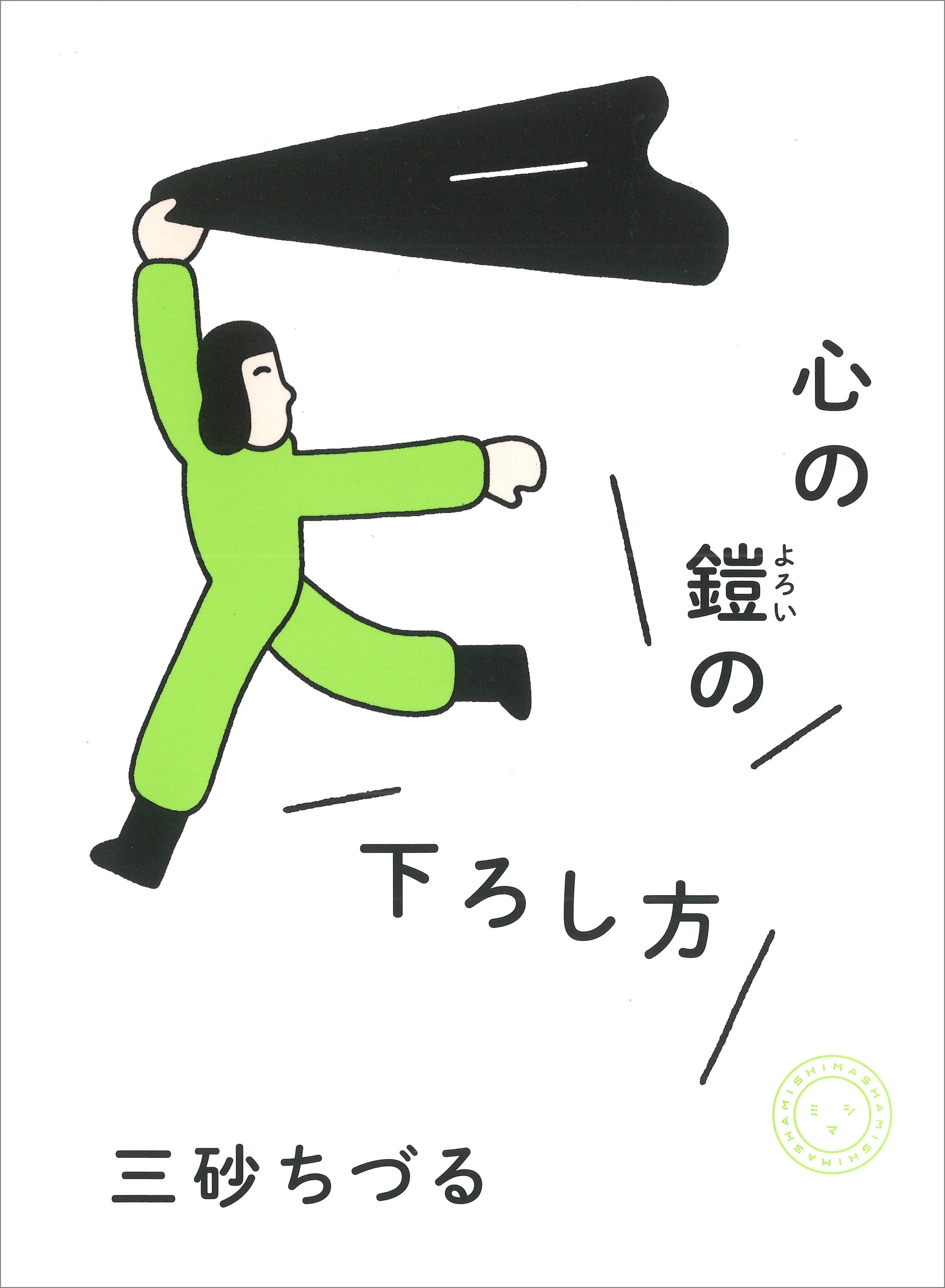
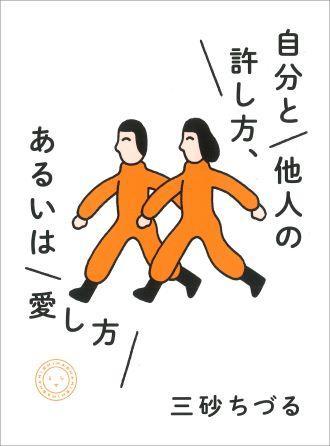


-thumb-800xauto-15803.jpg)


