第134回
生きるよろこび
2025.10.14更新
2025年上半期のNHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」をみながら、改めて、アンパンマンのすごさと、やなせたかしという人の人生を振り返ることになった。そういう人は私だけではない、ということがこのドラマの人気に現れていた。1988年にアニメ放映の始まったアンパンマンは、1958年生まれの私の子ども時代にはもちろんなかったのだが、最初の子どもが生まれたのが1990年なので、まさにアンパンマンと共に育った世代である。わたしの二人の子どもたちはブラジルやイギリスで生まれブラジルで10歳8歳まで育ったので、日本のテレビの様子はよくわからないのだが、当時はVHS全盛期でもあり、父が日本のアニメや子ども番組をまめに録画して送ってくれた。日本昔ばなしもあったが、その他の番組もあり、アンパンマンもあった。当時すごい人気だったのだ。それからも一貫して子どものいるところにはアンパンマン・・・という30年が過ぎ、2022年に生まれた初めての孫の男の子もアンパンマンなしでは夜も日も明けない。
2025年6月、3歳になったばかりの彼に妹が生まれるので、加勢に行った。保育所から帰る彼を迎えにいくのだが、保育所の向かいにコンビニがある。「今日はピカピカにしたからアンパンマン!」という。なんのことか最初はわからなかったが、ピカピカにした、というのは、お昼のお弁当を何も残さず全部食べた!ということであり、食の細い彼は、お弁当を完食したら、保育園の帰りに何かごほうびをもらえる、ということになっていたようで、お弁当を完食したその日は、コンビニでアンパンマンのチョコレートを買いたい、ということだったらしい。こちら、おばあちゃんなので、孫には、ただ、甘い。はいはい、と言って、コンビニについて行って、どこにあるの、というと、まっすぐアンパンマンチョコの売っている売り場にいく。売り場に着くと、さすが、アンパンマンチョコは3歳の子どものちょうど手の届く一番下の棚に配置してあり、アンパンマン、バイキンマン、メロンパンナちゃん、あかちゃんマン(こういうキャラクターを大人もすらすらと言えるということ自体がすごいが)らの顔を配したチョコレートが売っている。
キャラクターの顔を、どん、と配したペロペロチョコレートを頭からガブっと食べる、というのは、他のアニメなどのキャラクターでは、ちょっと、どうなの、と思うけど、アンパンマンは、なんせ、アンパンおよび他のパンや食べ物なのであるから(バイキンマン、違うけど)、さらにアンパンマンというのはお腹が空いた人に、はい、と自分の顔を差し出して食べさせるスーパーヒーローなのだから、顔を食べるのは、本来の意味で正しいのだ。おお、なんと、食品向けのキャラクターであろう。いや、食品そのものなのだから、当たり前か。改めて、これはすごい。で、孫は、今日はアンパンマン、と言った後で、ぼく、3歳になったから、三つ買うね、バイキンマンと、あかちゃんマン、と三つ、という。いやいやいや、きみ、三歳になったからチョコも三つ買っていいわけではない、今日はアンパンマン一つだ、とそれなりに交渉に応じ、納得してもらって、アンパンマンチョコ一つを買った。
次回、保育所に迎えに行った時も、ばあばは、買ってくれることがわかっているから、今日はピカピカ、アンパンマン、と言って、また、コンビニに行くことになる。すると今回は、今日は、パパとママの分も買うので、アンパンマン、バイキンマン、メロンパンナちゃんの三つを買う、という。むむ、今日は年齢ではなく、家族構成できたか。パパはバイキンマンが好きじゃないかもしれない、ママはメロンパンナちゃんよりあかちゃんマンがいいかもしれない、本人たちに選ばせるべきではないか、今日は君の欲しいものだけを買おう、と言ったら、彼はあかちゃんマン一つを選んだのであった。数が数えられるようになって、年齢やら家族構成を持ち出せるようになっている孫は、たいしたものだ、と感心して、あかちゃんマンチョコを食べていただく、甘々の、ばあばなのである。
この「ばあば」というのがいつから出てきたのか知らないが、わたしが子どもたちを育てている頃は、なかった。調べてみると、2004年のNHKドラマ"ジイジ〜孫といた夏"という作品あたりから普及した、2007年には国語辞典にも掲載されるようになった、と書いてある。なるほど、わたしの生活感覚にも近い。呼びやすいし、呼ばれる方もじいちゃん、ばあちゃん、より、良い、と思ったのかどうか、あっという間に普及した。わたしは「ばあば」なのであるが、わたしより10歳ほど若い嫁の母は、「ばあびい」と呼ばれている。おお、バービー・・・。なるほど。孫と長男家族はかように嫁の母を「バービー」、わたしを「ばあば」と呼んで差別化しているのである。わかりやすくて、良い。
嫁がとにかくお産なので、買い物、家事なども約一月加勢したのだが、買い物リストにも「アンパンマンのパン」というのがあって、アンパンマンのパン、って、アンパンはパンだろうが、とかいうそういう話では、もちろんない。アンパンマンをキャラクターに使った一口スティックパンのようなものが販売されており、野菜味とかいちご味とかいろいろあり、パンの売り場に「アンパンマンパン」のコーナーがあり、そこもまた、子どもの目線に合うように、かなり低いところに置いてある。そしてそこで野菜味のパンを買ってきて欲しい、というのが要望なのだが、いつ行ってもここのパンはかなり在庫が少なめで、野菜味は特に売り切れていたりする。つまりは、すごく売れているのである。
業界でも3歳まではアンパンマン、という言葉もあるようで日本の乳幼児はアンパンマンと共に育ってくる。アンパンマンは本当に丸を重ねていくと描けるようなとてもシンプルな創画なので、お父さんもお母さんも保育士さんもばあばも誰でもすぐにアンパンマンを描けるし、描くと子どもは喜ぶのである。子どものいくような施設、つまりは保育所とか小児科の病院とかそういうところには、手描きのアンパンマンの絵が壁とかロッカーとかに散見されるが、そしてアンパンマンはライセンスフリーなキャラクターではないから、おそらくこれは、著作権に抵触する可能性があるのでは・・・と思うが、これ自体が営利目的に使われているわけではないから、なんとなく、容認されてきたのであろう。子ども達はいつもアンパンマンを見たいし、それはとてもシンプルに真似できてしまう。わたしの息子たちの世代、1990年代以降、日本のおおよそすべての子どもはアンパンマンと共に育ってきたことになり、その絶大な人気は今もゆるぎない。今の1−3歳児の心をがっちりとらえていることは孫を見ていてもよくわかるのである。
アンパンマンのテーマソングである「アンパンマンのマーチ」はほぼ誰でも知っている童謡と同じレベルで知られていて、これは1990年代生まれ以降の子どもだけではなくその子どもと共に生きてきたはずである我々の脳裏にもしっかりと刻み込まれていて、音楽が流れれば、アンパンマンである、とわかるはずだ。聞いたことがないのではないか、と思っても、聞けば、必ず知っている。今回、あらためてこの曲を最初から最後まで聴いてみたが、冒頭からやなせたかしの詞がすごい。
そうだ うれしいんだ 生きるよろこび
たとえ胸の傷が痛んでも
で始まるアンパンマンの歌は、全く幼児向けに寄せていない、というか、どの世代が聞いてもずん、と心に響く、というか、むしろ、大人が聴くとびっくりするような歌詞なのだった。わたし自身がびっくりしている。大人になればなるほど、どれほど、今日の日を喜びと共に生きることがそんなに容易くないか、ということがわかる。胸の傷も深くなる。にこにこしているだけでは生きていけない。それでもなお、君はいくんだ、ほほえんで、と、アンパンマンマーチはうたうのである。さすがにテレビのアンパンマンの番組ではこの、「そうだ、うれしいんだ、生きるよろこび」で始まる一番は、子どもには難解である、ということで二番の歌詞、「そうだ、おそれないで みんなのために 愛と勇気だけがともだちさ」で始まっている。一番を知ってみると、ちょっと不満が残るような気がするし、おそらく作詞者のやなせたかしさんもそう思ったんじゃないかと思うが、でももちろん二番も十分に素晴らしいし、ヒーローものらしい歌詞だから、それでいいのだろう。ただ、一番を改めて聴いたわたしは本当に衝撃を受けた。これを聴きながら日本の乳幼児が育つ、という事実に。
どんな音楽を聴いていたか、どんな歌詞を聴いていたか、というのはその人のその後の人生に大きな影響を与える、というか、大人になるとそのことに影響されていたことに気づく。1990年代以降、日本に育つほぼすべての乳幼児がアンパンマンと共に育ってきたことを考える。「そうだ、うれしいんだ、生きるよろこび」という歌詞を聞いて育ってきたことを考える。
時は早くすぎる、光る星は消える、だから君はいくんだ、ほほえんで・・・
こんな深遠な歌詞を口ずさみながら、日本の幼児たちは育ってきたんだ。時は過ぎゆくし、星の光も消えていく、過ぎゆくし、消えていく、けれども、君はいくんだ、じゃないんだ。過ぎゆくし、消える、だから、君はいくんだ。なんてすごいんだろう。過ぎてゆき、消えていくことがわかっている、だから、いく。詩人であったやなせたかしの真骨頂が、この一つの「だから」という接続詞に凝縮されているように思う。
男の子たちは草食系と呼ばれるようになり、男、男、と言わずに、優しくて、思いやりがあって、生活のこともまめにできる男性として育ってきて、今はそういう男性でないと結婚もできない。これはそのような息子たちに育てたいと思ってきた母親の成果であるとわたしは考えていたが、同時に、アンパンマンと共に育ってきたからではないのか。優しくて、自らを差し出して、ほほ笑んで、今日も行くアンパンマンが幼い頃のヒーローならば、男の子たちが優しい人に育つのは、自然なことだ。そうだ、うれしいんだ、生きるよろこび、と、心に携える男の子たちが。



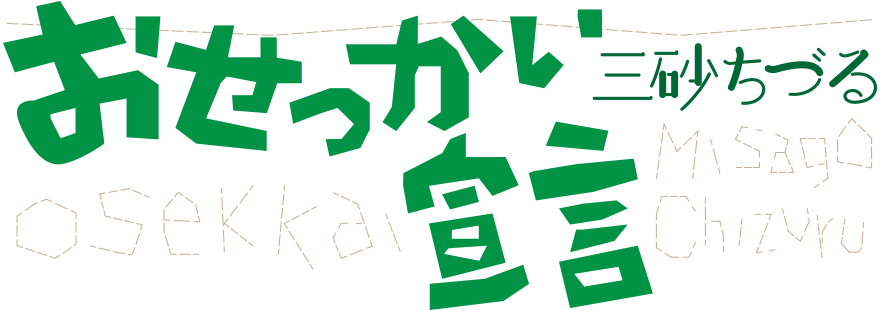

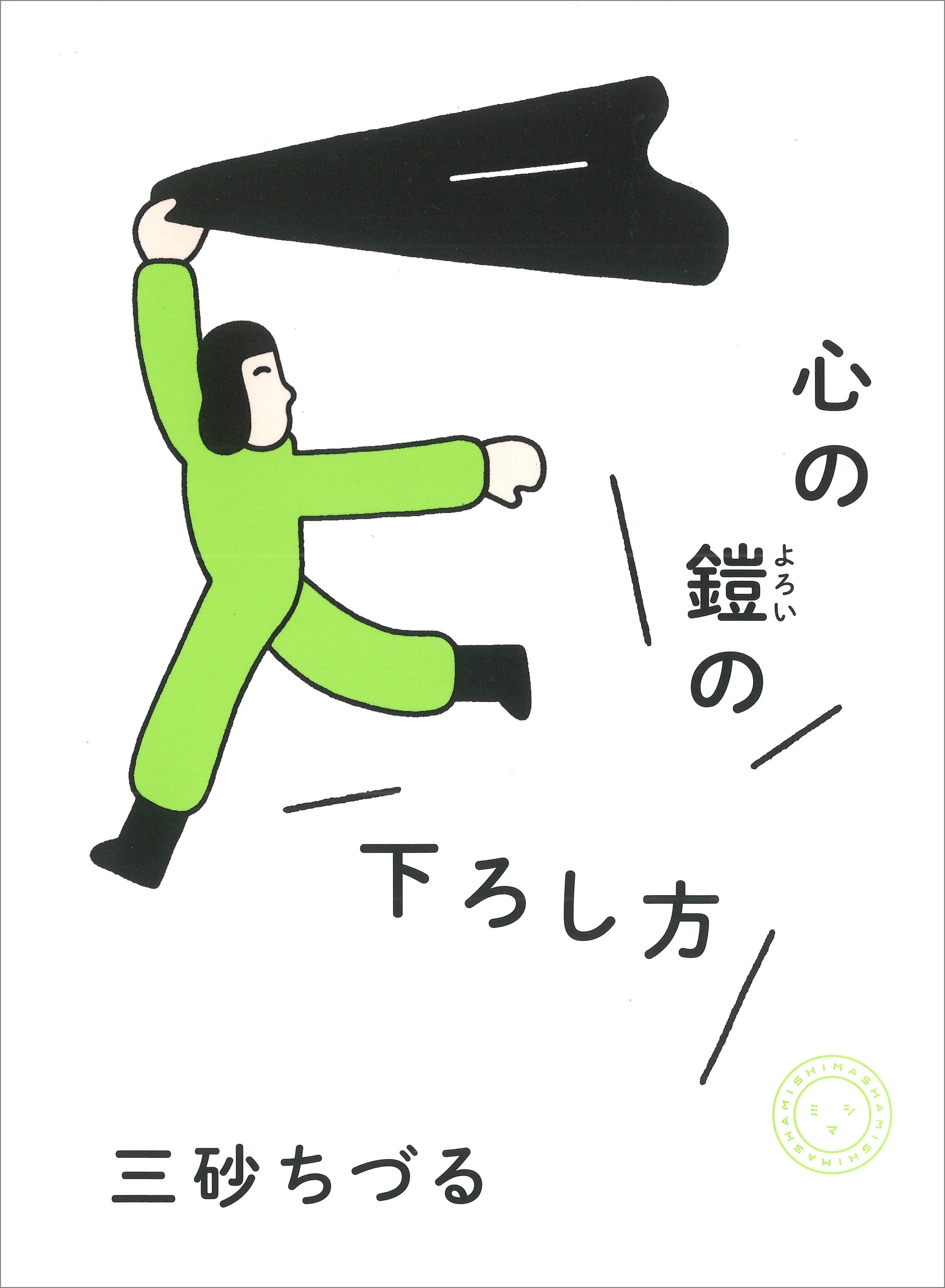
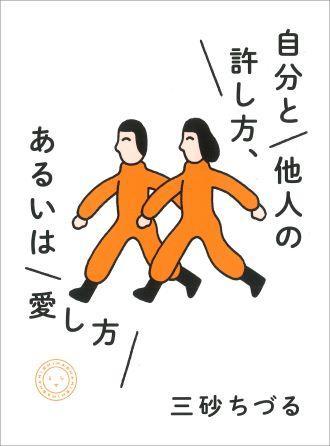




-thumb-800xauto-15803.jpg)
