第132回
ポストのある風景
2025.08.15更新
2025年7月、デンマークがとうとう赤い郵便ポストのサービスをやめる、というニュースが出ていた。そういった集配は民間委託するのだそうだ。郵便ポストの利用は減り続けていて、今後も増える可能性はない。そうだろうな。世の中が変わって、いろいろな職種やものがなくなっていったのだから。川の渡しから、駅の切符切りから、キオスクのおばちゃんの暗算計算まで。なくなっていく一つ一つには、人間的な関わりの手ざわりが残っていた。人間世界の発達は、人間がやっていたことを機械がやること、に、よっている。もちろん洗濯機や冷蔵庫や自動車やエアコンがこの世に発明されたことで、どれほどの恩恵を受けているかしれない。そもそもそれらの動きを担保する電気の存在からして。現在、八重山の離島に住んでいるが、ここに電気や水道や便利な家電が入ってから、まだ、50年前後しか経っていないわけだから、現在70代くらいの人は、まだこれらの恩恵が全くなかった時代のことをはっきり覚えておられるのでそんな昔の話ではない。買い物できる店もない離島に移住して、さほどの不便もなく、幸せだ、と能天気に暮らしていられるのは、時折停電するとはいえ、電気がしっかりしていて、石垣島から海底管を通じて水道水が送水されていて、冷蔵庫にしっかり食料が貯蔵できて、エアコン効いた部屋で快適に暮らせて、アマゾンプライムが無料で届き、Wi-Fiも完備されているからである。ああ、書き並べてみても、私の安寧はどれほどにこの世の発達に支えられていることか。
それでもなお。なくなっていく一つずつに存在していた人間の関わりは、それを絶ってしまってよかったのか、と思わざるを得ないし、そこに働いていた人の精魂込めて自分の力を手向けたことへの敬意を考えると、やはり寂しい。ノスタルジックと言われても、それらを忘れることはできない。
橋ができたら船はいらなくなる。川の渡し、は、川に隔てられることの多い山の国日本では、本当によくみられるものだった。船を漕ぐ人、同乗する人、見送る人、迎える人。私自身は渡しを生活で使った経験はないが、現在住んでいる竹富島から石垣島までほんの15分弱乗る船を頻繁に使っているので、十分に想像がつく。港に出て、船に乗って、石垣に着くまでに、誰とも話さない、ということはあり得ない。港に行けば、島の誰かしら、と会う。切符を買いに行けば売っているお姉さん、お兄さんたちはよく知る人たちだし、桟橋で待っている人ともあれこれ話すし、船の会社の仕事をしている人とも、自然に顔見知りになる。船に乗って出て行くだけで、多くのコミュニケーションが存在する。
沖縄の離島に橋をかけよう、という動きはかなりの勢いで存在して、宮古島近辺では、伊良部島、池間島、来間島に橋がかかっている。石垣―竹富間はそれらの島よりは遠いのであるが、技術的には不可能ではないわけだから、橋をかけようという話が浮上したこともあったらしい。もちろん橋をかければ便利で二十四時間移動が可能になる。
そんなことしなくていい、と、多くの島の人が思ったようである。島の静かで安全な生活は、海で隔てられていて、船が介在しているから保たれていることをよくわかっているからだろう。年間50万観光客の来る島であるが島で夜を過ごす人は多くない。ほとんどの人は石垣島からの日帰り観光である。船の最終便は午後5時50分で、その船が出た後は、島は、しん、と静かになり、その静けさは翌朝9時ごろまでずっと続いている。島ではキャンプは禁止で、島の人の顔の見えている民宿かホテルに泊まる以外ないから、どういう人が泊まっているかは島の人に把握されている。島には交番もないのでお巡りさんもいない。いたこともあるらしいが、あまりにヒマで、いること自体で風紀が乱れる、とかで、追い出されたのだとか、なんとか・・・で、お巡りさんがいた頃のことは寓話化されているくらい、昔である。とにかく警察はいないので、島の青壮年たちによる消防団が活躍している。誰かがキャンプしていたりするのが見つかると、消防団によって、退去を命じられ、船がありません、と言っても消防団員関係者の船で石垣島まで返されてしまうらしい。
橋がかかったら、そんなことではすまない。島の安全は一気に乱されることをみんなよくわかっているのだろう。鍵もかける必要がなく、暗いところを歩いても(本当に暗いので懐中電灯なしに歩けない)不安がない生活には不便の代償があっても構わない、と合意できているのだ。そもそも竹富島はまちなみ保存されている地区であり、古い沖縄集落の雰囲気がそのまま残っているからこそ、観光客も訪れる。それを守るための合意の作り方と島民の覚悟は筋金入り、ということであろう。それにしてもやはり、発展や開発を押し留めるのはいかにも難しい。
川の渡しや切符切りやキオスクの話をしていたのだ。駅の自動改札機は1960年代に関西で使われ始めたというが、一気に普及したのは、民営化後のJR東日本が1987年に導入してからという。ちょっとした失敗をしたりすると、がちゃん、と目の前のゲートが閉まることを誰もが経験したことがあると思うが、東京みたいに人が多いところだと、ゲートが止まると、後ろの人に舌打ちされたりする、あれは、やっぱりあまり気分の良いものではない。あの自動ゲートが登場する前には、切符にはさみを入れる切符切り、という人がいた。切符を次々に切っていく作業は滑らかで美しく、切符切りはさみをくるくると回す様はかっこよかった。ぱちぱちぱちぱち、という音も聞こえていて、それは忙しい都会の朝の風景でもあった。
駅のキオスクにいる女性(キオスクのおばちゃんと呼ばれていた)たちの暗算と商品引渡しとお釣りを手渡す速さは、職人技だった。朝の忙しい時間帯、一本でも早い列車に乗りたいと焦っている客に、一瞬でお金を預かり、必要なものを渡し、間違いないお釣りを手の上に置くことができた。キオスクはJR民営化前は鉄道弘済会が運営していて、国鉄勤めの夫を亡くした未亡人たちが働く場、とも言われていたが、JRも株式会社となり、バーコードで電子マネーで決済するようになって、この職人技が必要とされなくなったのは2025年現在からちょうど10年くらい前ではなかったか、と記憶している。
どちらも便利になって、そこにいる人間の存在は以前ほど必要ではなくなっていき、そういう職人芸は消えていき、誰でもできる仕事になってゆく。人間というのは、仕事を任されると、そこにそれなりの職人芸が生まれ、独特のコミュニケーションが生まれる。そこに伴う体の使い方とか、頭の使い方が、確実に、その仕事に関わる人の人格の涵養と仕事の矜持につながっていたと思われる。自らの仕事というのは、誰かに継いでもらいたいと思うのと同様、自らがかけがえのない一人でありたい、という思いとのせめぎ合いのうちにその洗練が成り立っている。仕事に貴賎はなく、どのような仕事にもその洗練が求められることについて、この国では結構意識的だった、と、海外の様子を見た後に思ったものだ。
今のようなSNSも電子メールもさらには電話やファックスもなかった頃から、郵便制度は機能していた。明治維新直後の明治4年には日本の郵便制度は始まっているし、世界の郵便も程なく整備され、世界中に郵便を送れて、世界中から郵便を受け取れるようになった。1984年、青年海外協力隊という、今となっては特に必要もなかろうと思う、元々は政府肝入りのボランティア組織に参加したことがある。当時は35歳以下の様々な技能を持つ若者たちが集まり、3か月の宿泊研修後、世界中の発展途上国に送られていった。3か月は若者たちが親しくなるには十分な時間で、インターネットはまだ存在せず、国際電話はとんでもなく高額だった時代だから、お互いのコミュニケーションは郵便に頼るしかなく、親しくなった我々は手紙を書いてお互いと連絡を取り合っていた。
南部アフリカの首都ルサカで働いている私に、ネパールの山奥で仕事をしている友人から手紙が届く。この手紙はどれほどの人の手を経て、あなたの元に届くのか、と書いてある。ネパールのポストに入れられた手紙は、山の集配人によって集められ、カバンに入れられ、袋に入れられ、首都に運ばれる。そこから、また行き先を分ける人たちの手によって、仕分けされ、想像できないようなルートを辿って、アフリカに着く。ネパールから南部アフリカの国まで、どういうルートだったんだろう。おそらくは1980年代だから書状はすでに船ではなく飛行機で、運ばれたのだろう。ネパールからイギリスに向かったのか。イギリスを経由して、南部アフリカの国まで届くのか。ルサカの空港から、また、多くの人の仕分けの苦労を経て、配達人が私の住む家のポストに届ける。それは奇跡のようなプロセスだ、と書いてあった。外国郵便の料金は決して安くはなかったが、それでも誰でもが、がんばれば投函できる程度の値段であり、その切手を貼ることで、私たちが自分の家で書いた書状は、家の近くのポストから、世界のピンポイントな人の郵便受けに向けて、間違いのない旅をしていったのである。
郵便制度とは、かくも多くの人の手のかかった、綿密に張り巡らされた制度であり、私たちはその制度のおかげで、自らの世界を広げ、自らのなつかしい人を愛おしみ、世界の広さも知ったのだ。筆記具を手に取り、便箋を広げ、思いをしたためる、ということが、SNSによる一瞬の指先の文章作成にとって変わった今、赤い郵便ポストが必要でなくなることは、致し方ない時代の流れ、である。世界中のどんなところにも置かれていた郵便ポストが消えていくのも時間の問題だが、実際に、国レベルで郵便ポストサービスをやめます、と言われると、世界への扉は開かれているようで本当は閉ざされていくような、なんとも言えない思いが広がっていくのを押し留めようもない。郵便ポストのある風景を、まだ思い出にしたくないのだ。



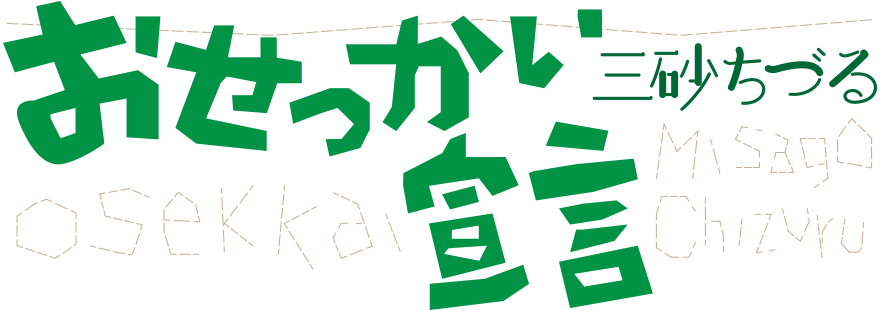

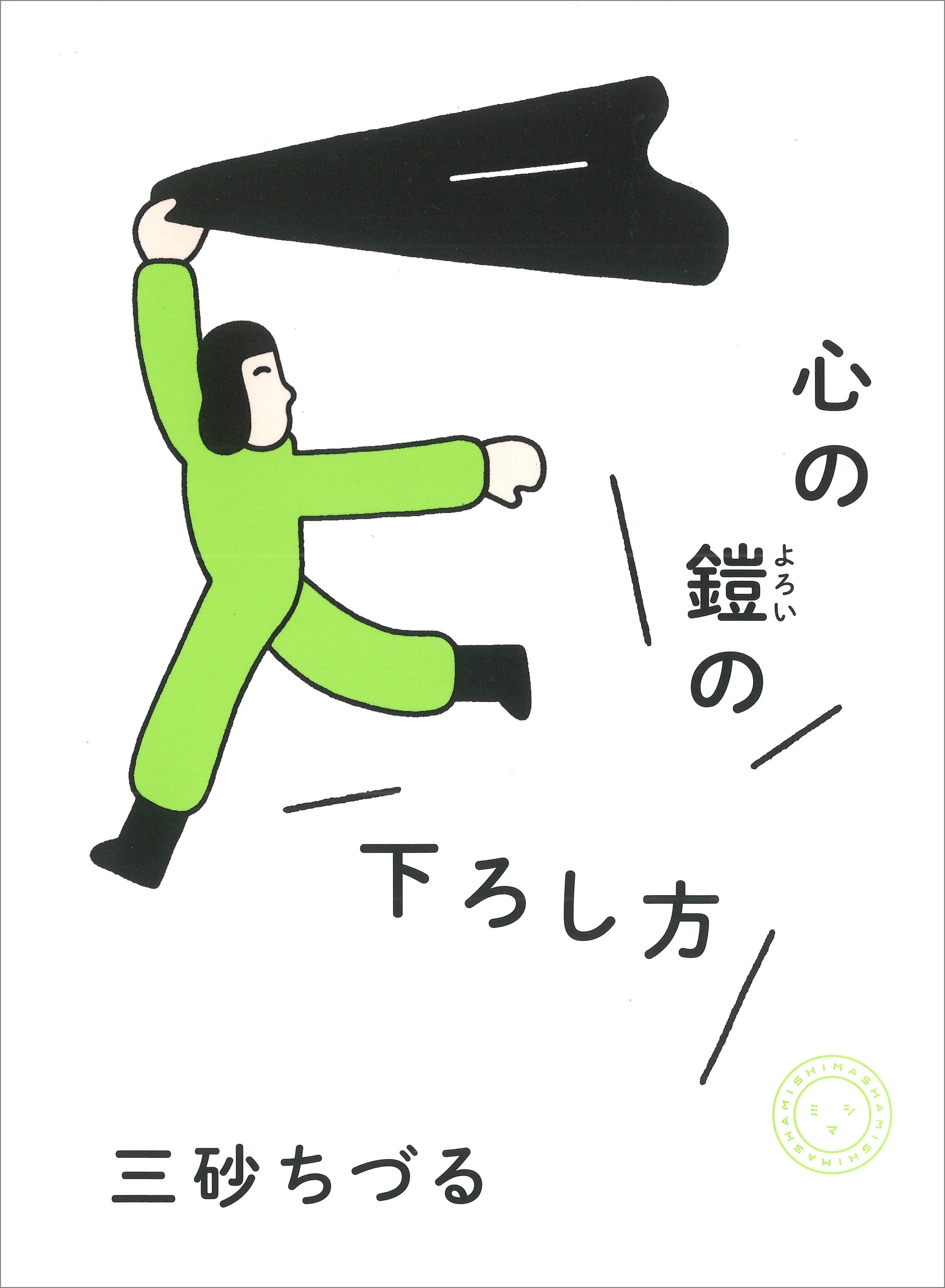
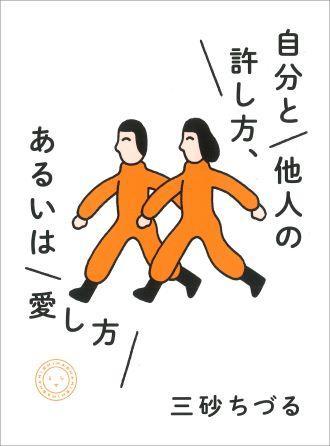




-thumb-800xauto-15803.jpg)
