第2回
いちじくいちのこと 01
2019.01.18更新
自著『魔法をかける編集』は、読書体験の少ない人でも読み通せそうな紙面構成(文字の大きさや余白)と質量(ページ数、厚み)を考えてもらって書きすすめた。しかし、限られたページ数のなかで、この本の主旨である「広義な編集」について理解してもらおうと思うほど、かえってその基本となる書籍編集、つまりは、従来の「狭義な編集」のエピソードのボリュームが多くなってしまわざるをえず葛藤した。それゆえ、アップデート版でまず書き加えたいと思っていたのが『いちじくいち』という秋田県にかほ市で年に一回開催しているマルシェイベントのこと。まずはその話からはじめようと思う。
秋田県にかほ市といえば、木版画家池田修三の生誕地として知られるようになったことは自著に書いたとおり。僕はこのにかほ市という町に、知らず愛憎が芽生えはじめていた。ちなみに僕にとって「愛」はつねに「憎」とともにあるもので、これは俗に言う「愛が芽生えてきた」と同義だから、気になる人は脳内変換してくれればいいと思う。どうしてそこにこだわるのかという僕の癖みたいなものは、連載を読み進めてくれればきっと理解してもらえるはず。
雄壮な姿をみせる鳥海山と麓に広がる九十九島。その周りを囲むようにある田畑と溢れる水脈。そのまま後ろを振り返れば広がる碧色の日本海。池田修三さんに惚れ込んだことから何度も訪れるようになったにかほ市だけれど、僕はいつのまにか、この圧倒的な風景にこそ魅了されていた。山と海が近い独特の風景という意味では、僕の地元神戸にも似ている。それゆえ何か特別な気持ちが生まれたのかもしれないけれど、正直に言うならば、僕は池田修三というよりも、このにかほという町のポテンシャルそのものに興味を持ち始めていた。
展覧会をすれば一万人以上の人が訪れ、空港や駅に作品が大きく飾られるようになったとはいえ、池田修三というコンテンツは、アートや芸術といったカテゴリーに分類される。池田修三の作品に魅力を感じてくれる人は確かに増えたけれど、その数はきっとどこかで頭打ちになる。そう思っていた。そうなれば、あとはじっくり時間をかけるしかないし、そこからは地元の人たちが育んでくれるのが一番だ。よって僕が池田修三さんに関してやれることは、ほぼやりきったような気持ちになっていた。
そんな2016年春のこと。にかほの酒屋さん「佐藤勘六商店」の三代目、佐藤玲くんから連絡があった。以前、僕が編集長を務めていた『のんびり』という雑誌の表紙撮影に参加してもらったこともあったので、僕は彼を、酒蔵の気持ちをきちんと届けようと奮闘するイケてる小売酒屋さんの一人と認識していた。しかし彼の口から出たのは「にかほのいちじくを取材してほしい」という言葉だった。
佐藤勘六商店がある、にかほ市大竹地区は『北限のいちじく』と呼ばれるいちじくの産地で、佐藤勘六商店は玲くんのおばあちゃんの代からその技を引き継いだ「いちじくの甘露煮」のメーカーでもあった。にかほの一般家庭のリビングに玄関に、普通に飾られている池田修三作品のリサーチのために、各家々を取材して回っていた僕は、常々このいちじくの甘露煮文化を不思議に思っていた。にかほの家にお邪魔すると、結構な頻度でお茶やコーヒーとともにいちじくの甘露煮が出てくる。しかし正直その甘露煮が僕は苦手だった。だって甘すぎるのだ。
にかほで採れるいちじくは、僕たちがふだん食べている、愛知や和歌山、僕の地元兵庫などで多く採れるいちじくとは品種が違う。全国的によく食べられているのは「桝井ドーフィン」という品種で、でっぷりと赤く完熟したいちじくの、その皮をむいてガブリと齧りつくのが一般的な食べ方だと思うけれど、秋田をはじめ東北で採れるいちじくは「ホワイトゼノア」といって、色は緑で小さく、甘さも控えめなゆえに、甘露煮にして食べるのが一般的。保存食として重宝されたゆえ、大量の砂糖を投下するので、それはまあ強烈な甘さなのだ。
「にかほのいちじくを取材してほしい」そう玲くんに言われた僕は、思わず苦い顔をしてしまった。それは、あの甘いやつかー! と思ったからだ。しかし冷蔵庫も冷凍庫も普及した世の中で、そこまで糖度を高めなくとも、もうちょっと甘さ控えめに作って瓶詰めし「いちじくのコンポート」なんて言ったら、急に「DEAN & DELUCA」とかで女の子が好んで買ってくれそうだし、すなわち僕はそこに編集の魔法をかけてみる余地みたいなものを感じた。
実際、食文化が多様化したいま、にかほ市内でも甘露煮を作るのは年配の人だけになってきているとのこと。僕は奇しくもまた、池田修三さんのことを思い出した。当時、にかほの家庭にある修三作品を探しまわっていた時に何度も聞いた「最近まで飾ってたんだけど」という言葉。タッチの差で押入れの奥にしまわれてしまっていた修三さんの作品が、再び飾られるようになったいま、僕はにかほに住む人たちに誇りを感じてもらうためにも、そのアイデンティティとしてのいちじくに再び火を灯すのもよいかもしれないと思った。時代に合う甘露煮文化や、いちじくの食べ方を提案すればいいし、何より、アートに比べて食は広くて強い! いちじくをもって、より多くの人に、にかほの魅力に触れてもらえる機会をつくれるかもしれない。
その瞬間、僕の頭に一つのイメージが浮かんだ。旬のいちじくを求めて次から次へとこの町にやってくるたくさんの人たち。そこここで、いちじくを使ったスイーツを食べながら談笑する人々。DJブースから流れる音楽に身をまかせつつ、肩寄せ合う恋人たちの眺める先には、夕日を浴びて染まる鳥海山・・・。
雑誌で紹介してほしいという玲くんを前に、僕はこう言った。「じゃあ、マルシェをやろう!」


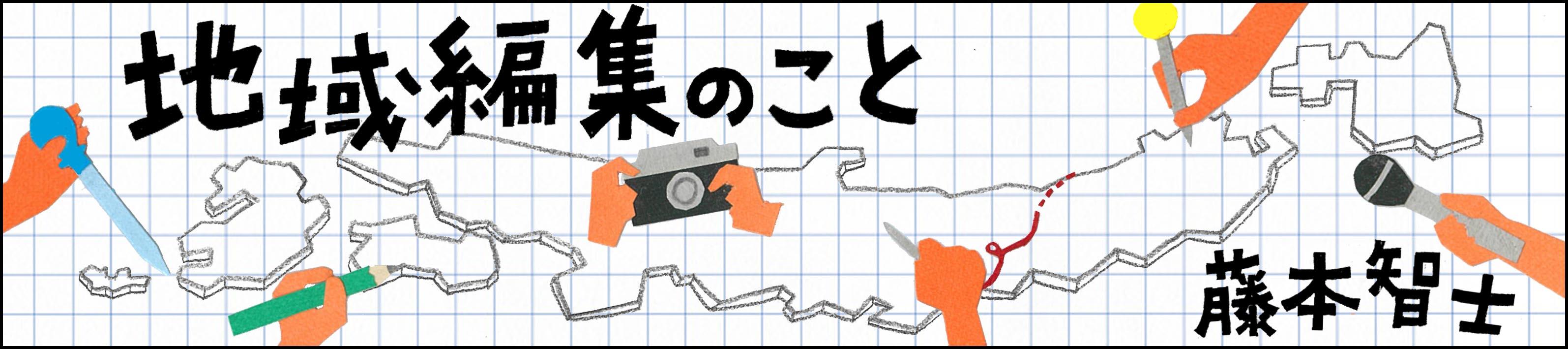






-thumb-800xauto-15803.jpg)
