第36回
編集視点を持つ一番の方法
2021.10.08更新
もはや、地域に必要なのは、よそ者というよりも、その土地の人たち自身が「よそ者目線」や「よそ者思考」を持つことなんじゃないか。そしてそのキーとなるのが編集視点だと書いた前回。では、その視点ってどういうものなのかについて書いていく。
そこでまず最初に挙げられるのが「俯瞰」の視点だ。地域で活動をするなかで積極的に動くということは自分自身がプレイヤーとなることでもあるけれど、それゆえ当事者としての絶対的な思いや願望が強まりすぎて、他者の意見をフラットに聞けなくなってしまいがち。そんな時こそ、自分のなかの当事者意識を敢えて横に置くことが大切。人間は行動すればするほどに、それを正当化したくもなるから、それに対して否定的な言葉を聞いたときに、受け入れがたくなる。俯瞰で見るチカラというのは、異なった意見から、他者の風景を認識するチカラでもある。当事者でありながら俯瞰で物事を見るというのは難しいけれど必ず必要なこと。
しかしどうやったらそんな視点を持てるのか? その方法は実は明確で、過去を知ることだと僕は思う。そもそも歴史を知ることなくして、次の一手が打てるはずがない。どれだけ革新的なアイデアも経験の先にある。歴史をみるというのは、時間を大きく捉えるということで、これ以上に俯瞰的な目線を得られる術はないだろう。ただ、俯瞰で見よとだけ言われると、周りの環境や、周辺の人たちの関係性などに目が行きがちだけれど、そういった水平軸的な視点も大事ながら、それを半ば強制的に垂直に拡げてくれるのが、記憶や記録だ。ここでかつて何が行われていたのか? 何故いまこうなっているのか、そこにこの土地の風土が関係しているのではないか? そういった問いから必然的に生まれるフィールドワークが視界を全方向に拡げてくれる。そうやって「知る」ことから立ち上がってくる何かを捉えることが、編集の本当のスタートだ。編集において「取材」が欠かせないのは、そういう理由だと僕は考えている。
だからもしあなたがいま何か新しいアクションや企画を進めていて、その根っこにあるのは自分の発想や閃きだと感じているならば、くれぐれも気をつけてほしい。その思いは必ず反発と軋轢を生む。これは僕自身、痛いほど経験してきた。いかなる課題もそこに至る理由があって、その経緯を軽んじている自分に気づくことができるかどうかはあなた次第だ。そういった自分の奢りに気付かせてもらえるかどうかの分かれ目となるのが傾聴力の有無。
かつて僕は大先輩編集者である後藤繁雄さんに「編集者とはインタビュアーだ」と言われたことがある。その言葉を聞いた20代の僕はインタビュアーはライターさんの仕事では? としか思えなかったけれど、いまはその意味がとてもよくわかる。編集の仕事が取材という名のフィールドワークからしか始まらないのだから、そこにはまず聴く力が必要だ。しかし一般的にインタビューの上手さのモノサシとされる、話を引き出す力、つまり「訊く」力はさして重要ではなく、それよりも「ただ聴く」力が重要だ。仕事としてのインタビューでは、僕は対話をとても重んじるけれど、リサーチ、取材、フィールドワークにおけるインタビューにおいては、ただ聴くことを重んじる。自分の意見を伝えようとするのではなく、ただ聴くチカラを持つ人は、異なった意見を受け入れる力がある人で、そういう人は、自分の外にある多くのものから気づきを得るチャンスが幾度となくやってくる。そうやって過去を知ることから人は謙虚さを得る。その謙虚さが編集者には不可欠だ。
僕は元来、編集という仕事は単純な影響力の大小で図れないものだと思っている。それはそもそも編集の意義が「小さきものの声に耳を傾ける」ことにあると信じているからだ。黙っていても聞こえてくる大きな声よりも、小さいけれども切実な声に耳を傾けられる編集者に僕はなりたい。そういう意味でも、過去を知るためのフィールドワークから、その地層にある小さな声の蓄積を感じるチカラを持ちたいと思う。


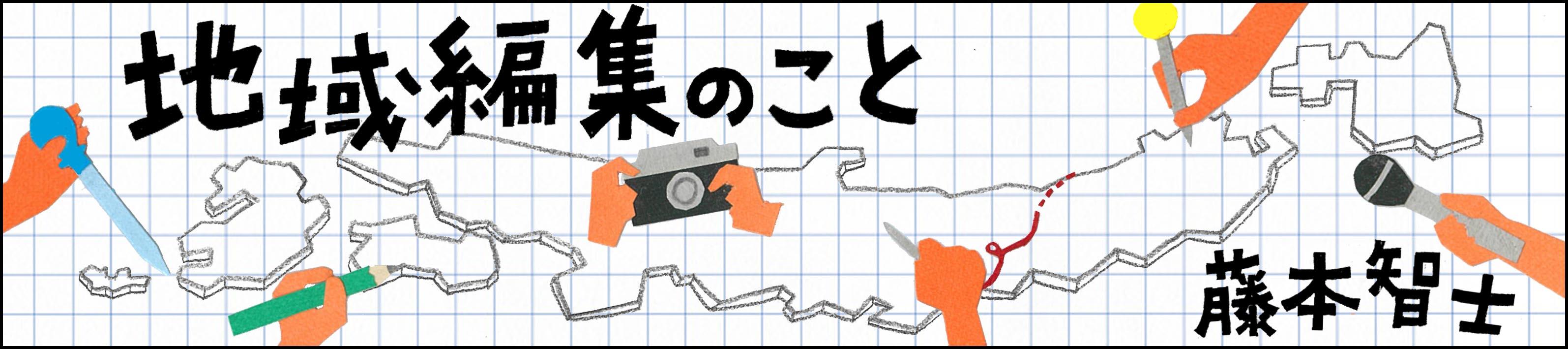




-thumb-800xauto-15803.jpg)


