第53回
市政と市井をほどよくグレーに。
2023.03.07更新
先日、ご縁があって長野市役所に勤める約100人の方にむけて講演をさせてもらった。市のブランディング施策の策定のために地域編集事例を話してほしいとのことだったので、資料をつくっていたら、スライドが240枚以上になった。実際見せることができたのは170枚程度だったけれど、まあ想定内。それでもよく見せられたほうだと思う。僕は講演も誌面もエンターテインメント性が重要だと思っている。それもこれもとにかく内容が胸に届いてほしいからだ。どこの誰だかわからないおじさんの約90分もの講演を聞いてもらおうと思えば、それなりに気を引く努力をしなきゃ難しい。この人数になってくると、僕の講演を能動的に見たいと思って来ている人なんて一握りだ。M-1グランプリのダークホース枠みたいな気持ちで取り組むしかない。ネタ時間4分に対するボケ数がついつい増加するように、知らずスライドの枚数が増えていた。
そもそもどうしてそんなに今回の講演に熱が入ったのかというと、久しぶりに行政の人たちだけ、しかも一つの市役所のなかの人たちだけにむけた講演だったからだ。長野市というそこそこ大きな都市とはいえ、役所内の方が100人も集まってくださるということは、さまざまな部署の担当者が聞きに来てくれているということ。となれば、先述のとおり、渋々来ている人が相当いるはず。そういうどっしりと背もたれに身を預けている人にこそ、僕は届けたいことがある。だからこそ、シンプルに燃えた。
地域編集がテーマとはいえ、観光やシティプロモーションを担当する部署の方だけではなく、日々粛々と市民の生活と向き合い、お仕事をされている人たちが、そこには多くいらっしゃったはず。ならばまさに、そういった役所全体の空気みたいなものを醸成するお手伝いができるとてもよい機会に違いなかった。市のブランディングなんてものは、いわば空気づくりだ。編集者がつくれる最大のものは、そこはかとなく漂う空気なのではないかと僕は思っている。そんなことを考えてスライドをつくっていたら240枚を超えてしまったのだ。
 撮影:徳谷柿次郎
撮影:徳谷柿次郎
今回の講演のメインに据えたことは、秋田県庁のみなさんと取り組んだ『のんびり』というフリーマガジンの話だった。県のみなさんと、まさに「一緒に」つくっていった『のんびり』は、僕にとって忘れられないお仕事の一つで、この連載でも何度も書いている「ディレクション」つまりは仲間づくりの大切さ、真のチームプレイの重要性みたいなことを身をもって体験させてもらった大切なお仕事だった。そもそも行政の方との取り組みというのは、予算ベースで動くので、民間の事業者は、まずその予算を取れるか取れないかというところに執着しすぎる。それゆえに、「取れましたー! コンペ受かりましたー!」みたいな報告をまるでゴールテープを切ったかのように伝える人も多く、まさにその空気が行政の方々にも伝わるからか、自治体の担当者も、事業者を決めることで大きな仕事を果たし終えたような顔になる。これは本当によくない。
行政の方々が民間の事業者に発注して「はい、あとはよろしくお願いしますね」とバトンを渡し、民間の事業者も「はい任せてください」と言いつつ、できるだけ粗利を多く残すことに注力するような、不毛なプロジェクトゲームが全国で実際に行われている。そんなことにしないためには、密なコミュニケーションがとても大切だ。立場も考え方も、何を大切にするかという哲学も、まったく違う人たち同士が、ときにぶつかりながらも、互いに信頼を積み上げていくことの先にしか、よいクリエイティブは生まれない。そこにどこまで本気で取り組み合えるか、行政の人たちがどこまで本気で関わろうとするかが、スタートラインですよという話をした。
ここで、講演で話したエピソードを一つだけ抜き出すと、僕は秋田で初めて、県庁職員にこんな一言をもらった。
「何かあったら我々が守りますから」。
これは、『のんびり』を一緒につくっていた、県庁の担当職員の方の言葉だ。よりよいものをつくりたい。より胸に届くものをつくりたいという一心で、既存の雑誌づくりとは違うアプローチの取材を続けていた僕たちは、それゆえに起こり得る急な取材依頼など、行政の人たちにとっては、ある種のクレーム対象になりかねないようなことを、黙認というより、もっと積極的な態度で見守ってくれていた。
「何かあったら我々が守りますから」。この言葉は、絶対に迷惑をかけちゃいけないという我々編集チームの緊張感にもつながったし、実際どうしてもそういったことが起こってしまったときに、本当に県庁のみなさんは僕たちを守ってくれた。フリーマガジン『のんびり』が持っている臨場感ある取材体験は多くの人の心を動かし、読者をも巻き込んだムーブメントを起こしていったという自負があるけれど、その背景には、そのリスクをともに背負い込んで一緒にたたかってくれた県庁職員の方たちがいたという事実。そんな職員のみなさんと出会えたことは、その後の僕の人生の強い希望となっている。
僕はスライドの最後に、こんなメッセージを入れた。
「グレーをわるものにしない」
ほとんどの人はみな、僕たちの前例のないチャレンジを、既存の枠組みに押し込めたり、枠から外れる部分を無思考にカットしたり、ひどいときは、枠内のさらに内側に防護線を引いて押し込める。しかし、それが行政の人たちの役割や使命じゃないはずだ。
白黒はっきりさせるのは一番簡単な仕事。グレーをグレーのままにというのは、目の前の事態にしっかりと向き合い続けるということだ。日本の真ん中の政治が、黒をグレーに見せようとしているけれど、地方で踏ん張る僕たちのグレーはそうじゃない。もっとピュアに美しいグレーだ。そのためには、本来わかりあえない立場の行政と民間が、互いを知ろうと努力することが大切。もちろんこれは、行政の人たちにだけ歩み寄りを求める話ではない。逆に「まったく役所の奴は」なんて言葉を気軽に発する民間の人を僕はまったく信用しない。市井の人々の思いが市政そのものにつながっていくような、そんな美しきグレーのなかで、僕はこれからも地域編集を続けたいと思う。


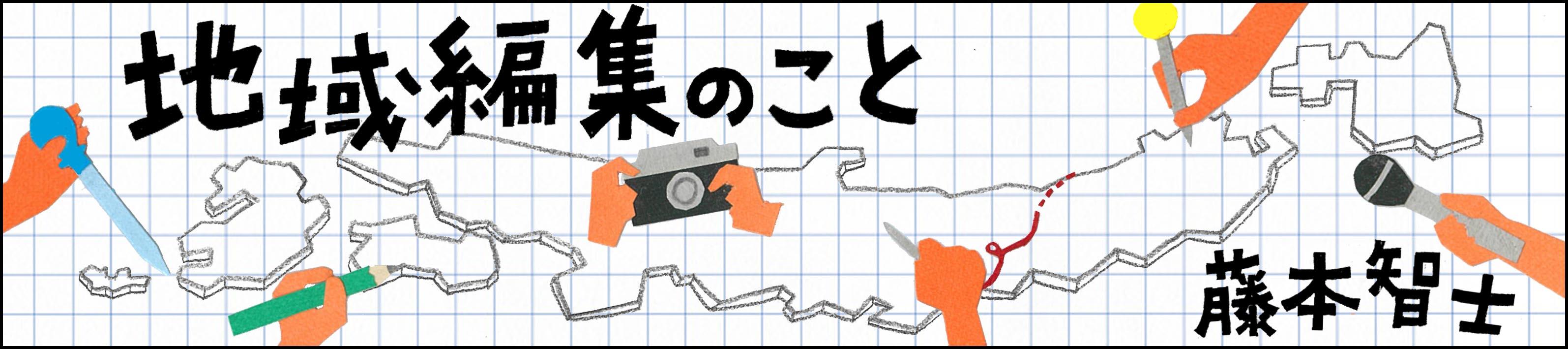

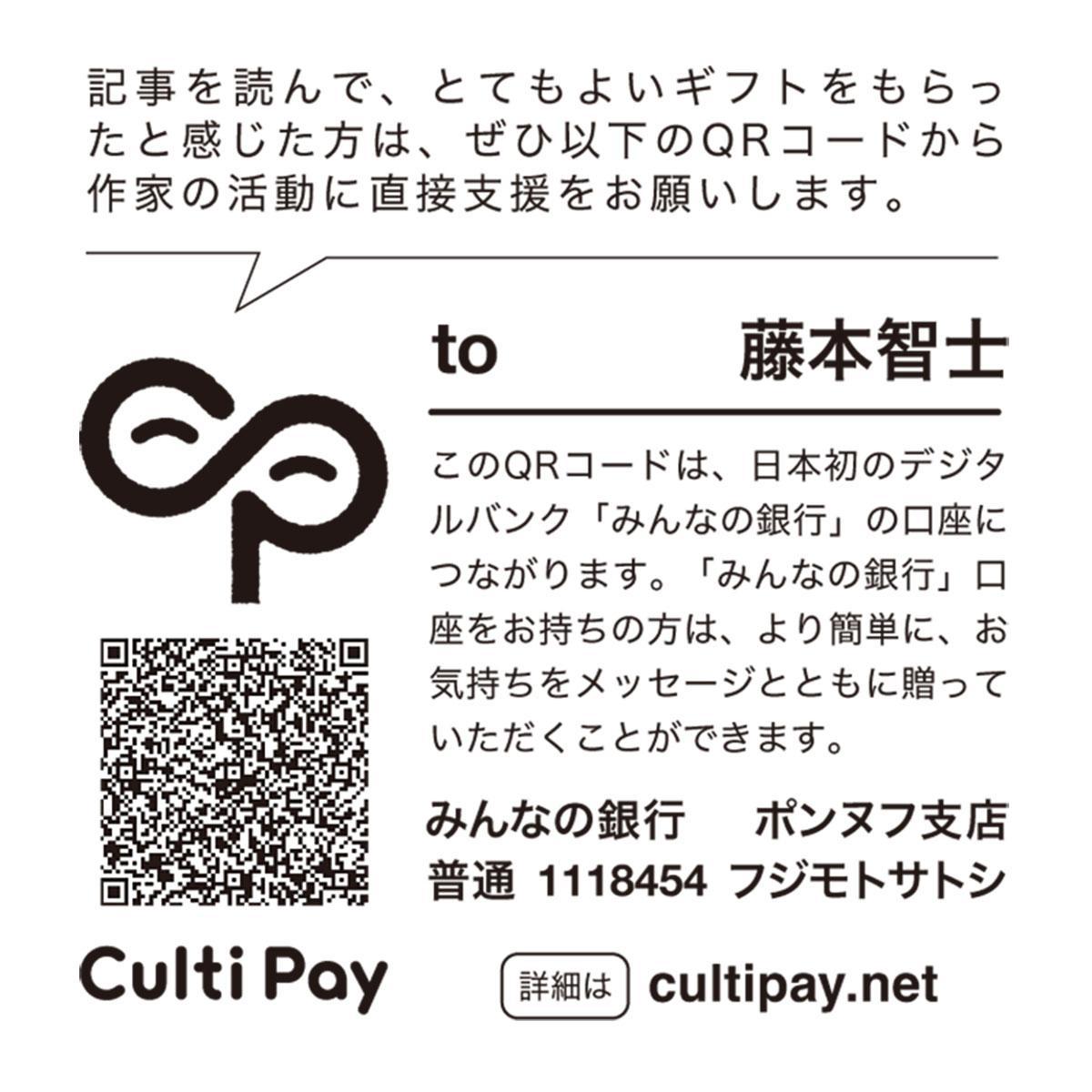


-thumb-800xauto-15803.jpg)


