第50回
フックアップされることで知る編集のチカラ
2022.12.07更新
僕のつたない企画書が、後藤繁雄さんという大先輩編集者の手によって『artbeat』というイベントに昇華された。若かった僕は最初こそ一瞬戸惑いつつも、とにかくそれを受け入れ、その波に乗らせていただくことにした。大阪でフリーペーパーをつくっているだけの、何者でもない僕にとって、こんなにもありがたい話はなかった。
そもそも僕が書いた企画の骨子は、クリエイターたちのマーケットブースを真ん中に、音楽ライブ(無謀にもベックを呼びたいとか書いてた・・・)や、フードマルシェなどを開催し、関西からアートの大きなうねりをつくりたいというもので、形としては、いまでいう音楽フェスに近いものだった。フェスの先駆け『FUJI ROCK』が苗場での開催をはじめたのが1999年だから、きっとそういったイメージも強くあったのだと思う。
とにかく後藤さんは僕のパラパラとしたまとまりのない企画にまさに心臓を埋め込んでくれた。当時、後藤さんは「これからは環境とアートの時代だ」と、しきりにおっしゃっていたけれど、デザインクリエイティブしかり、フードしかり、音楽しかり、それらの真ん中にある衝動のピュアな発露がアートなんだと、すなわちすべてのクリエイティブの源泉にartの鼓動があるんだということをそのタイトルを持って表現してくれた。実際そのことで、多種多様な運営メンバーが一つになった。これは間違いなく編集のチカラだといまは思う。
また、会場内でごみゼロナビゲーションの試みなども実施し、環境負荷について考える場面も組み込まれており、そういう意味で『artbeat』は現在の『ap bank fes』に近いイベントだったかもしれない。ちなみに『artbeat』は2001年の開催。のちの『ap bank fes』につながる、ap bankの設立が2003年。少なくとも、2000年代における優秀なプロデューサー・編集者のなかで重要なシンクロニシティがあったことは間違いないように思う。アートの鼓動を真ん中にした『artbeat』は、5万人の観客を動員し、見事に成功した。
後藤さんのディレクションのもと、アートマーケットという最も肝となる部分の責任者を任された僕は、明らかに自分の器を超えるイベント運営を前に、どんな心持ちでいたのだろう。まだ26歳だった僕にとって何もかもが初めての世界。必死の思いでくらいついていたように想像するけれど、不思議なことに、辛かった記憶は一つもない。人間の本能として、あまりに辛い経験を綺麗さっぱり消去してしまったのかもしれないけれど、おそらくそれ以上に、自分の小さな企画アイデアがこんなにも大きなイベントとして現実のものになっていく姿に、どこかずっと興奮していたんだと思う。そしてその高揚感の源は、間違いなく後藤さんだった。後藤繁雄というスーパー編集者の振る舞いを間近で見ることが出来たことは、僕の血肉となっている。
明確な編集視点をまだまだ持てないでいた20代の僕にとって、編集に対する考え方や、ある種の編集者像は、後藤さんの哲学と行動をベースにつくられた。当時、後藤さんはスーパースクールという編集スクールもやっておられたと記憶しているけれど、ある意味で僕は無償でそのスクールに通わせてもらっていたようなものだった。いや、全てが現場実践だったから、それ以上の経験をさせてもらっていたに違いない。
artbeatの成功を受けて、たった半年後に第二回が開催されることになった。当時閉館していた老舗百貨店、心斎橋そごう(現在の心斎橋PARCO)1階スペースを丸ごと使ってやらないか? という話が浮上したのだ。そして2001年9月、artbeatの第二弾『ARTBEAT DEPARTMENT』が開催された。artbeat同様、アートマーケットの責任者を任された僕は、ライブペインティングの企画を後藤さんに提案してみたのだけれど、その回答として後藤さんはそのステージを会場を大きくゾーン分けする長い壁にしてしまおうと提案されて度肝を抜かれた。そんな大胆な会場デザインをつくったのが、当時、新進気鋭のデザイン集団として注目されつつあったgraf。いまでは巨匠感ただようgrafさんだけれど、当時はまだ代表の服部滋樹さんも30代で、そのことに改めて後藤さんの編集手腕というか、ストレートに言えば度胸のようなものを感じる。
grafさんの名が知られるようになったのは、間違いなく、青森県弘前市にある煉瓦倉庫を舞台にした、美術作家、奈良美智さんとのプロジェクト『Yoshitomo Nara + graf AtoZ』だと思うけれど、それが2006年だから、さらにその5年前の時点で、grafさんに会場デザインを任せてしまう審美眼には、いまさらながら惚れ惚れする。僕はそこで編集者の大きなしごとが、フックアップであることを知ったように思う。有名無名。大衆性と革新性。本質と軽薄さ。そういった矛盾するもの同士の幸福な関係を描き、この世に生み出すことが、僕の編集の真ん中に存在するのは、きっとそのせいだ。才能を信じる気持ちと覚悟があれば、ステージを上げるチカラが編集にはある。
また、後藤繁雄さんは京都出身ながら、その活動拠点が東京だったゆえ、関西のアートシーンにおいてかなり、よそ者な立場だった。それゆえ、関わる大人たちのなかには後藤繁雄という編集者(プロデューサー)の登場をよく思わない人もいたように思う。しかしその絶妙な距離感と中立的な立場が、関西のクリエイティブ界隈の妙ななわばりや、閉塞的なコミュニティの壁をないものにした。間違いなく後藤さんはそれを意図的にやっていたように思う。地方の面倒な政治を飛び越えるために有効なものは、よそもの・ばか者・若者だとはよく言われるけれど、よそ者の後藤さんは明らかに何も知らぬ馬鹿なふりをして様々にジャンルを越境し、そしてまだ若かった僕をフックアップした。それは後藤さんにとっての一つの手立てだったのだ。それを証拠に、後藤さんは僕と初めて会った新阪急ホテルのラウンジでこういった。
「俺はこれから数年、君のことを利用するから、君も俺のことを利用しろ」
初対面の僕にだ。利用という言葉に、なんだかわるい印象を持つ人もいるかもしれないけれど、それは僕にとって悪魔というより、天使の契約だと感じた。


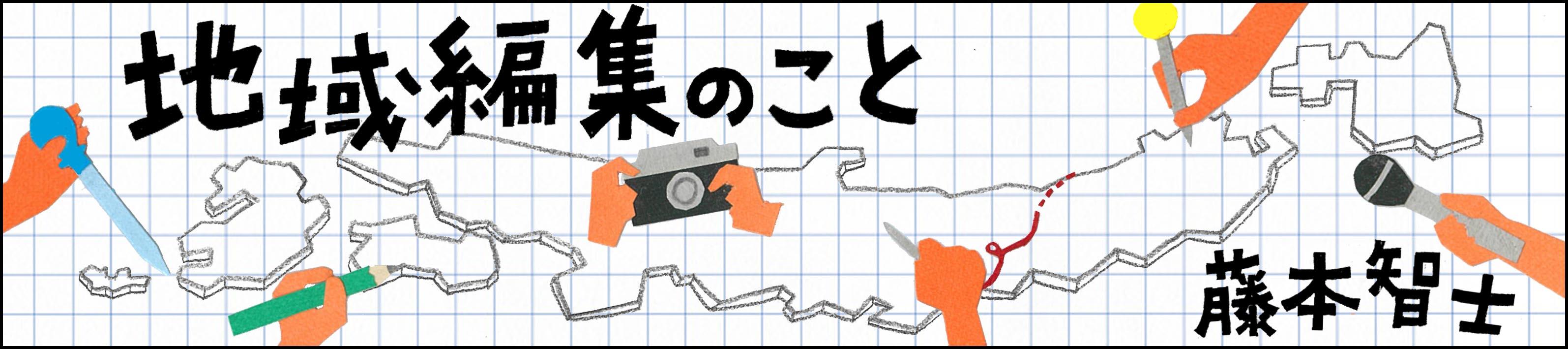

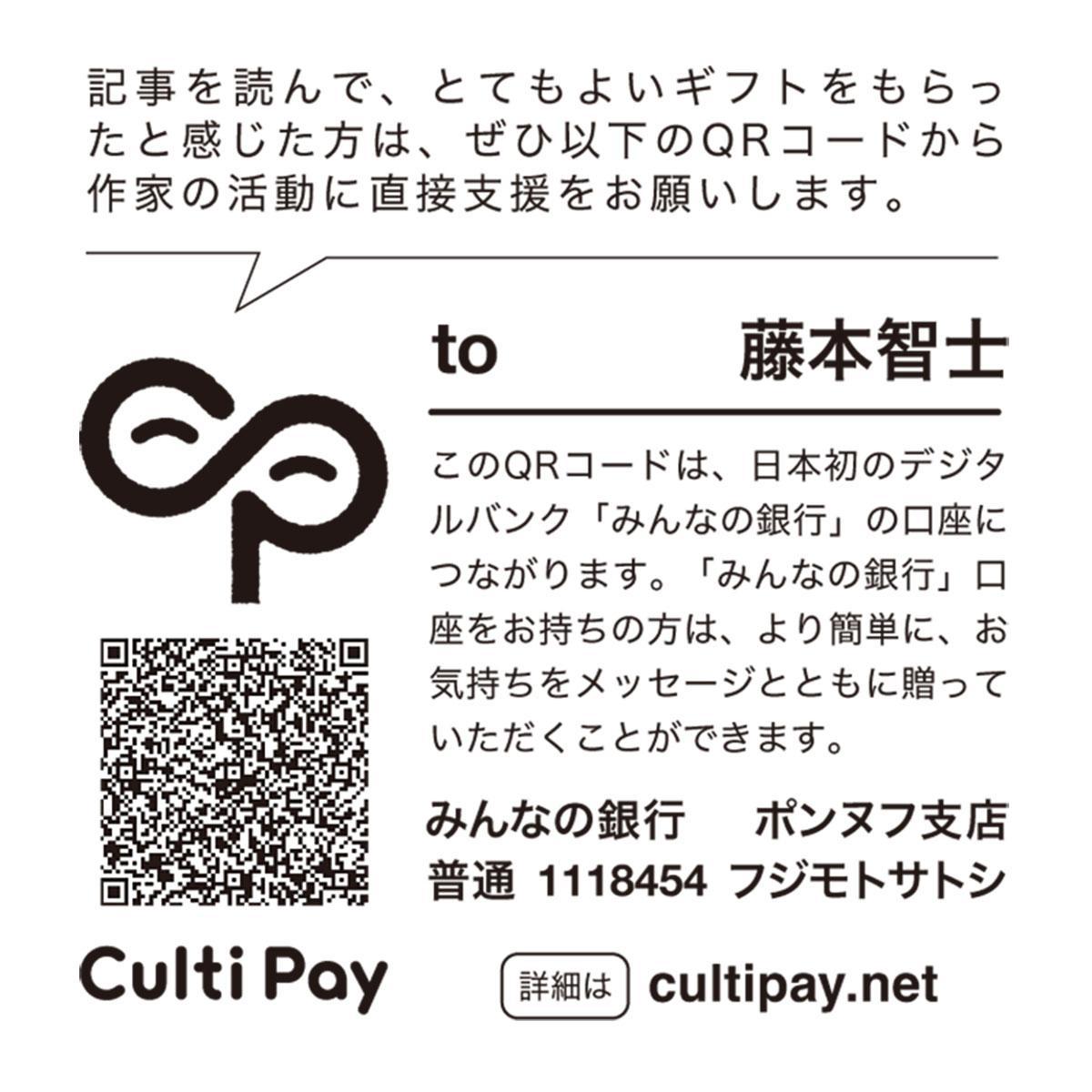


-thumb-800xauto-15803.jpg)


