第44回
編集のスタートライン
2022.06.08更新
これまでさまざまな地域における編集事例を通して、書籍や雑誌などのテキストメディアだけではない編集について考えてきた本連載だが、気づけば丸3年以上連載を続けさせていただいている。ある意味で僕の思考の整理の場にもなっていて、ときにチャレンジングな場所として、ミシマ社のみなさんにはとてもおおらかに対応いただいていたけれど、この3年間を経た僕の編集に対する現在地をしっかり書き記していきたいなと思う。
言わずもがな、僕は編集者だ。しかし僕が編集するのは本や雑誌やWEBメディアだけではない。僕が編集する対象は、ときに商品だったり、イベントだったり、場所だったりする。ゆえに僕が言うところの「編集」をまっすぐ文章の編集だけだと思われると、どうしても齟齬が生じる。そこでいよいよ「編集」や「編集者」という言葉の定義を拡げていきたいと思って書いたのが、この連載のきっかけともなった『魔法をかける編集』(しごとのわ)だった。
世の中の変化もあって、編集という言葉は随分広義に捉えられるようになったと感じるけれど、それでもまだまだ僕の思う編集の姿には程遠く、だからこそ「地域編集」といった言葉を積極的に使うことで、編集が紙面に落とし込まれるものだけではないということを伝えようともした。
しかしいよいよ思うのは、その前にまずやるべきことは「編集とは何か?」を明確にすることだ。それこそ「地域編集」なる言葉における「編集」とはいったい何なのか。「言葉を集め編むこと」が象徴しているものについて明らかにすること、すなわちそうやって「編集」という言葉の領分を明確にすることではじめて、「編集」の定義は自然に拡張するんじゃないか。
そもそも僕はよいもわるいも「らしくない」編集者だと思う。飲みの場で後輩編集者たちに「あなたは作家だ。白状しろ」と詰め寄られたこともある。うん確かにそうかも、と思った。彼らの言葉の意味するところは、きっと僕が多分に表現者的だということなのだろう。けれど僕はおかげでそこに編集という概念の線引きが見えた気がした。多くの人たちにとって、編集者というものは裏方稼業なのだ。だけど僕にとっての編集者とは決して裏方ではなく、ある種の作家性も持ち得るし、積極的に世の中を変化させようとする活動家のような側面もある。ただそのように見えないのは優れた編集者たちがみな、とても謙虚だからだ。ちなみにその謙虚さは、そういう心持ちでいましょうねという道徳的な態度の話ではなく、どうしたって謙虚にならざるを得ないさだめの話。編集は自らの無力さを受け入れるところからしかスタートしない。自身の無力さを知る人。それが僕は編集者の絶対条件だと思う。まずはそこから語ってみたい。
まさに僕は昔、作家(小説家)を目指していたことがある。そんな僕が作家になることをやめたのは、26歳の時、こいつには敵わないなという人物に出会ったからだ。と書くと、ちょっぴりネガティブな挫折エピソードに思われるけれど、この時の心情はとてもポジティブで、清々しいくらいの開放感とともに前向きな気持ちで満たされていた。僕はあの瞬間、能力をアウトソーシングすればいいということに気づいた。それはもはや強大な力を得たようなものだった。無力さを受け入れることが、僕に大きな力をくれた。若いうちは「こういうことが得意です」「これが僕の良さです」みたいなことをアピールすること、もしくはそうやってアピールできる事柄を増やすことに必死になりがちだけれど、それが有効なのは、ほんのひと握りの特殊な才能を持ち得た人たちだけのような気がする。いや、そう思える人ほど、早い段階で自らの無力さを認めたのかもしれない。出来ないことを知ることは、譲れぬ大義を実現するための大きな器となる。
それこそ20代の頃は、僕自身がどんな料理をつくれるかということばかりを考えていたけれど、そもそもその料理、僕が作らなくてよいのでは?と気づいたことが、僕に素材の重要さを教えてくれた。それを調理するシェフはもちろん、器、テーブル、カトラリーなど、その周りにまでイメージが及んだとき、人は編集という行為の小さな一歩を踏み出すのだと思う。
つまりそれがディレクションだ。これこそが、編集のスタートにしてゴールとも言える、もっとも大切な部分だと僕は考えている。わかりやすく、雑誌づくりで言うならば、カメラマンは誰がよいか、ライターは誰にするべきか、イラストは誰に描いてもらうとよいのか、そういった采配をもって編集者はクリエーション(創造)するのだ。
ここからすでにものづくりははじまっているのだという自覚がないディレクションは、取り急ぎだからと100均で買った器で、結局日々暮らしていくのと似ている。あの日、あの時、何気に「とりあえず100均でいいか・・・」と思った自分が、いまの暮らしのスケール感をすでに確定させてしまっている。だからこそ僕たちは、誰に頼むか? ということに、とても神経をとがらせる。編集が甘いなあと感じてしまう物事の多くはこのディレクションに問題がある。本連載でも取り上げ続けてきた「地域編集」というフィールドにおいても、この最も大切なはずのディレクションを大切にしていないことが多い。編集者にとって最もクリエイティビティを発揮できる部分がこのディレクションであり、編集者が最初にメッセージを込める場所こそがディレクションだ。自らの無力さを真摯に受け入れた人だけが立てる地点。そこが編集のスタートラインだ。


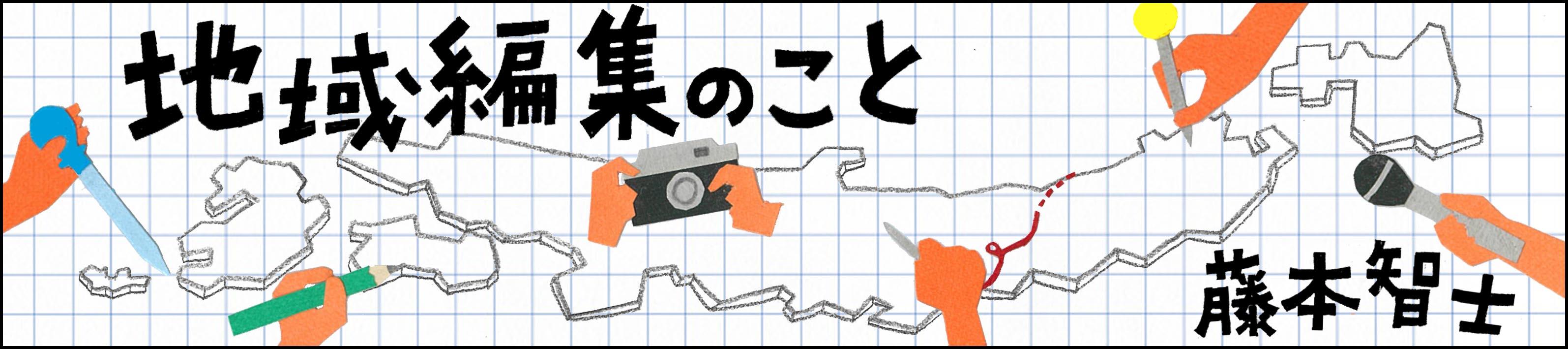




-thumb-800xauto-15803.jpg)


