第58回
縁食から世界を変える(1)
2020.12.17更新
お金の「円」ではなく、人と人、また人間以外のものとの「縁」をベースに「食」を考えなおした、藤原辰史さんの新刊『縁食論』。「縁食」のようなしなやかなつながりが、コロナ後の社会の鍵となる、とすでに多くの反響をいただいています。
そんな本書の発刊を記念して、『うしろめたさの人類学』の著者である文化人類学者の松村圭一郎さんとの対談イベントをMSLive!で開催しました。
松村さんが投げかける問いから、とてつもないスピード感でおふたりの思考が深まっていき、「縁食論のその後」のようなお話にまで議論が及びました。その模様を、本日と明日の2日間にわたってお伝えします。
構成:田渕洋二郎
社会の歪みが家族に丸投げされている
松村 今日はよろしくお願いします。この『縁食論』を手に取って読み始めると、最初のほうで私の名前が2箇所くらい出てきて、読み終わると『うしろめたさの人類学』の広告がばーんとあってもう「松村、出てこい!」と呼びかけられている感じがしました(笑)。
藤原 明らかにそうですね(笑)。
松村 今回は『縁食論』の徹底解剖ということで、私がポイントだと思った部分やもう少し掘り下げたいところをぶつけながら話を聞けたらなと思っております。
藤原 よろしくお願いします!
松村 まずは、サブタイトルに「孤食と共食のあいだ」とあるように、「孤食」は文字通りひとりで食べることで、「共食」は家族でちゃぶ台を囲んで一家団欒というイメージ。その「共食的」な家族の食のあり方を、藤原さんは「家族絶対主義」という言葉で批判していますよね。なぜ、家族の食を論じなければいけない、と思ったのかを最初に聞かせてもらえますか?
藤原 そうですね。いま、家族という形態がすごく多様化していて、ひとつの家に赤の他人が一緒に住んで台所を囲む「シェアハウス」みたいなかたちもあれば、ひとり親や、夫婦だけの家族もある。でも近代家族を前提に設計されたいまの社会が、この家族の多様化についていけていないんです。その際たる例が介護や育児で、政治家は近代家族のモデルに従って、全部家族に面倒をみさせようとする。自民党の改憲草案にも「家族は大切にしなくてはならない」とありましたが、そういう言葉ですべてを家族に押し付ける国家のあり方を批判したかった。
松村 そこはとても重要な点だと思います。家族は心安らげる場だということが当たり前になってますけど、家族を愛情関係として捉えはじめたのは産業革命以降ですよね。それ以前の家族は、農民にしても町人にしても、生業や商売を成り立たせるための経営体だった。家業をやるための最小単位なわけです。でも近代化するにつれて、仕事や職場が家族から分離されるのがミソだと思うんです。藤原さんはその近代化と家族のつながりが強調された流れについてはどう思われますか。
藤原 経済の面から話すと、資本主義の内部で作れないものが、自然の力、具体的にいえば、土や海、労働力でもある「人間」なわけです。人間は家族にしかつくれない。そして、仕事をして疲れて帰ったというときにもう一度「労働力」として働けるように回復させる装置として、今の社会で家族が必要とされているんです。
でもそれは市場外にあるから、法律やイデオロギーでコントロールしていかないといけない。だからこそこの家族を語るときに「愛」というのが上から降ってくる、という仕組みになっているんじゃないかなと思っています。
松村 そうですね。そして、癒しの場であることが家族に求められているとしたら、労働条件の悪さとか社会の歪みみたいなものの解決が全部家族に丸投げされていることにもなる。
それを社会の側で解決しようとはせず、家族にまかせきりになっている今の状況こそが、結果として家族の多様化にもつながっているんだと思います。
藤原 そうそう。本来は企業や地域、また福祉でケアしてあげていたものが全て「家族」におしつけられている。介護の問題にしても、施設にあずけるのが難しい場合は、家で見るしかない。『縁食論』を書く前提としてそういう状況がありました。
松村 大学で教えていても、しんどい状況になる学生がときどきいるんです。話を聞いてみると、家族の問題が背後にある。そして家族の問題になってしまうと、社会から見えないプライベートな空間で、公的な支援も入りにくい。
この前、「プリズンサークル」という、日本で唯一更生プログラムを導入している島根の刑務所に、カメラが入ったドキュメンタリー映画を見たんですけど、そのなかでも、罪を犯した若い受刑者が生い立ちを語ると、ほとんどは家族に問題を抱えていました。食事をつくってもらえず、食べることができないとか、虐待を受けてきたとか。
いま日本はこれだけ豊かだけれども、この瞬間もひもじい思いをしている子どもたちがリアルにいるんですよね。その一部が犯罪に手を染めてしまうけれども、その子を罰したところで根本から問題が解決するわけではない。家族という問いは、食を考える上でもまず考えなくてはいけないポイントだと私も思いました。
なぜ「無料食堂」なのか?
松村 「家族」の問題と並んで、もうひとつこの『縁食論』で踏み込んで書かれているのが「無料食堂」ですよね。その前提として、かつて歴史的に存在してきた「公衆食堂」のことを説明してもらえますか?
藤原 そもそも公衆食堂の歴史を紐解くと、19世紀の貧民救済のチャリティー、そして第一次世界対戦中のヨーロッパの大都市が重要です。後者は、戦争が長引くなかで飢えている人が続出したことが背景です。そんななか、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、ウィーンなどいたるところで、ひとつの家族を超えたセーフティーネットとして、公衆食堂ができた。
日本でも関東大震災をはじめ、都市自体が不安定になったり、経済成長が活性化する中で貧富の差が激しくなったときに、福祉政策として自治体が公衆食堂を作ったんです。人力車のかたや、くず拾いをされているかたの溜まり場にもなっていた。安いチケットを買って、ご飯と味噌汁をとおかずを買って椅子に座って食べるというかたちで公衆衛生的にも清潔だった。
湯澤規子さんの『胃袋の近代』に書かれていますけれども、行政が資金を出すだけでなく、実業家がお金を出し合う場合もあって、かならずしも無料ではないけれども、どんな人でもきてよかった。
松村 ありがとうございます。こういった公衆食堂は少額であれ、お金をとるかたちですけど、『縁食論』では、食べ物に価格がつけられて売買されるのはおかしい、つまり、「無料食堂」を提案されています。これは、どういう経緯でたどり着かれたのですか?
藤原 この「無料食堂」の話は、試行錯誤しながら、清水の舞台から飛び降りるくらいの気持ちで書いたんです。やっぱり、5円くらいがいいかな、100円くらいがいいかなと何度も行きつ戻りつ考えて。
そんななかで無料食堂を人文学の課題として真剣に考えようと思った理由のひとつは、松村さんが議論の中でおっしゃっていた、エチオピアの国連の食料援助のお話にあったんです。食料は援助なので無料で手に入るんだけれども、それが入っている袋が市場で売られてしまう。贈与されたものがもう一度市場に流れてしまったり、あるいは地域の主に絡めとられて商品化してしまってギフトがそのままギフトにならないのはおかしいなと。
もうひとつはベーシックインカムですね。いろいろと歴史をみてみたんですが、やはりお金だと限界があると感じることが多かった。だから最初は、「ベーシック田んぼ」で思考実験したんです。全員すべからく田んぼをあげる奈良時代の「口分田」ですね。亡くなったら自治体に返して、基本的にはそこで何を育てても良い。しかし田んぼや畑は技術が必要で食卓にいくまでに挫折する人も出てきてしまう。
だから、調理済みのご飯が目の前にあって、誰もがありつける方が、社会として居心地がいいと思って、いっそのこと無料食堂について一度きちんと論じてみようと決めたんです。そして調べてみると、世界には、食べものを料理して無料で配っている例がいくつかあったんです。
松村 なるほど。たしかに、エチオピアの村でもシングルマザーや働けない高齢の女性がいても、そういう人もなんとか食べられるように融通するのが普通です。喜んであげるわけではないけれども、お腹を空かせている人がいたら、みんながちょっとずつ分け与えるのが人間としてあたりまえの行為。
だからこそ、日本で誰にも気づかれずにお腹空かせて餓死してしまう人がいる、という話をエチオピアでするとすごく驚かれるんです。「どうして隣の人に食べさせて、って言わなかったの?」と。日本では、家族や家がすごく閉じていて、周りの人がそこで何が起きているのか、たとえ虐待が起きていても、老人がひとり暮らしで困っていても、そういう状況に気づけない。もし、知っていたら手助けしますという人はたくさんいるのに、分断されて届かないんですよね。
お互いが「ありがとう」と言える場
藤原 エチオピアで「食べ物を施す」というときは、家に余っているものをあげるんでしょうか?
松村 農村だと調理済みではない芋やとうもろこしなどの作物をあげることもありますし、都会だと、残飯に近いものや乾燥したパンなどもありますね。日本もちょっと前までは、作りすぎちゃったとか、あまったので、というかたちで食べ物が回ることが日常の風景としてありましたよね。
あと、エチオピアの地方では、貧しい子は教会に預けられて、目の不自由な老人と一緒に家を回ったりする。それで食べ物をもらうと、彼らは神への祈りを捧げるのですが、そこで面白いのは、食べ物を渡す側も最後は神に祝福されて、最終的にもらう側になる。食べ物をもらう側も、ただみじめな思いをするのではなくて、与える側になっているんです。ちょっとした負い目が宗教的なものを介して解消される仕組みがある。
藤原 面白いですね! 『縁食論』を書いているときも、「あげる」「もらう」の関係で起こる負い目やスティグマがずっと気になっていたんです。「教会」というある意味での烙印を解いてくれるシステムがあるのはいいですね。
松村 『縁食論』でもシク教徒の寺院の話が出てましたけど、イスラム教でもラマダンの時期なんかは食事を大量に作って、日没後みんなで食べますよね。お金を出せる人が寄付をして、お金のない人も何の気まずさもなく、みんなで食べる。そうやって神を通して、無料で食べ物をえられて、負い目も恥ずかしさも生じない。
ただ日本で負い目を感じることなく、無料で食事を食べることはできるだろうか、と思うんです。無料か有料かという問題では解消されない何かがある。そもそも無料食堂を開設するとしても、今の日本の状況だと近所で反対運動とか起きそうですし。
藤原 そうなんです。それを乗り越えるためには、ひとつは多機能性だと思っているんです。スタートから「貧困対策」と銘打つのではなく、溜まり場や、遊び場としての食堂にする。実際に「こども食堂」の現場でもそういう場所づくりを苦心してやってらっしゃいます。あと、「親が忙しいからきた」というかたちでこどもがきてもいい。
でも、それで本当に届けなければならない貧窮者がこれるかというと難しいところがあるんですよね。食べものを買うお金がなくて困っている人たちでも違和感なくこられる設計にするために思うのは、まずは空間の面で、屋根を高くして、半分外みたいな状況を作るのはどうかなと思っています。シンガポールのフードコートに「ホーカーズセンター」というのがあるんですが、座ることができて、とりあえず雨だけは防げる、みたいな。そういう空間だと存在が目立たない。服も靴も目立たなくさせることができる。こういうようなスティグマ問題について考えていました。
松村 それもいいかもですね。いろんな食堂の風景でいうと、つい最近お店を閉じてしまいましたけど、京都の出町柳の「餃子の王将」が30分皿洗いしたらただで食べさせてくれる、というのをやっていましたよね。あれもひとつの無料食堂のイメージかもしれません。食事と皿洗いを交換する仕組みで、お金のない学生に負い目を負わせない優しさがある。
藤原 そうそう。あれも思い出しながら書いていました。あと『うしろめたさの人類学』を読んでいても、わざと、ジャラっとこぼれ落ちるように小銭を持って歩いて、物乞いにあげる、という話ありましたよね。その感覚というか、私もドイツにいたときにホームレスがいらして、彼らは私がアジア人だからお金があると思って寄ってくるんですけど、そのとき「自分はこういう理由で今お金がない、つきましては今日パンが必要なので、お恵みいただけないかと」と理由を述べておられました。でもなぜかパッと出せなくて。そこで、すみませんけど「ドイツ語の講義をしてください。5分間私と一緒に喋ってください。」ということにしたんです。それで、当時の首相・シュレーダーの批判を言ったりしたあと、「お世話になりました。ダンケ・シェーン!」と言って、ドイツ語会話料としてお金をお渡しすることで、最初の出せなかったときの気持ちが少し解消されました。
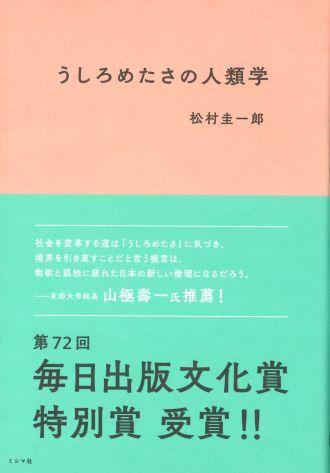 『うしろめたさの人類学』松村圭一郎(ミシマ社)
『うしろめたさの人類学』松村圭一郎(ミシマ社)
松村 物乞いをされたけれど、藤原さんが感謝して終わるのがいいですよね。私は九州出身なんですが、大学で京都に来て驚いたのが、バスを降りるときに乗客が運転手さんに「ありがとう」っていうんですよね。サービスで言うと、運転手が「ありがとう」という立場なのに、お金払って乗る人が「ありがとう」という。そういうどっちがどっちにしてあげたかが曖昧な状態でお金が払われる。どっちもありがとうと言って帰れる食堂がいいですよね。
『うしろめたさの人類学』にも書きましたが、東日本大震災のあと援助物資がたくさん倉庫に余っていたんですが、有料の「移動コンビニ」がきたとき、避難者の方が嬉々として買い物をしていたことがあった。そうやって、お金を払うことで「私が自分で選んで買っている」という感覚が生まれるのが、市場のモラリティなんでしょうね。お金を払うことでお互いが尊厳を持つ対等な存在になれて、わだかまりが生じない。そういう意味では、「商品化」することをあまりむげに否定できないのかなあと思います。
藤原 そうなんです! お金を介さないからこそ、偉そうになったり、上下関係ができてしまうのが、無料食堂に合わないなあと思っていたのでそこを指摘していただけてとてもうれしかったです。そして、いま、松村さんのお話を聴きながら、第3案の構想を思いつきました。
私が商品化をすごく嫌がったのが、外部の巨大な資本がそこに接続して、そうすると冷凍食品や大量生産したものになってしまうところだったんです。
でも今のお話を聞いて、無料食堂があるマーケットで、市場でしか通用しない、ローカルマネーを作るのはどうでしょう。ご飯だけでなく、地域通貨としてその場で払われる。そうすると、外部から入ってくることはなくなりますよね。
松村 おお! それを貧しい人がどう手に入れられるか、という課題はありますが、その可能性もまた考えていきたいですね。
(後編につづく)



 『縁食論』藤原辰史(ミシマ社)
『縁食論』藤原辰史(ミシマ社)
 「ちゃぶ台」が今号から「生活者のための総合雑誌」としてリニューアルしました! 藤原辰史さんと松村圭一郎さんによる対談「分解とアナキズム」も掲載されています。
「ちゃぶ台」が今号から「生活者のための総合雑誌」としてリニューアルしました! 藤原辰史さんと松村圭一郎さんによる対談「分解とアナキズム」も掲載されています。

-thumb-800xauto-15803.jpg)


