第2回
「万引き家族」を10倍楽しむための10章(1)
2018.06.05更新
第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝裕和監督。「万引き家族」のパンフレットには、「10年くらい自分なりに考えて来たことを全部この作品に込めようと、そんな覚悟で臨みました」という監督のコメントが載せられています。
2016年6月にミシマ社から発刊された『映画を撮りながら考えたこと』では、テレビディレクター時代から『海よりもまだ深く』まで、各作品をつくりながら考えてきたこと、試行錯誤してきたことの軌跡が、400ページ超にわたり綴られています。
本書を読んで、ぜひ「万引き家族」をより深く味わっていただきたい。そんな思いのもと、今回の特集では、『映画を撮りながら考えたこと』全10章からの引用ご紹介と、「是枝監督自著を語る」というイベントレポートのダイジェストを、2日間にわたりお送りします!

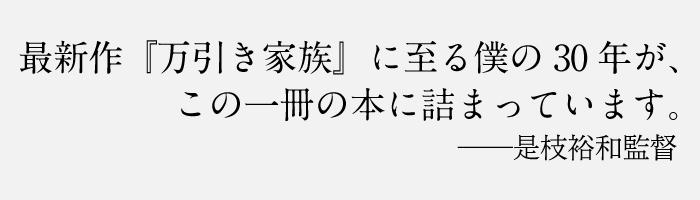
第1日目の今日は、『映画を撮りながら考えたこと』の第1章~終章からそれぞれ、是枝監督の映画や映画祭に対する思いが綴られている部分を中心に、引用をご紹介していきます。
●第1章 絵コンテでつくったデビュー作
しかし何よりいちばん辛かったのが、自分でがちがちに決め込んで描いた三〇〇枚の絵コンテに自分自身がしばられていたことです。コンテにしばられているとわかっていたら、コンテを捨てればよかったのですが、当時の僕にはそれすらわからなかった。周りはベテランぞろい、僕だけ初めての現場で、不安も大きかったのだと思います。能力のあるスタッフに助けられてなんとかゴールまで辿り着きましたが、たぶん現場で起きたおもしろいことを映画の中にはあまりすくいとれなかったと思います。港町にいたムクという名前の野良犬くらいでしょうか。コンテにないのに映画に登場しているのは。
――p23~24『幻の光』について
●第2章 青春期・挫折
「放送」とはいったい何なのだろう。僕は悩みました。報道ではないテレビドキュメンタリーはどういう根拠で相手にカメラを向けられるのだろう。知る権利ではなくカメラを引き受けてもらう被取材者の根拠をどう捉えたらいいのだろう。そこを構築しないと自分がカメラを持つ理由・根拠がないのです。
――p68『しかし...~福祉切り捨ての時代に~』について
●第3章 演出と「やらせ」
「再現」ではなく「生成」にどう立ち会うか、という姿勢の先にしかドキュメンタリーは生まれない。この「生成」に自らと取材対象を開いていくための演出と再現に自らを閉じていくための「やらせ」は区別されるべきだと僕は考えています。しかし、新聞を中心とする多くの活字メディアは、その目的の区別をせずに手段としての「やらせ」をすべて断罪しようとした。これはやはり映像に対するリテラシーが活字の側も低いことが原因だと思います。
――p108『ドキュメンタリーの定義』について
●第4章 白でもなく、黒でもなく
テレビは犯罪事件を扱うときに「情緒的に哀しみの対象として出てくる被害者」対「攻撃の対象として出てくる加害者」という単純な図式にあてはめようとします。僕はその構図からはみ出るような事件の直接の関係者ではない人間が、どうすれば事件を自分のものとして捉えることができるかを考えたくて、加害者側の家族を主人公にすることを思いつきました。
――p122~123『DISTANCE』について
●第5章 不在を抱えてどう生きるか
『誰も知らない』はカンヌ国際映画祭で八〇近い取材を受けましたが、いちばん印象的だったのは、「あなたは映画の登場人物に道徳的なジャッジを下さない。子どもを捨てた母さえ断罪していない」という指摘でした。僕はこのように答えました。映画は人を裁くためにあるのではないし、監督は神でも裁判官でもない。悪者を用意することで物語(世界)はわかりやすくなるかもしれないけれど、そうしないことで逆に観た人たちがこの映画を自分の問題として日常にまで引きずって帰ってもらえるのではないだろうか―。その考えはいまも基本的に変わりません。映画を見た人が日常に帰っていったときに、その人の日常の見え方が変わったり、日常を批評的に見るためのきっかけになったりしてくれたら、といつも願っています。
――p176『誰も知らない』について
●第6章 世界の映画祭をめぐる
映画祭というのは、「映画の豊かさとは何か? そのために私たちは何ができるのか?」を考える場です。映画を神様に譬えるつもりはありませんが、映画の僕(しもべ)として自分たちに何ができるのかを思考し、映画という太い河に流れる一滴の水としてそこに参加できる喜びをみなで分かち合う、それが映画祭です。
――p258
●第7章 テレビによるテレビ論
ときどき「なぜテレビをやるんですか?」と訊かれることがあって、僕は「ふいに出会うのがテレビの魅力だと思うから」と答えています。お金を払って劇場に観に行ったものだけが、人の心に残るわけではない。偶然見て強烈な印象を受け、その後の人生に少なからず影響を与えたテレビ番組というのが、人には何本かあると思うのです。それが僕の場合は、『帰ってきたウルトラマン』や、佐々木昭一郎さんのドラマです。
――p275
●第8章 テレビドラマでできること、その限界
僕は決して「家族がいちばん」だとは思ってはいません。ただ、ちょっと話が飛躍するかもしれないですが、「インターネットを漂っている人がなぜ右翼というかナショナリストになるのか?」。この問いを考えていくと、人とつながっている実感がない人がネットへこぼれ落ちたときに、彼らを回収するいちばんわかりやすい唯一の価値観が「国家」というものでしかなかったのだということに、気づかされるのです。現代の日本は、地域共同体はもはや壊滅状態だし、企業共同体も終身雇用制の終焉とともに消えたし、家族のつながりも希薄になっている。そこで、共同体や家族に代わる魅力的なもの・場所・価値観(それを「ホーム」と言ってもいいかもしれませんが)を提示できないかぎり、彼らは国家という幻想に次々と回収されていくでしょう。
――p328~329『ゴーイングマイホーム』について
●第9章 料理人として
『奇跡』『そして父になる』『海街diary』の三本は、僕が「作家」よりも「職人」を目指してつくった作品といえるかもしれません。いつだったか「職人になりたい」と言ったら「監督は作家でいてください」と返されたことがあります。何が違うのか考えたのですが、たとえば「旬の旨うまい魚をどのように料理したら、素材の持つ味を活かしながら、お客様に満足のいくものとして提供できるだろうか」ということを考えるのが職人なのであれば、監督の仕事というのはやはりそれに近いのではないかと僕は思うのです。(中略)。僕のキャリアでは分岐点となったこの三作のおかげで、自分のキャパシティはとても広がった気がします。
――p384~386
●終章 これから「撮る」人たちへ
この先の二十年で、何をどう撮るか。たぶん撮れて十本かなと思うと、これまでに実現できていないプロットは十以上あるから、そのうちのどれかはできない。これからやりたいモチーフも出てくるでしょう。それに映画監督は本当に体力勝負なところがあるので、五十代でしか撮れない規模のものはこの五~六年の間に撮っておきたい。もしできなかったら、同じ題材を六十代で別の切り口で撮るかもしれない。ホームドラマはたぶん七十代のおじいちゃんの目線でも、また撮れるかもしれない......。
――p409~410
是枝監督の、映画、そしてテレビでの作品づくりの技術や金銭事情など、具体的なお話から、考え続けているテーマ、映画という文化への思いまで、みっちりと詰まった本書、「万引き家族」を観る前に、あるいは観た後に、ぜひお楽しみいただけたらと思います。
「万引き家族」 2018年6月8日(金) 全国ロードショー
プロフィール
是枝裕和(これえだ・ひろかず)
映画監督、テレビディレクター。1962 年、東京生まれ。早稲田大学卒業後、テレビマンユニオンに参加。主にドキュメンタリー番組の演出を手がける。1995 年、『幻の光』で映画監督デビュー。2004年、『誰も知らない』がカンヌ国際映画祭にて史上最年少の最優秀男優賞(柳楽優弥)受賞。2013 年、『そして父になる』がカンヌ国際映画祭審査員賞受賞。2014年、テレビマンユニオンから独立、制作者集団「分福」を立ち上げる。最新作『万引き家族』で第71回カンヌ国際映画祭・パルムドール受賞。8回伊丹十三賞受賞。著書に『雲は答えなかった 高級官僚 その生と死』(PHP文庫)、『万引き家族』『歩くような速さで』(ポプラ社)、対談集に『世界といまを考える1、2』(PHP文庫)などがある。


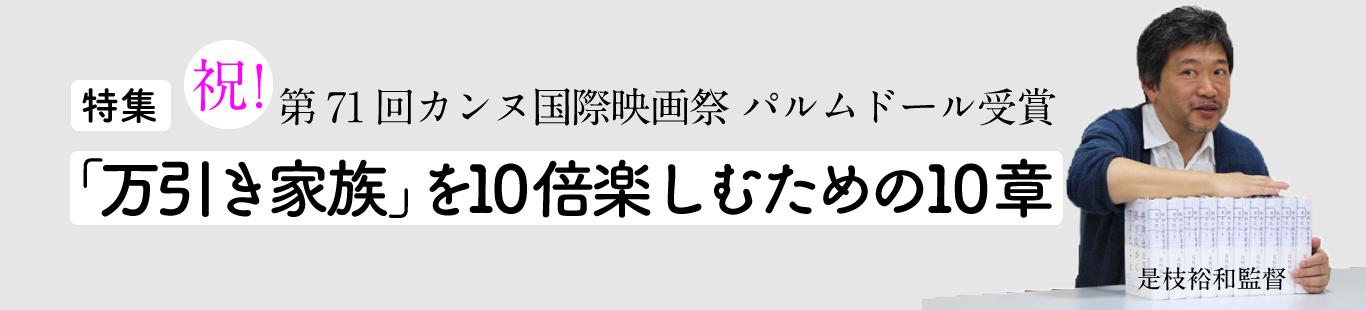




-thumb-800xauto-15803.jpg)
