第192回
「まともであることには価値がある――トランプ氏の言動に振り回されないために」小山哲さんインタビュー(後編)
2025.05.06更新
アメリカ大統領にトランプ氏が就任して以来、ウクライナとロシアの「停戦交渉」をめぐる報道が続いています。トランプ氏とゼレンスキー氏の口論、軍事支援の停止・・・大国の動向にざわつく今、本当に目を向けるべきはなんなのか?
長い歴史をふまえた見方、そして、中東欧の現地の人びとからこの状況がどう見えているかを知りたいと思い、『中学生から知りたいウクライナのこと』『中学生から知りたいパレスチナのこと』著者の小山哲さんにお話を聞きました。本日は後編をお届けします。
(取材日:2025年3月12日 構成:角智春)
ロシアに占領されるということが意味するもの
小山 この地域(中東欧)の歴史的経験としては、ロシアとの関係についても語らないわけにはいきません。ロシア帝国もソ連も、ウクライナやポーランドの人たちが暮らす領域に何度も力尽くで介入してきました。この歴史が、今もなお苦しい状況に向き合うときにどうしても想起されてしまうんです。
2022年2月にウクライナ侵攻が起こったとき、ロシアの戦車部隊がベラルーシ国境を越えて、キーウに向かって南下しましたよね。このときもっとも凄惨な暴力が振るわれた町のひとつが、キーウ近郊のブチャです。ロシア軍の撤退後、市民の遺体が通りに転がっている映像が世界中に流れました。このとき、後ろ手に縛られて射殺された遺体がいくつも見つかりましたが、ポーランドのメディアでは、これは第二次大戦中の「カティンの森」と同じだという議論が出てきたんです。
カティンの森事件とは、ポーランド東部に侵攻したソ連が1940年に起こした虐殺事件で、ソ連軍の捕虜として収容所に移送された約22,000人のポーランド軍将校が、カティンをはじめとする複数の場所で殺害されました。カティンの虐殺の現場は発掘されて殺害の状況がかなり詳しくわかっているのですが、捕虜の多くが後ろ手に縛られて後頭部を銃で撃たれて亡くなっています。
つまり、ポーランドの人たちにとって、今のロシア軍の振る舞いは、ソ連時代の集団的虐殺のメソッドを受け継いでいるのではないかというふうにも見える。そのような関係が事実として存在するのかどうかはきちんと研究する必要がありますが、彼らがそういう眼差しを向けていることはメディアを通じて伝わってきます。
中東欧の人びとは、ロシアの占領というものに「その状況だけは作ってはいけない」というほどの強い恐怖感があるんです。
たとえば日本では、ずっと抵抗を続けるウクライナについて、「これ以上兵士を犠牲にしないためにも戦争をやめて、ロシアに占領されたところは、暫定的であれ、いったんロシア領として認めるしかないんじゃないか」と主張する人がいますよね。でも、あの地域の人たちにとっては、ロシアの占領下で平和な暮らしが復活するとは到底思えない、という感覚がとても強いのだと思います。
――なかなか想像の及ばない感覚です。
小山 気をつけなきゃいけないのは、この恐怖感は「ロシア人が嫌い」というのとは次元が違うということです。そうではなくて、たぶん、歴史を通じて、ときどき表面的には見えにくくなったりすることもあるけれど、でも時代を越えて執拗に続いている帝国的なシステムに対する非常に強い恐怖感なんですよ。これを日本の人に感じとってもらうのはすごく難しいなといつも思うんですけどね。
ポーランドで起きている軍備強化
小山 もうひとつお話ししたいのは、今のポーランドの軍備強化についてです。
ウクライナ侵攻が起きてから、ポーランドはウクライナの避難民を積極的に迎え入れてきました。ただ、もうひとつの、ベラルーシ国境を越えてくる中東(シリア、マグレブ、アフガニスタンなど)の難民については態度がまったくちがって、国境を越えさせないように阻止しています。ベラルーシ-ポーランド国境は広大な森林地帯で、その中で行き場を失って命を落とす人たちもでてくる、というとても非人道的な状況が生まれています。ポーランドという国にある非常に根深いダブルスタンダードです。
そんな状況で、2024年5月にポーランドの国防省は「東の盾」構想という方針を発表しました。ベラルーシ-ポーランド国境は、EUの東の境界でもあり、またNATOの境界でもあって、ここをなんとしても守り抜くことが重要だ、という考えにもとづく構想です。ロシア軍がベラルーシを通過してポーランド領内に侵略する可能性を想定していて、巨額の予算を投じて、国境から内側50kmまでの地帯を衛星まで使って完全に監視するシステムを作り上げようとしているんですね。地雷を埋めるゾーンも設ける、そのためには対人地雷の使用を禁止した国際条約からも脱退する、と。
もはや、ベラルーシとの国境は、通常のやり方では越えられなくなるということです。これまでは鉄条網をかいくぐって難民が入ってくることもあったけれど、そんなのどかな世界ではなくなる。ポーランドはもはや、そこまでやらないと気が済まないような状態になっているのです。
成人男子の軍事訓練もやるといっています。ふだん銃なんか持たない人たちが、これから定期的に銃を持って実戦を想定した訓練を受けていく。訓練には必ず仮想敵がいるわけだし、倒すべき相手をイメージした標的を狙って撃つわけでしょう。
そういうことがくりかえされたときに社会がどうなっていくのかを私は気にしています。これもトランプショックの余波のように思えますね。戦争の影響は、本当にいろんなところに及ぶなと感じています。
まともであることには価値がある
小山 ウクライナ侵攻から3年が経った2025年2月24日に、国連総会で、ロシア軍の撤退を求める決議が採択されました。アメリカが反対に回って、波紋を呼んだ決議です。
この総会で、ポーランドのシコルスキ外務大臣がウクライナを支持するスピーチをしたのですが、そこで印象的な言葉を引用していました。
「まともであることには価値がある」("It's worth being decent.")という言葉です。
――おお。
小山 これはポーランドのバルトシェフスキという人物の言葉で、「まともであることには価値がある。たとえ、まともでいないほうが儲けられるとしても」と彼は言っています。
――すごい・・・。
小山 バルトシェフスキは1922年生まれで、ポーランドの外務大臣を二度務めた人なのですが、あの地域の現代史の危機をぜんぶ経験してきたような、ちょっと破格の来歴の持ち主です。
バルトシェフスキの本を手に語る小山さん
小山 まず、第二次大戦中は、ワルシャワ市内で一斉検挙にあってアウシュヴィッツに収容されています。戦争がはじまる前にバルトシェフスキはポーランド赤十字で働いていたのですが、この赤十字の介入のおかげで辛うじて収容所から釈放されました。その後、彼はドイツ占領下で地下活動に参加し、ユダヤ人の救援活動にかかわり、1944年のワルシャワ蜂起ではナチス・ドイツの占領からの解放をめざす国内軍の兵士として戦いました。
戦後は、こんどはスターリン体制のもとで、ポーランドの社会主義政権によって投獄されています。彼は、全体主義的な体制を批判する側でずっと体を張り続けていて、「連帯」運動(ワレサらが主導した、ポーランド民主化につながる労働運動)の中心人物にもなりました。独立後に外務大臣となってからは、東西統一後のドイツと関係を再構築し、EUの拡大に貢献するなど、大きな外交的達成を成し遂げています。
そういう、壮絶であり壮大な人生を歩んだ人物が、「まともであることに価値がある」と言っていることに、私はとても重みがあると思うんです。
彼は辛くも生き延びましたが、まちがいなく、「まともである」がゆえに殺された人たちのこともたくさん見ている。それでもなお、こう言ったんですね。
――はい。
小山 バルトシェフスキは2015年に亡くなりましたが、かつてこの人物が務めた地位を引き継ぐ外務大臣が、自分の主張を支える考え方として彼の言葉を引用したことは、とてもポーランド的だと思いました。「まとも(decent)」という言葉――ポーランド語では「プシズヴォイティ(przyzwoity)」と言います――は日本語にうまく訳すのが難しいのですが、少し補って言えば「こういうことは普通してはいけない、という感覚をもっていること」といったニュアンスになるでしょうか。これが今、世界に欠けているとても大事なものだと思います。
このまともさというのは、相手を尊重して、相手からも尊重されるという相互関係の中で成り立つものであって、だからこそ、バルトシェフスキは外国の指導者からも非常に尊敬されていたし、彼の言い分なら聞くという人が多かったのだと思いますね。
彼はユダヤ人をホロコーストから救った人物としてイスラエルの名誉市民に認定されていますが、外務大臣としてパレスチナ問題にどう関わったのかについては、きちんと調べる必要がありそうです。それでも、この言葉自体は、私は良い言葉だと思います。
――そうですね。胸に刻みたいです。ありがとうございました。
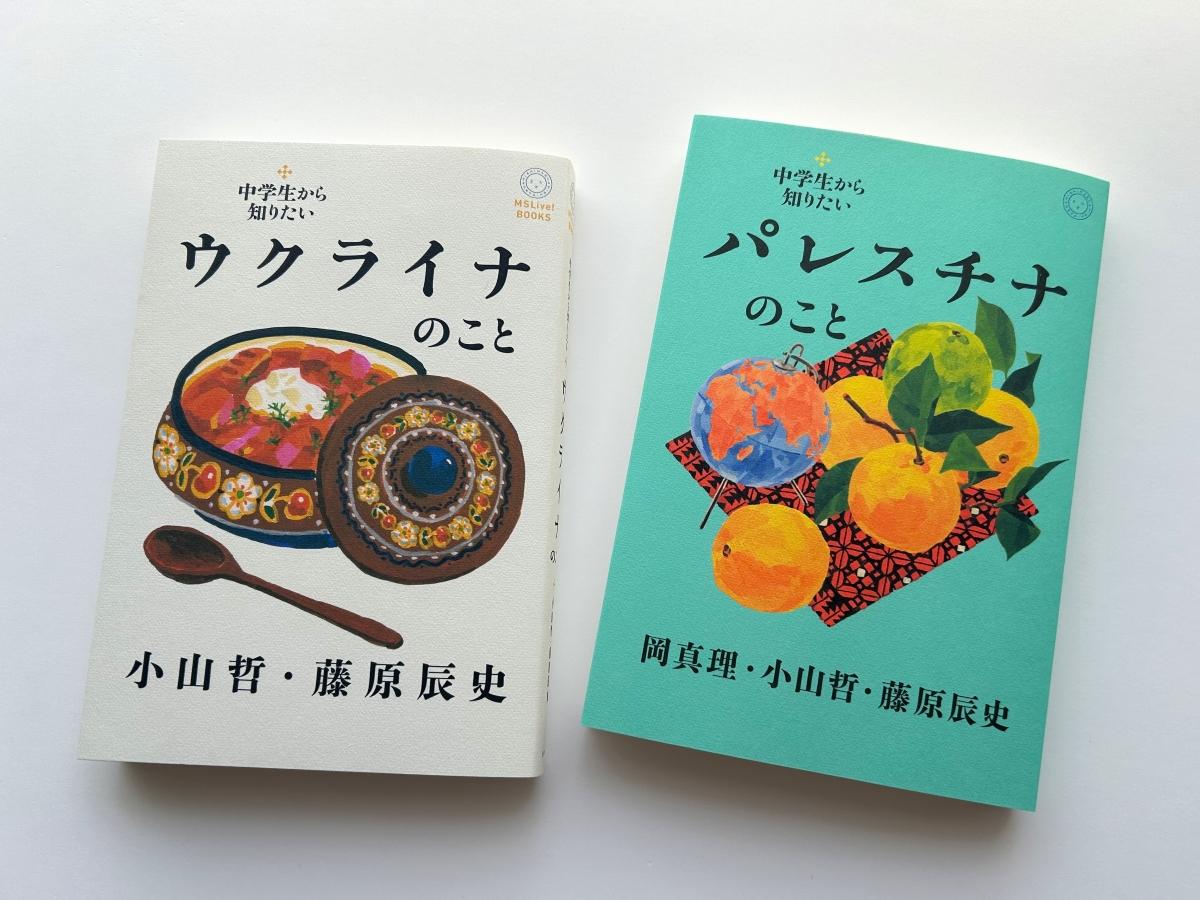 『中学生から知りたいウクライナのこと』/『中学生から知りたいパレスチナのこと』
『中学生から知りたいウクライナのこと』/『中学生から知りたいパレスチナのこと』
(終)



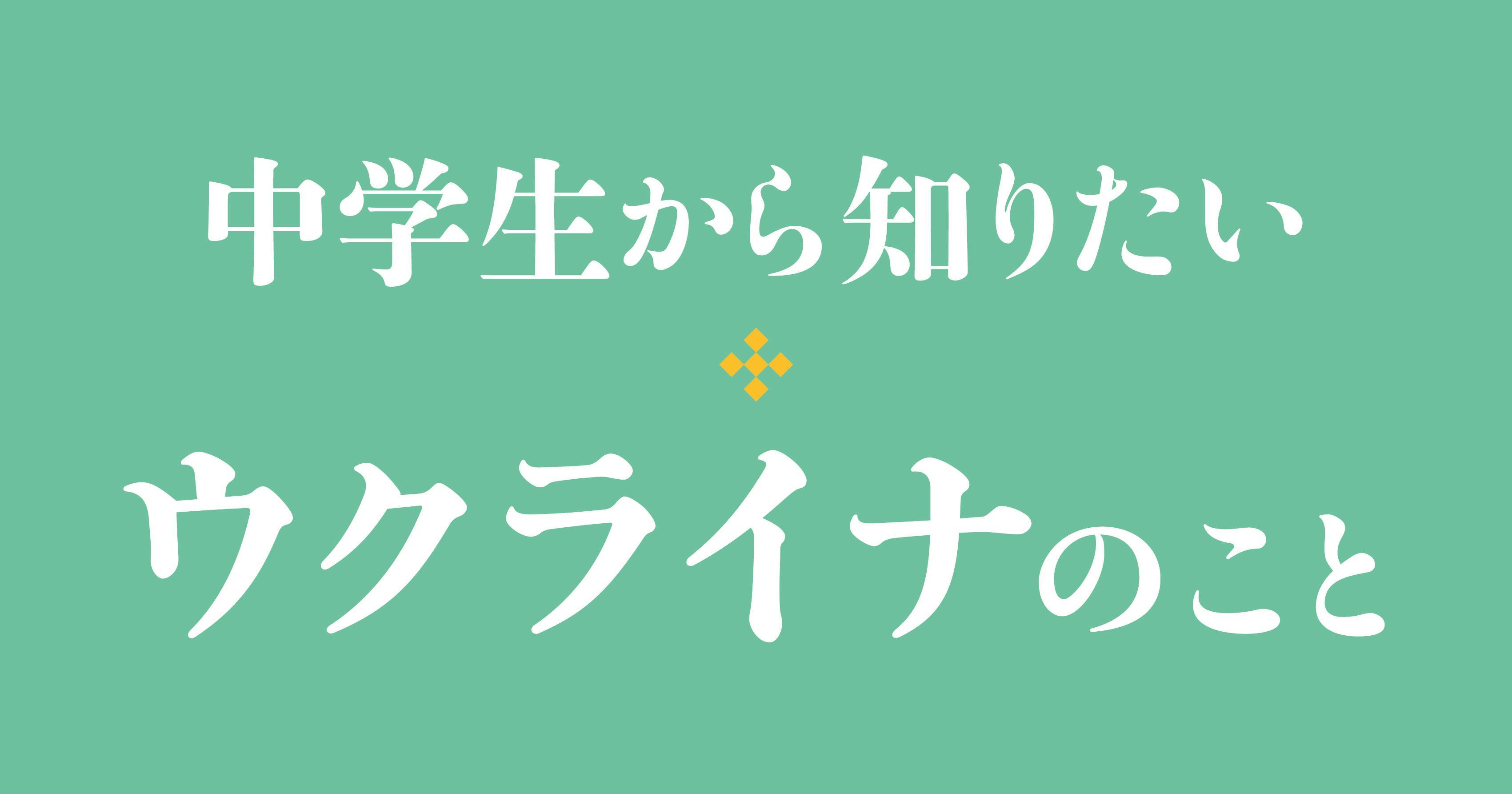
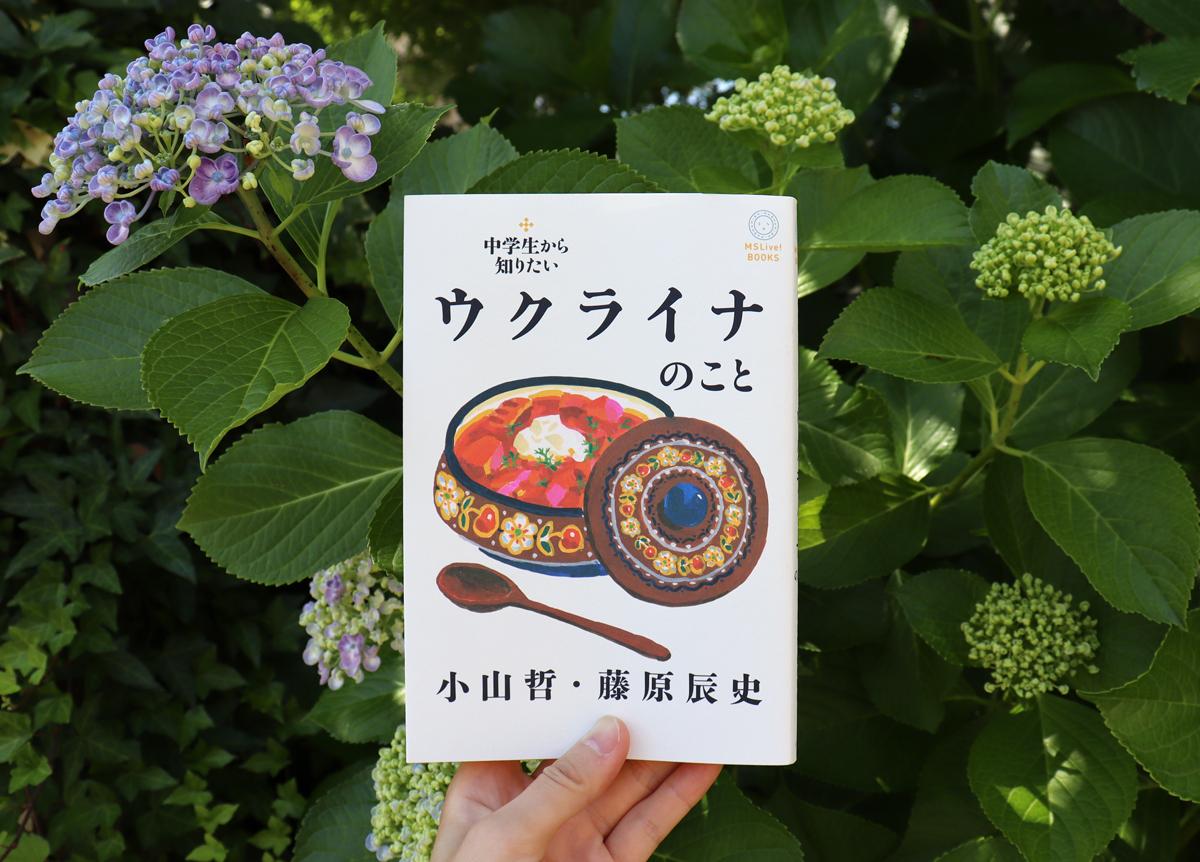
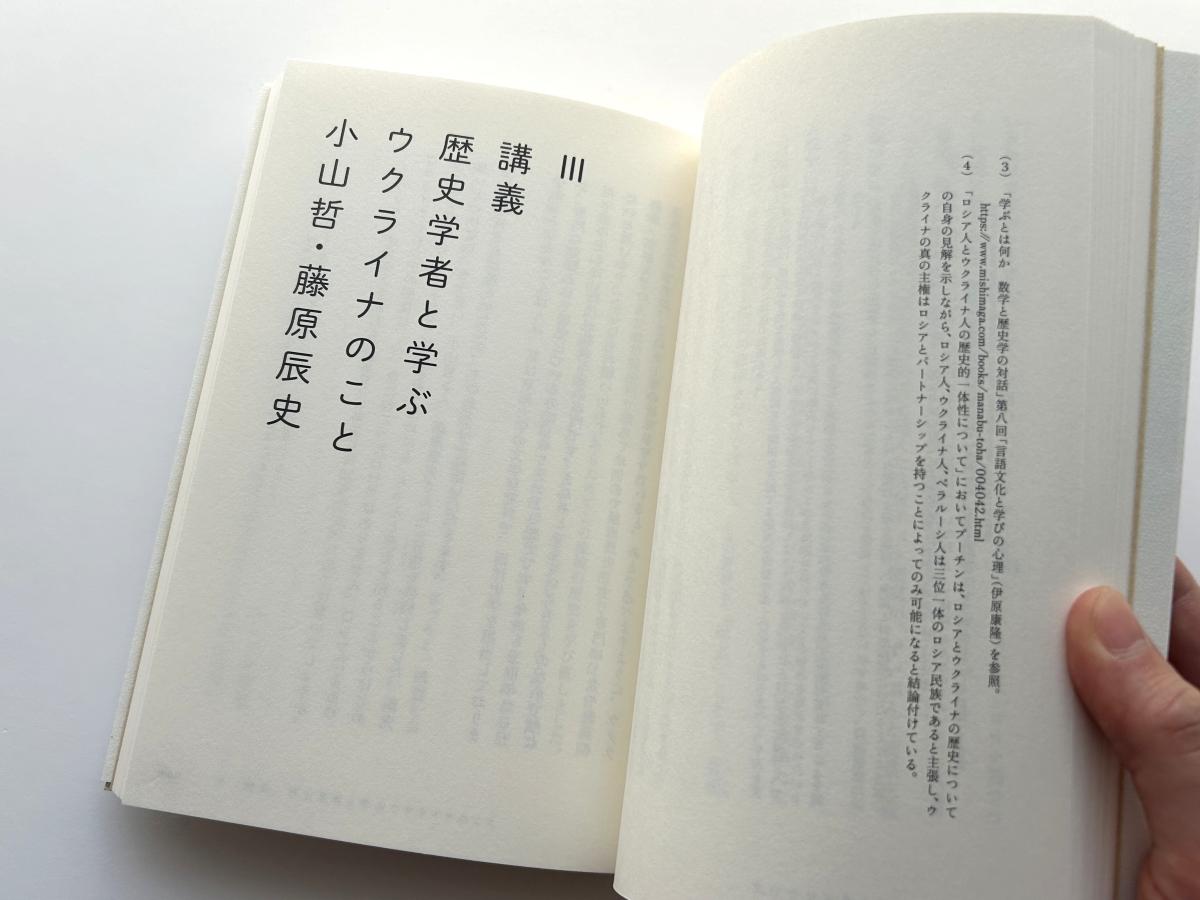




-thumb-800xauto-15803.jpg)
